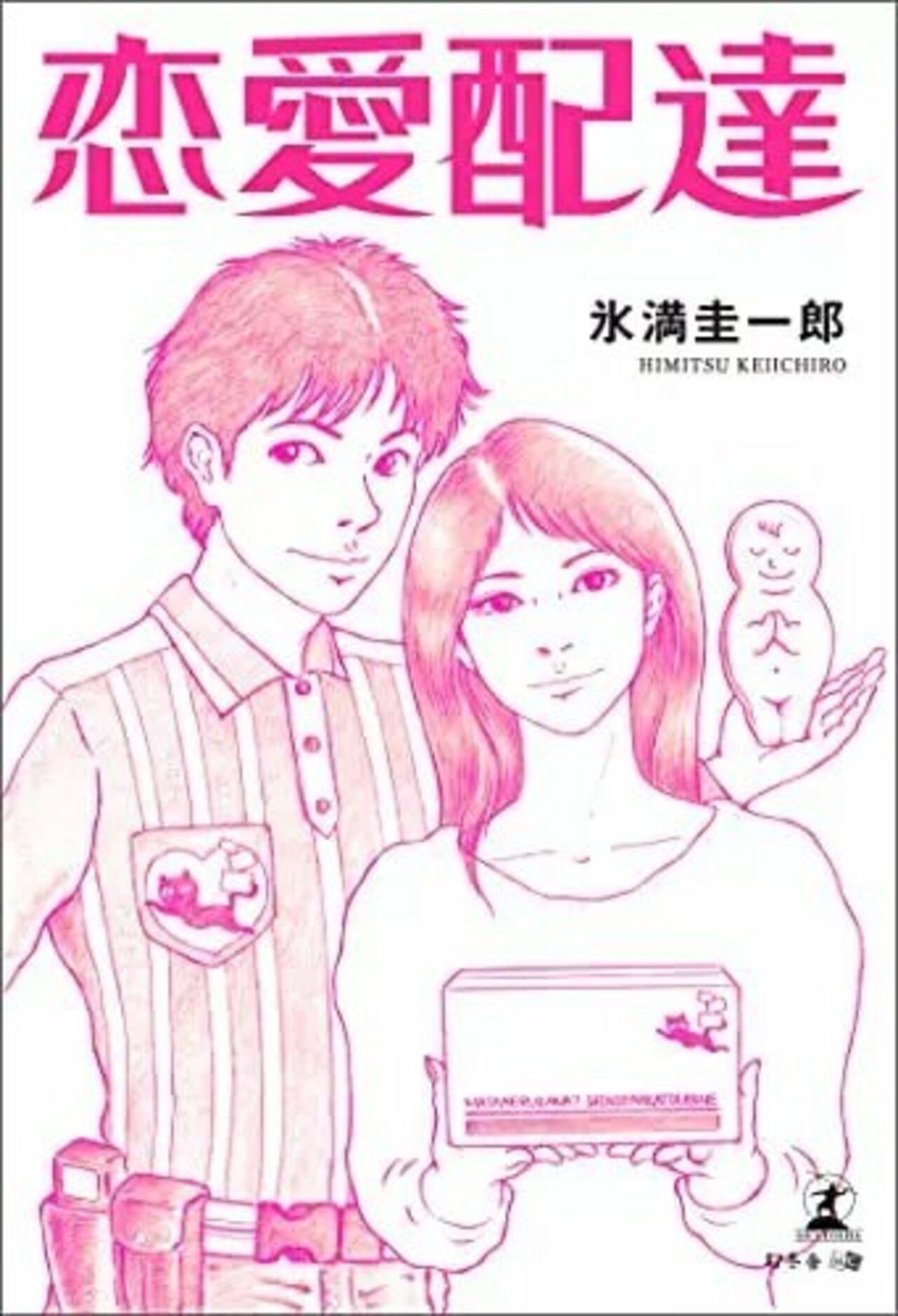その場所で一人涙を流す自分に理由も聞かず、「香織さんも花の雫をたくさん花にあげてね。それが彼女たちの養分になるから。私たちも高校の時にここでたくさん花の雫を寄付したの。時は流れて人が変わっても彼女たちの前ではみんな同じことを繰り返してるのよ。彼女たちはそれを長い間黙って見守ってくれてるの。彼女たちの中で花時計が時を刻んで季節は巡っているんだけどね」と言って慰めてくれた。
そんな心優しい優海を慕って彼女の勤める大学の教育学部に入学し、彼女の担当する植物生態学の講義を選択して学んだ。
卒業後は母校に赴任し彼女の息子の担任になるという不思議な縁を感じた。
そんな彼を目の前にして、橘は自分の高校時代に重ねて考えていた。
これからの三年間は子供から大人への架け橋を渡らなければならない※モラトリアム。
その間に試行錯誤を繰り返し、『自分とは何か』の問いに対する明確な答えを探さなければならない。それは自分の存在価値を求め、そこに自分に合う役割を見つける。
ひいては自分の使命を突き止めることにも繋がる大切な期間。
そしてその三年間はあっという間に過ぎ去ってしまう。自分がどう立ち向かっても、抗えない辛い現実がそこにあるということをこれから経験していくに違いない。
その間に失わなければ得られないものがあるということには彼はまだ気づけていないだろう。
それを失って始めて大切だったと気づくものがあるということを。
そしてそれは全てを経験してから初めて気づくものだということも。
でもその悲しく苦しい経験を乗り越えていかないと大人にはなれない。
それを経験したら彼の母親がしてくれたように私が彼に寄り添ってあげよう。
たとえ、彼にとってそれがどんなに辛いことだとしても……。