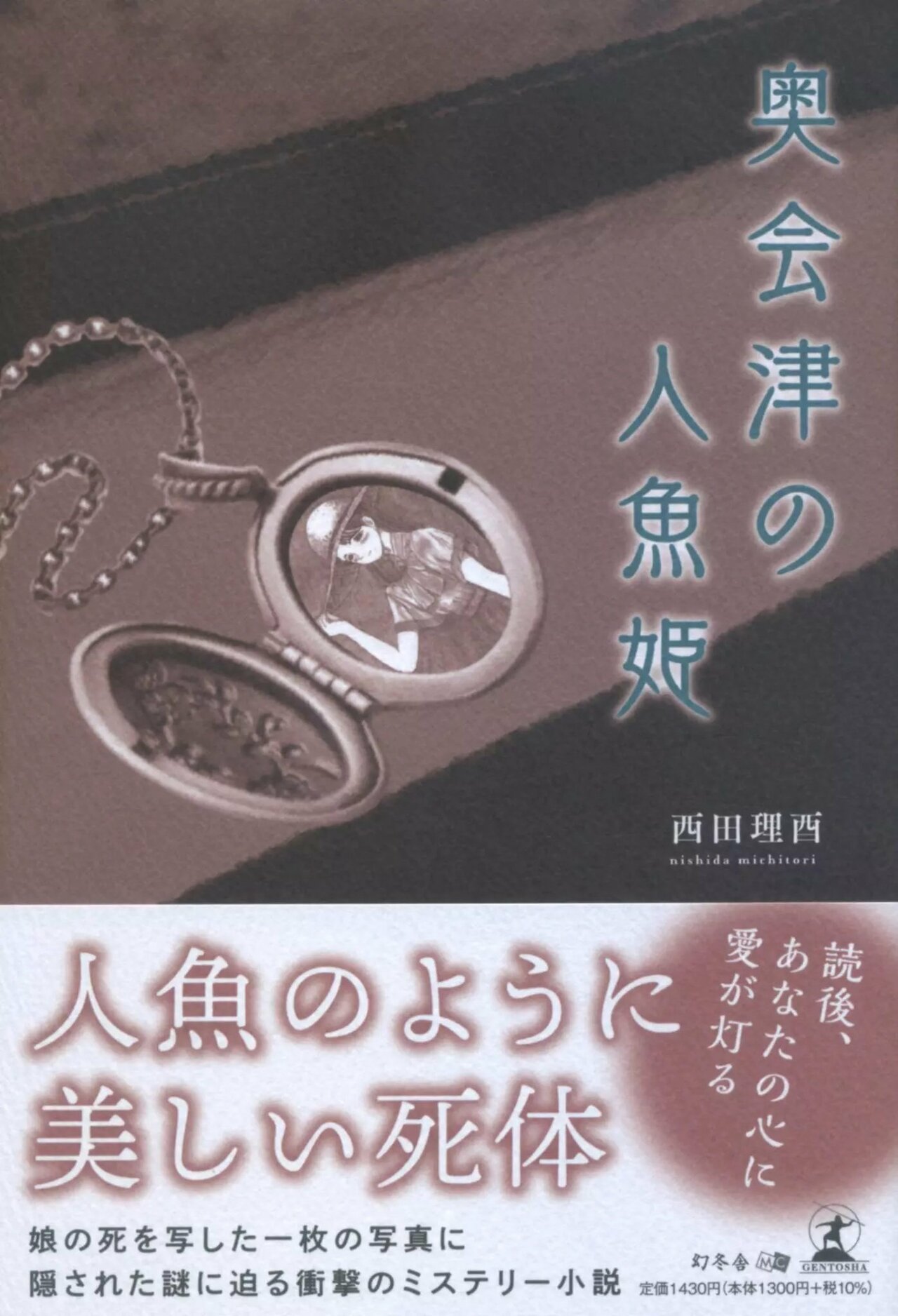千景の、自由の利かない体に抗いながらの魂の叫びは、さらに続いた。
「自分が何よりも大事にしているものが、まったく別のものであったことを知った時の衝撃をお前は知っているか? 今まで見ていた世界が、がらがらと音を立てて瓦解していくあの感触を。まるでオセロの駒のように、白と黒が入れ替わっていくあの空虚感を。
しかも最も恐ろしいのは、問題の本質を俺だけが知らないまま、当たり前のように時間だけが過ぎていくことだ。そしてほどなく俺はこの世から退場していなくなる。なぁ鍛冶内、こんな不可思議なことがこの世にあってもいいのか? 他にこれ以上理不尽な出来事が、この世界に存在するというのだろうか」
苦悩する千景の様子は、痛々しいほど切実だった。
「でも俺はすぐに気を取り直したよ。しばらくは湖面を見て、ぼんやりしていた俺だったが、その乙音と名乗っている娘に、俺の心配事を気取られるのが得策ではないことを、俺の中に住む第六感が忠告してきたからね」
そこまで話すと、山頂手前で休憩を取る登山者のように、大きな息を一つ吐いて、鍛冶内のほうを見た。
「俺が知りたいのは単純なことだ」
空虚な間が流れた。鍛冶内は言葉を失って、ただ千景の顔のしわを見つめていた。
「あの日亡くなったのが、汐里でないとすれば、亡くなったのは乙音以外に考えられない。乙音と汐里の間に何があって、俺の知らないところで何が起こっていたのか、それを考えるといても立ってもいられなくなる。いつも俺を豊かな愛情で包んでくれていた、あの優しくて献身的な乙音が俺の知らないところで亡くなっていただなんて、考えただけでも俺は気が変になりそうになる。
俺が何かの異変を感じ取れていたなら、ひょっとするとそれが避けられていたのではないか。そんなことを思うたびに、自分のふがいなさに涙が止まらなくなるんだ」
千景のしわがれた声はいつの間にか、かすれた涙声へと変わっていた。
「なぁ、鍛冶内。お前に無茶なお願いをしている自覚は十分にある。だが体の自由を奪われつつある俺にできることなど、もうほとんど残されていない。学生時代から友だちなどほとんどいない俺にとって、お前しか頼める相手がいないんだ」
鍛冶内は、そこまで話して疲れ果てている様子の旧友が、絞り出すように言ったこの夜最後の一言を聞いた。
「俺に代わって真相を調べてくれないか、鍛冶内」