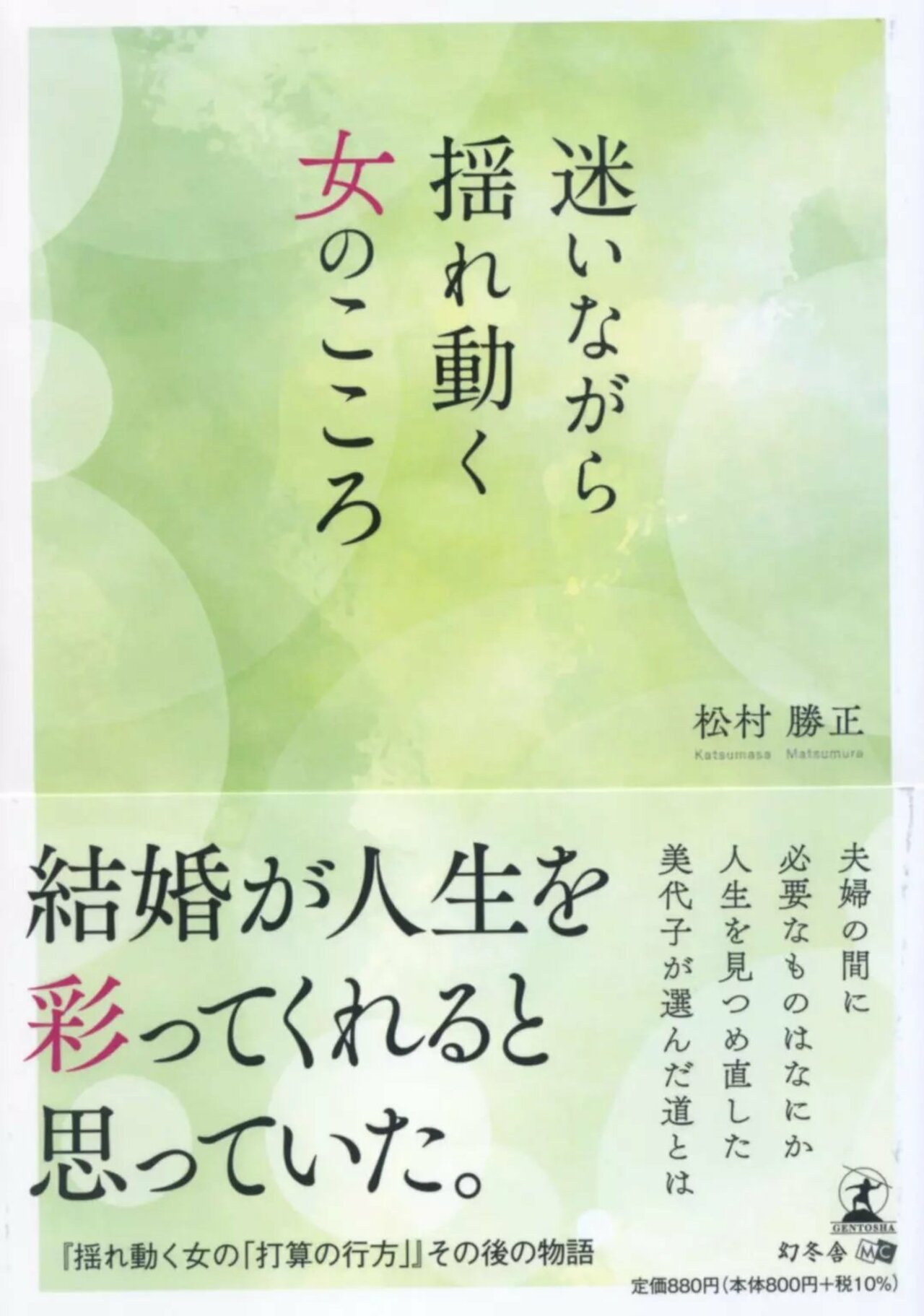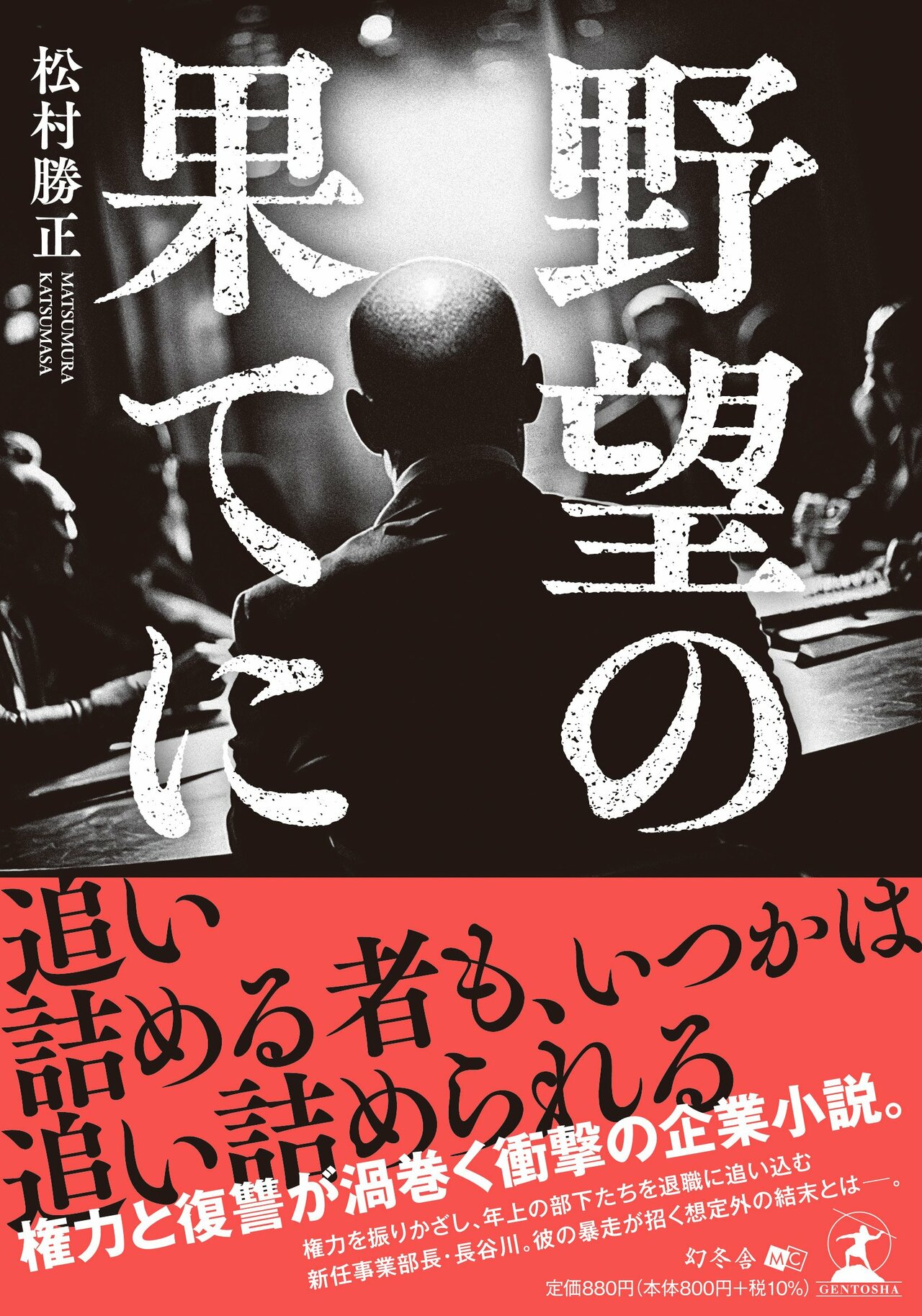美代子は観察気味に美月の顔の表情を見ていたが、特にいつもと違うような様相ではなかった。でもどうしても引っかかることがあった。あの夜中に聞こえたのは女性の声、この家には私以外、美月さんしかいないから、どうしてあんな時間に悠真の部屋にいたのか解せない。しかし一方で、美代子は嫉妬心とか敵対心など、全然湧いてこないから不思議、冷静になっている自分が怖いと感じていた。
悠真に問いただす気はしなかった。裏を返すと悠真に対する愛情が薄いものなのかもしれない。私たち夫婦は同居人と割り切っていたから、冷静になれたのだ。
もう少し今後の様子を見てみようと思った。
美代子には思い当たる節もあった。スペイン旅行から帰ってきて、入浴介助を申し入れたり、パエリアの料理を作ったりして、美月さんの女心に火を点けてしまったのかもしれない。山形家に家政婦として来て悠真さんの介護を献身的に姉弟のように接してきたといえども、女の部分がどこかでくすぶっていたのだ。そのように分析していた。
「ごちそうさま、美味しかった」
「良かったですね。そうだ、今日は悠真さんの定期健診とリハビリなんです。出かけるついでに何か買うものありましたらどうぞ」
「ありがとう、特にないわね。今日、私も久しぶりに友達と会うことにしているの、結婚前に会って以来だから楽しみなのです」
気のせいかもしれないが、美月の応対がいつになく瞳が輝いていて、明るく感じた。心の片隅では女性にありがちなホルモンが作用しているのかもと思いながら、少し意地悪な質問をした。
「美月さん、何かいいことでもありました?」
「どうしてですか?」
「いつもより、肌つやがいいから」
「いやですよ、もう四十のおばさんですから、からかわないでください。美代子さんにはかないませんよ」
二人は顔を見合って大きな声で笑った。