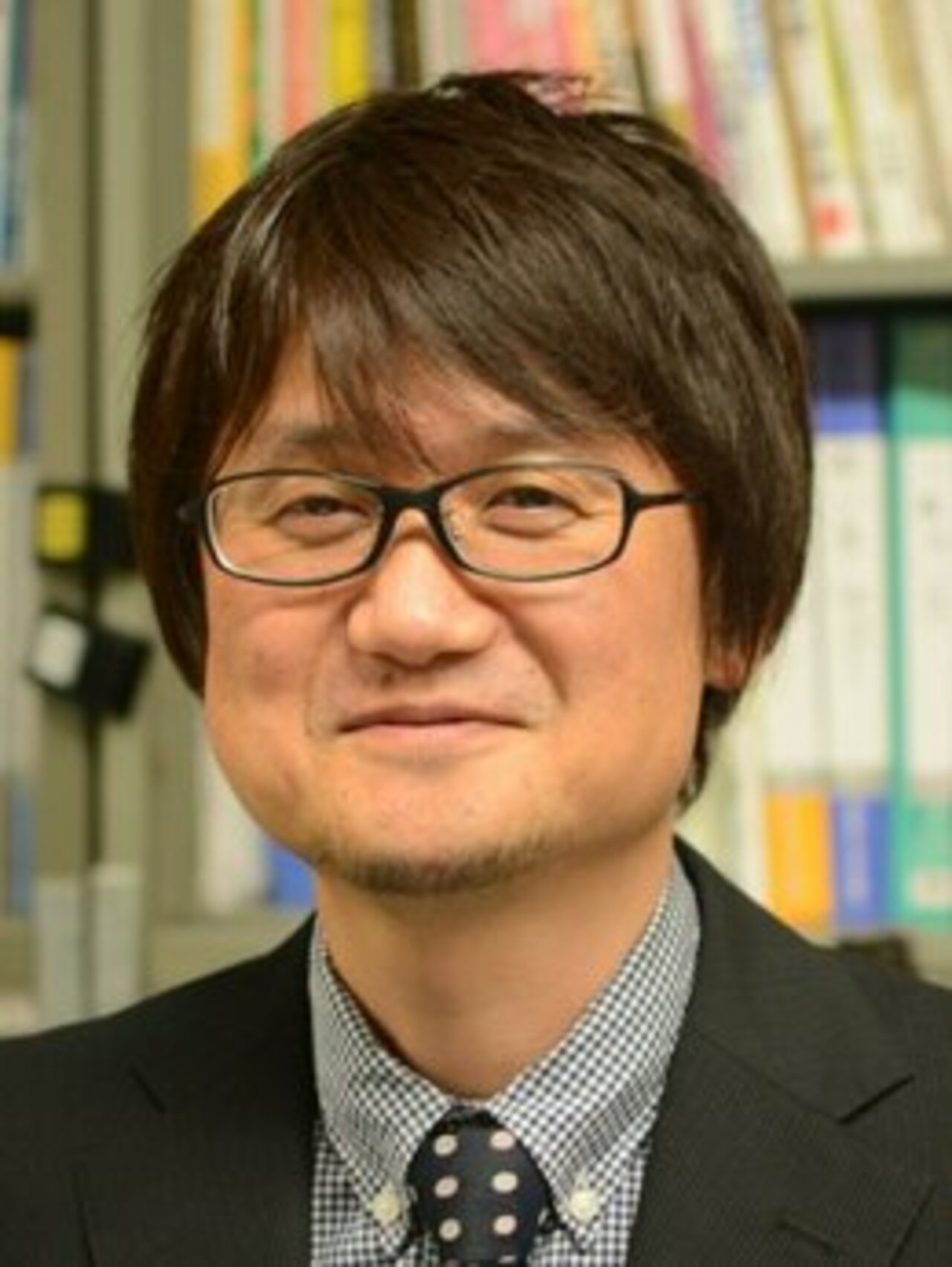3
新大久保駅を出て薄暗いガード下を抜け、大通りの右手にほんの人一人通れる程度の狭い石段がある。途中左右に2度ほど曲がる。階段を上るたびに太陽の光が当たらず暗くなっていく。階段の途中、足元に小さな木の看板がありマジックで乱雑に「イスラームビジネス研究所」と書いてある。右矢印のマークと共に。
そこには小学校の体育館の横にある物置小屋を想像させる木造の建物があった。ケントが近づいてくるのを扉ののぞき穴から見ていたのは大学時代の同級生のユウだ。袖口が擦り切れたような体には大きすぎる不釣り合いなグレーのスーツを着ていた。随分とやせ細ってもう何日も太陽に触れていないような不健康そうな白い肌だ。
「久しぶり。元気?」と扉を開け、ケントが爽やかな声で言った。ユウはその声に不快感を覚えた。苦労を知らない純粋さが表情から溢れていた。ケントは昔とかわらず若々しい。いい給料もらってさぞいいものを食べてるんだろう。肌がツヤツヤしている。髪型も整っている。毎月行きつけの美容院で「いつもの感じで」と言ってカットしてもらっているのだろう。学生時代と同じように。ユウは苦々しく思った。
「ケントくんから連絡をもらえると思わなかったよ。大学院も出てあの有名なエリザス製薬で研究員をしているケントくんが、なんで怪しげなハラールの世界に興味を持ったんだ」
「やっぱ怪しいんだ」と言うケントの声を背後に聞きながら、誰もいない事務所に一つだけのテーブルに案内した。は一番陽の当たらない場所だ。何人もが腰掛け、その人達の陰を吸い取ったような、黒く変色した椅子にケントは浅く腰をかけた。
は、ケントと向かい合うように座り、テーブルにあった灰皿から親指ほどの折れ曲がったタバコを拾い上げ、火をつけてから言った。
「怪しいからハラール認証団体が毎月のように増えてるの、知ってるだろ
「怪しいって言っても、イスラーム教の教義をクリアしてるか、基準に基づいて判断してるんだよね?」
大学時代と変わらず正論を正論らしく丁寧にしゃべる顔になぜだか苛立ちを覚えた。それに比べて自分はなぜ、こんな汚れた狭い部屋で毎日過ごしているんだ、どこで人生が狂ってしまったんだと、ケントの顔を見ながら考えていた。
「わかってないなぁ。ケントくんは。食品業界はドロドロしてんだよ。正しいか間違ってるかなんて、その場の雰囲気でコロコロ変わるんだよ。つまり、はっきりとした基準なんてないんだよ。だから我が社のような団体が必要なんだよ。インターネットにハラール認証基準です、な〜んて、わかりやすい表とか出てたらどうなる? 我が社はグシャッ、だよ。グレーなものをグレーに維持しつつ、顧客の要望を満たす。これがプロ。わかるかな?」
ケントの表情が曇っていくのがユウに分かった。ケントはタバコを吸わない。煙が嫌なんだ。この苦い臭いが汚れた自分を浄化してくれる。この浄化作業を始めたのはいつだろう。浄化が必要と感じた時にちがいない。いくら考えてもタバコを吸い始めたのがいつか思い出せなかった。タバコを指で弾いて灰皿に入れた。
「でもね、ユウ。会社から相談を受けて、商品が基準を満たすかを判断する。そして認証マークを貼ったり、認証状みたいなものを発行する。じゃ、やっぱり基準があるってことじゃないの?」
大学時代と変わらない純粋な目をしている。その目には俺はどう映っているのか。考えたくもなかった。
「ケントくん。実験と違うんだよ。実社会は。再現性がないのが実社会。わかるかな?」
ユウはうんざりだと言わんばかりに、灰皿の中を覗き込み、まだ吸えそうなタバコを探した。このタバコが俺の目をますます濁らせていく。社会で経験をつめば社会がよりよく見えると思ってきた。現実は違った。ますます濁っていく。肺が濁っていくのと同じ様に。
「じゃね。ユウね。商品の具体的なこと、原材料とか、工場の製造ラインとかを伝えたら、基準に合致するか判断できるのかな?」
子供だなと思った。当たり前のことを当たり前のようにしゃべるケントは幼稚な子供だ。詳しく話をしても結局持ち帰り、上司に判断をあおぐんだ。自分じゃ決められないお子様だ。詳しく話すほどのことはないと思った。
「もちろんでございますよ。ケントくん。それが我が社の仕事ですので。この審査概要をお渡しします。よくお読みになって社内で審議ください。それでいいよね。ケントくん」
これで充分だ。書類を見れば済む話だ。
これ以上、ケントと話を続けると、楽しく輝いていた大学時代を思い出してしまう。あれはもう過去のこと。過去というより前世のことだ。忘れてしまいたい。頭の中でもやもやとしたその記憶を吹き消してしまいたいと思った。椅子から立ち上がるとケントも立ち上がった。もうこれでおわりにしたかった。ケントは頭を掻きながら書類を鞄にしまった。「また今度、ゆっくりね」と言ってケントは事務所を出て行った。ユウはケントの顔を見るのが嫌だった。
ケントが出ていったあと、テーブルに戻り灰皿から吸えそうなタバコを探した。
何をきっかけにタバコを始めたのだろう。大学時代には吸わなかった。大学では優秀のユウと呼ばれていた。ケントより俺の方が優秀だった。実際のところ仲間内で成績は一番だった。親に感謝するほど手先は器用で、食品に含まれる成分の分析は得意で、ビューレットを使った実験では、滴定値の誤差が0.010ということも自然にできた。他の学生がなぜうまく操作できないのか分からなかった。期末試験の前になると仲間に出題傾向をまとめたレポートを配布した。それでも分からない仲間には丁寧に指導もしてやった。
医学部を目指していた。でも国立大学に入るほどの学力はなく断念した。私大の薬学部も考えたが卒業までに6年間かかる。親に相談したが、「学費が高いし、普通でいいんだから」と言われた。学費が安く就職にも有利で、理系科目のうち得意な化学が活かせる学部を探すと、管理栄養士の国家資格につながる大学を見つけた。「食品成分は化学物質で出来上がっている」という化学の教員の言葉にも影響を受けた選択だった。
大学の仲間のできの悪さに辟易することもあった。俺の学力はずば抜けていた。いずれはこの大学で教授になるだろうとの噂まで流れていた。しかし教授になるには必須の大学院には進学しなかった。その選択がまずかったのかもしれない。2年間の大学院進学がリスクに思えた。「人並みに4年間勉強すれば充分じゃないのか」との親の言葉もあったし、大学院進学者を就職のできない金持ちの「入院患者」と揶揄する言葉を耳にしたことも理由の一つだ。事実、金銭的にもできない選択だった。短いタバコはすぐに終わる。灰皿におしつけた。
ケントは勉強ができるタイプではなかった。仲間の中で一番できが悪かった。ケントの面倒をみたのは俺なんだ。俺のおかげでケントは期末試験をくぐり抜けたんだ。ケントは実験では失敗を繰り返し実験器具をよく壊していた。そんなできの悪いケントを励ましたのも俺だ。「ケントは優秀だと思うよ。なんて言えばいいかな、センスがあるっていうのがピッタリだよ。結果の解釈の仕方が素晴らしい。教科書的な解釈に飽き足らず自分なりの解釈ができる。実際に皆同じ結果なのにケントは実にユニークな解釈をする。これは持って生まれたセンスだよ」と褒めたことを覚えている。そうだ、俺がそう言ったからだ。
これまで気にならなかった灰皿のタバコがひどく汚れて見えた。
タバコの残骸が体のあちこちで腫瘍となって体を蝕んでいく。流しに灰皿を置き、水を少し流し入れた。
そうだよ。ケントは俺の言葉に影響を受けて研究者を目指したんだ。「優秀な同級生に褒められていると両親に話した。それもあって大学院に進学する許可を得た」。そう言って俺に感謝してくれた。もちろんケントの家は比較的裕福だった。だからこその今があるんじゃないのか。それら全てが今のケントを作り上げている。一流企業のエリザス製薬勤務につながっているんだ。
灰皿から水が溢れた。ひどく濁った水だ。
だとしたら、俺に礼のひとつも言ってほしい。俺によって今のケントがあると言っても言い過ぎでない。それなのに、なぜケントがエリザス製薬で、この俺がこんななんちゃら所で働いてるんだ。人生の分岐点は大学卒業時だ。就職した会社はいい会社だった。給与も良かった。品質管理部門も俺にはあっていた。ルーチンな仕事で公務員的で最高だった。あれさえなければ安泰だった。
ユウは灰皿の中身をそのまま流しに捨てた。メガネを外して水道水で顔を洗った。
やけに冷たく感じた。
数日後、ユウはエリザス製薬にいた。ホテルのような豪華なレセプションの横には、ガラスで仕切られたいくつものミーティングルームがあった。ユウが待っていると、ケントと女性の姿がガラス越しに見えた。ケントより小柄な女性は、黒のハイヒールに白のタイトなパンツ、薄いピンクのシャツの上に薄いブルーのカーディガンを羽織い、モデルのような身のこなしで歩いてきた。
「本日はご足労いただきありがとうございます。健康食品部新規食品開発課の鈴木由美と申します。ハラールについては全く理解していないものですので、ご教示のほど宜しくお願い致します」と、由美が頭を下げると、なんとも言えないいい香りがした。
「鈴木ケントさんとは同じ大学出身です。そうは言っても私とケントさんは頭のできが全然違います。ケントさんは大学院にも進学し、そして現在このような大企業で勤務されています。同期として誇らしいんです。今回、連絡をもらい光栄です」とユウは笑顔を作り、話を続けた。
「私は、大学卒業後、食品会社の品質管理部門におりました。商品パッケージに表示する内容物、例えば食物繊維などが表示通り含まれているか、チェックをする仕事です。3年間勤めたのち、このイスラームビジネス研究所に転職しました。自分でも言うのもなんですが、食品の表示の基礎を経験したのち、応用編としてハラール基準に関わっているわけです」
ユウはいくどとなく繰り返してきた言葉を頭を使わず、ただただ口から出していた。喉の奥にカセットテープが組み込まれているかのように。
「では、まずハラールの概略をお話しします」
いつものように説明した。イスラーム教の経典、キリスト教の聖書みたいなものをクルアーンと呼ぶ。その中に食事に対する注意事項とか礼拝の仕方や頻度などが書かれている。しかし、その書かれ方はルールブックと呼ぶような作りではない。「食事」とかの項目分けなどされていない。簡単に言うと、神の言葉を受け取ったムハンマドという人が、神の言葉をそのままの口述形式で記したものだ。そこにはこんな記述がある。
「……豚を食べてはならぬ……アルコールはよろしくない……」
これを根拠にイスラーム教徒は、豚肉を食べない、アルコールを飲まないことを良しとしている。この良い行いが、「ハラール」なのだと。そこで我々、イスラームビジネス研究所では豚、アルコールの混入がないような商品作りをお手伝いしている、と説明した。
「では御社、イスラームビジネス研究所ではハラールの判断をどうしていらっしゃるのですか?」と鈴木課長が言った。いつものように答えた。
「委託契約しているイスラーム教徒に判断してもらいます。マレーシア人です。マレーシアは実はハラールの基準を国が定めています。そんな国、ほかにないんですね。マレーシアは多民族国家です。主にマレー系、インド系、中華系ですが、インド系、中華系の才能ある人達が国内でのビジネスに成功し、マレー系は隅に追いやられた感じでした。国内での民族のバランスを取る形でマレー系を優遇する必要があったんです。マレー系の多くはイスラーム教徒です。それを分かりやすく目に見える形にしたのがハラール基準です。国の認証マークを表示することでマレー系の存在を強く示したものですね」
由美の横に座り、静かに聞いていたケントが我慢しきれないという風に発言した。
「そのマレーシアのイスラーム教徒の方は国家公務員で、基準を判断する資格を持っているのですか?」
よくある質問だと言わんばかりにユウは目線をケントから由美に向け、静かに丁寧に言った。
「我々が委託契約している方はマレー系です。イスラーム教徒が集うモスク、キリスト教徒にとっての教会ですね。そこで重要な立場にいる方です。イスラーム教という宗教に非常に詳しい指導的立場の方です。その方の判断ですから我々も信頼しています」
ユウには、この説明が嫌だった。奥歯に物が詰まったような言い方というが、そのとおりだった。頷きながら説明を聞いていた由美は言った。
「そうなんですね。じゃ安心ですね。宗教観に根ざしたハラールですものね。イスラーム教に詳しい方に判断いただくのが一番ですよね。それにそもそも食べてもらうお客様はイスラーム教徒の方々ですからね」
この答えにすんなり理解を示す由美にユウは少し驚いた。本気で取り組もうと思っていないことが透けて見えるようだった。
「ありがとうございました。よくわかりましたわ。では、予算のこともありますので、上司とも相談し今後のことは改めて連絡致します。今後とも宜しくお願い致します」と由美が椅子から立ち上がって挨拶をした。
ユウも立ち上がり、エリザス製薬を後にした。
会社を出たユウはケントのことを羨ましく思った。また、由美の深く考えていないところが腹立たしかった。あんな風に業務だと割り切って考えればよかったんだ、と前職のことを思い出していた。
ユウは大学卒業後すぐに食品会社の品質保証部で働き始めた。製造販売している商品をランダムに抜き取って成分を分析し、表示してある数値と合致するかの判断をする部署だった。3年目になると自分のペースで仕事ができた。社内の誰かと競い合う必要がないことも平穏でよかった。
ところが、いつものように分析していると自分の測定した数値が、販売している商品の表示より随分と少ないことに気づいた。会社の主力商品の一つ特定保健用食品の食物繊維の数値だった。何度測定しても自分の数値が正しい。それは表示の数値の半分程度しかなかった。過去の資料を読み込んでいくと、商品販売当初と原材料の仕入先が違っていた。上司に相談したが、「そんなはずはない。君の測定が間違っているんだろう。もし君の言う通り食物繊維の量が少なかったとしても、すでに販売している。トクホも取得している。今更すいません。違ってました。なんて言えないよ」と聞き入れてもらえなかった。
ユウは何日も悩んだ末に父親に相談した。「波風立てなくっていいんじゃないのか。平穏に暮らせれば」と全く他人事だった。ユウは決意した。ことの詳細を消費者庁の内部告発窓口に投稿した。もちろん匿名でだ。
一ヵ月が過ぎた頃、上司に呼ばれ部署の移動を命じられた。グループ会社であり原材料仕入先のマレーシア法人だった。一旦はそれを受け入れたものの納得がいかなかった。そこで、友人・知人を頼って転職先を探した。それが現職イスラームビジネス研究所だ。この職にユウは満足していなかった。自分の実力を思う存分発揮できる職があるはずだと思っていた。それはまさに、エリザス製薬に勤務するケントの仕事だ。
そう思えば思うほど、ケントを羨ましく思った。ケントが辞めれば、代わりに自分が働ける可能性があるのかもしれない。だとしたら、ケントの失敗は俺の成功だ。ユウは鞄からまっさらなタバコの箱を取り出し封を切った。ケントに代わって自分が由美と一緒にエリザス製薬で働く姿を想像しながらタバコを咥えた。真新しいタバコの口当たりが心地よい。新しいことが始まる予感で笑顔になっていた。