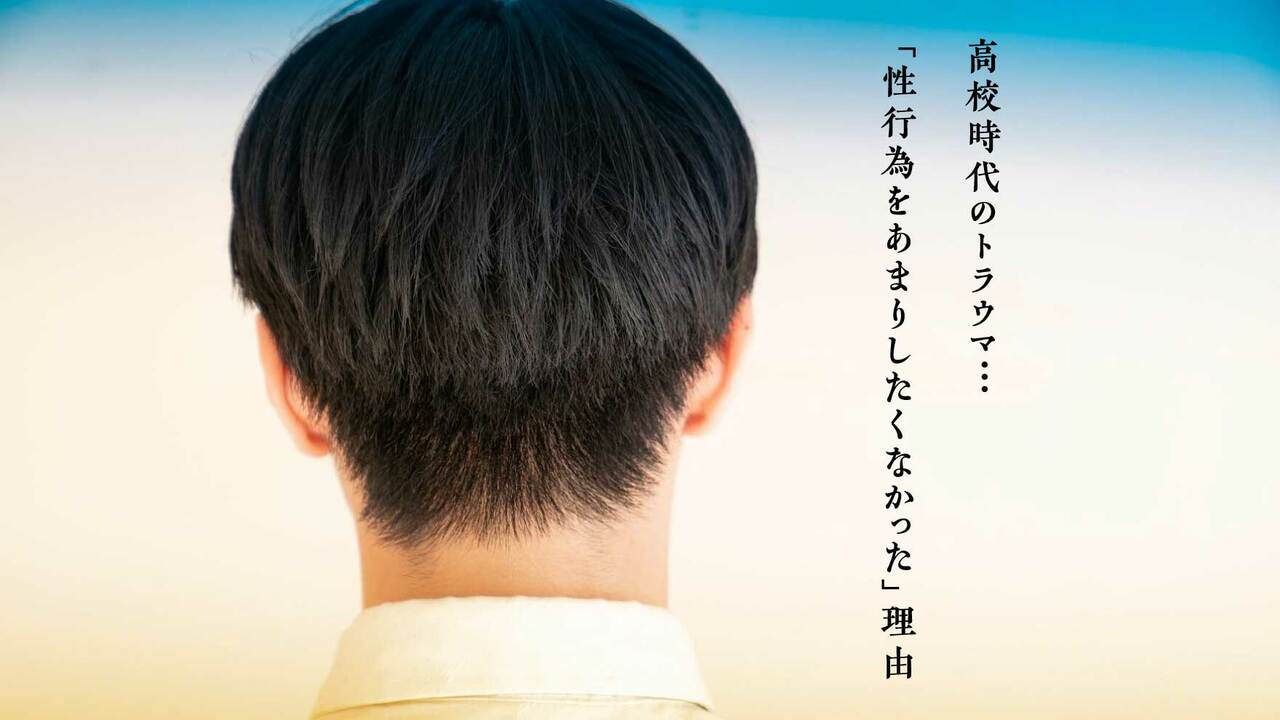第二章
大学入学後は、勉強と部活動とアルバイトで日々忙しく、また良き先輩にも恵まれ、とても充実した日々だった。
長期休みがあっても、アルバイトが忙しいからと滅多に実家には帰らなかったが、両親から苦言を呈されることもなく、お互いに一定の距離を保っていた。また、いわゆる中流家庭だったので、アルバイトをしないと経済的に厳しい状態であったことも事実だった。
大学時代、彼氏と呼べる人がいた時期はあったが、高校時代のトラウマで性行為はあまりしたくなかった。ニヤニヤ笑いながら陰茎を大きくしていた、あの時の男たち。あの光景がどうしても思い出されて、極力性行為を避けていた。
応じたとしても、気持ちいいと思ったことは一度もないし、いわゆるイクということが、私には全く理解できなかった。汗をびっしりかいて必死に腰を振っている男たちが、滑稽にさえ思えた。
だが、大学生の男子が性行為を拒否されて我慢できるわけがない。理由を話すのは嫌だったので、適当にやり過ごしていたら、大体向こうから別れを切り出された。でも正直なところ、そんなことで別れたくなるような関係性なら、要らないと思っていた。
「そんなだったから、自分で自分に鎧をまとわせて、他人に傷つけられないように生きてきたんだ。傷つきそうになったら、自分から捨ててきてしまった。そういう生き方は寂しいと思って、ある頃から人との付き合い方は変えてこられたと思うんだけど。
でも、女性として欠落した部分は確かにあるの。誰にもこの話をしたことはないけど、健太君は理解してくれるかもしれないと思ったのと、あなたが本心から気持ちを言ってくれたから、私もちゃんと話すのが礼儀だと思って。ごめんね、こんな女で。私、あなたを女性として満たしてあげられないかもしれない。そんな女が相手で、あなたはいいのかなって、それで迷っちゃってさぁ……」
途中からパラパラと雨が落ちてきて、必死で話していたから気付かなかった。私に悟られないように、健太君が静かに大粒の涙を流していた。それを見た瞬間、私の方が感極まって、思わず大声をあげて泣いてしまった。そんな私を、彼は優しく抱きしめてくれた。
「今まで、どんだけつらい思いをしてきたんですか、先生。よく一人で頑張って来ましたね」
彼のその言葉で、私は体中の水分がなくなってしまうのではないかというほど、泣いた。ようやく私が落ち着くと、自分の羽織っていたシャツを私の頭に掛け、自宅まで何も言わず手を繋いで帰ってくれた。私が眠るまで、ただ頭を撫でていてくれた。
――この人なら、大丈夫かもしれない。