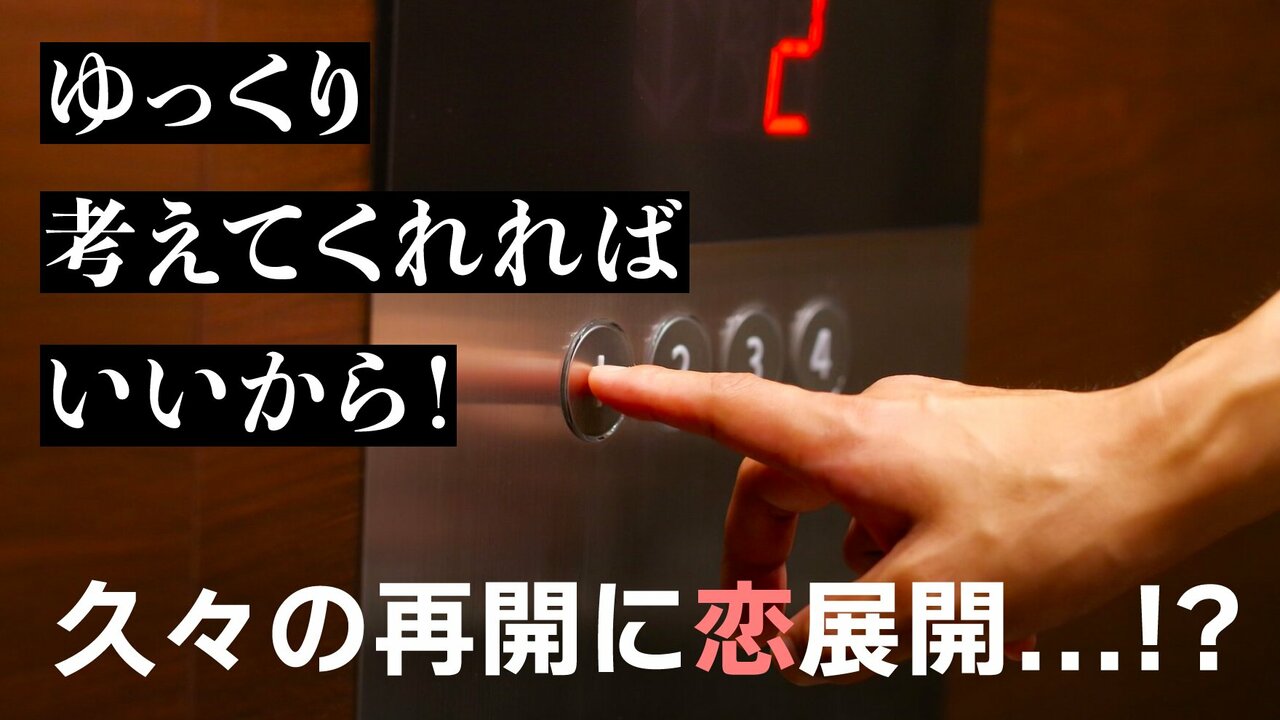第二章
本当に、色んな思い出ができた。だが、青春時代は長く続かず、二〇一二年が明けて、二月上旬。医局から急な異動を言い渡された。四月から海南台総合病院で働いてほしい、と。
当時の職場と通勤距離も変わらないし、承諾した。通常の人事は半年以上前に決定するが、今回は急に退職せざるを得なくなった先生の代わり、とのことで突然決まったのだ。思いがけず学生時代の先輩、朋子先生と働けることになり、それは純粋に楽しみだった。しかし、元村さんたちと職場が離れることが予想以上に寂しくて、異動が決まってから、ため息をつくような瞬間が増えた。
結局、異動まで日がなかったので、申し送りや残したデータ処理などのため、退職する日まで本当に忙しかった。ほとんど毎日病院へ入り浸りで、自宅へは寝に帰るだけだった。そんなだったから、元村さんとも健太君とも、職場で退職日に挨拶をしただけで、プライベートでお別れの会をすることはできなかった。時間だけが淡々と過ぎ、新たな環境での仕事が始まった。
初日から朋子先生と隣同士の診察室で外来業務を行ない、特に問題なく終わることができた。カルテ処理を行なう私のところへ朋子先生がやってきて、褒めてくれる。
「真希、今まで頑張ってきたんだね。あんたがいて、今日助かったわ」
「いやぁ、恐縮ですぅ。なんちゃって」
私は、鼻をこすりながら、おどけてみた。
「ったく。昔から変わんないね、あんたは。安心した」
彼女はそう言って、私の頭をポンポンと撫でてくれ、私は大学時代を思い出した。看護師の田野さんはそんな私たちを見て
「姉妹みたいですね」
と笑った。
朋子先生は私の五歳年上で、学年も五つ上。私が入学後すぐ入部した硬式テニス部の女子キャプテンだった。テニスの実力もさることながら、人柄もとても素敵で、男女問わず部員から信頼を得ている人だった。嫌なものは嫌、いいことはいい。誰にも飾らないサバサバした性格の彼女が、私もすぐに大好きになった。
仲良くなったきっかけは覚えていないけれど、二年生から五年生までの先輩たちを飛び越えて、彼女は私のことをとても可愛がってくれた。六年生は国家試験のための勉強が本格的に忙しくなり、一緒に活動した期間は短かったが、その後も何かと気にかけてくれ、ずっと付き合いを続けることができていた。私にとっては、とても貴重な存在なのだった。そんな彼女に認めてもらえることは、年齢を重ねても、やはり嬉しい。
新しい職場に早く慣れたいと思っていたので、特に仕事の用がなくても病棟や外来に顔を出し、スタッフとコミュニケーションをとるようにしていた。自動的に帰宅時間は遅くなるのだが、それは必要なことであると思っていたから、全く苦ではなかった。