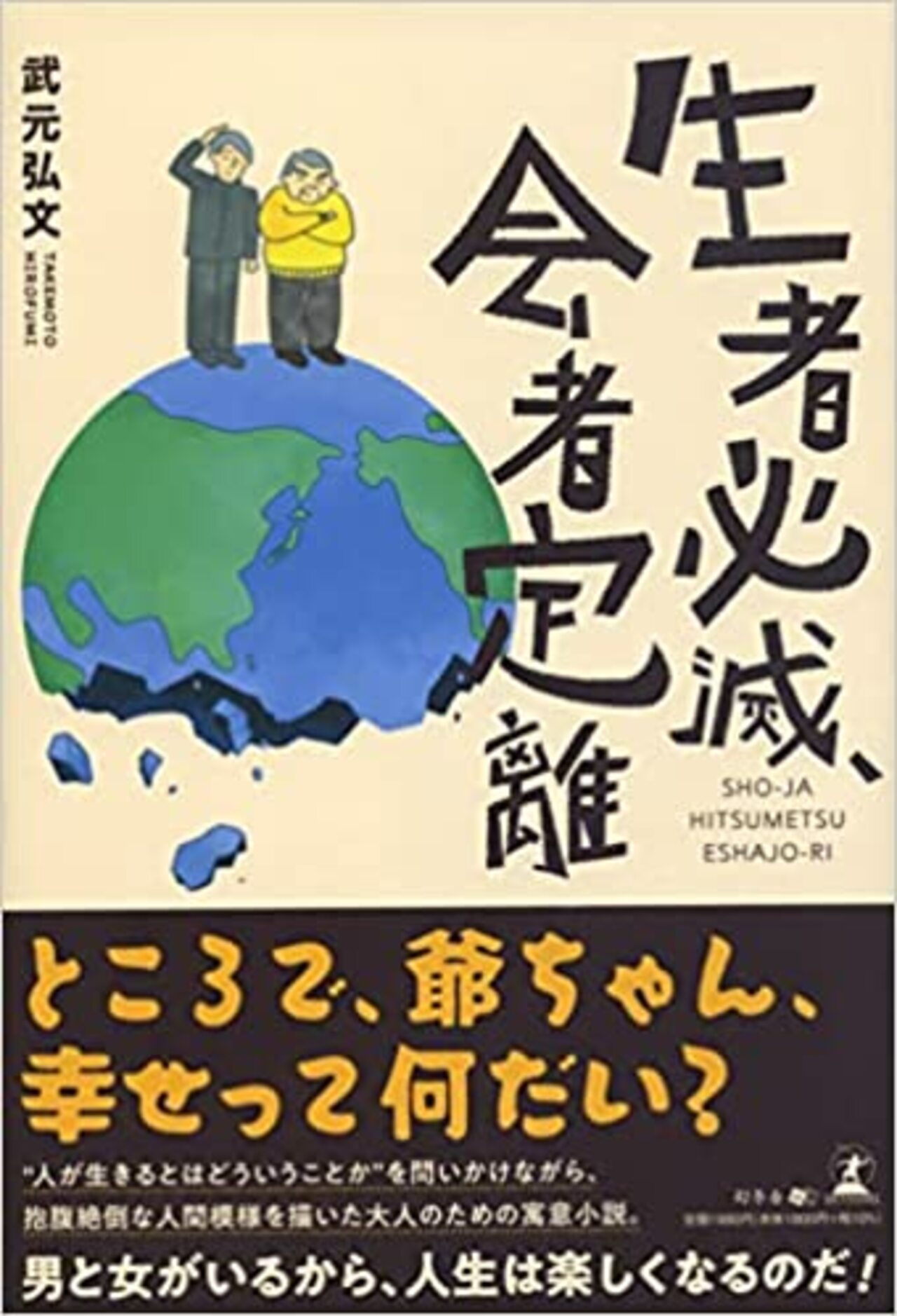お鶴は母、千里から吹き込まれた奥の手『龍神様をいつもの雄に戻す妙薬は、そなたの生まれたままの姿じゃ』を、思い出す。お鶴は文左衛門の腕の中からするりと抜け出し、次の間の赤い夜具の上に向こうを向いて立つ。繻子の帯がしゅっと、音を立てたかと思うと、足下に落ちていく。ついで、赤い蹴出しがさっと落ち、最後に湯文字がはらりと落ちる。お鶴はその一つ一つを丁寧にたたみ、乱れ籠に収める。
そしてもう一度、向こうを向いたまま立ち上がり、着物を襦袢もろとも腰のところまでゆっくりと下ろす。
新雪のようにまぶしい背中、着物の浅葱色、掛け布団の紅色、まさに歌麿の浮世絵だ。最後に、一切がはらりと落ちる。数え切れないほどの裸体を見てきた文左衛門だが、浮世絵のように色っぽい裸体は、お鶴をおいて他にない。豊かな胸、蜂のようにくびれたウエスト、手鞠のようにこんもりと盛り上がった左右のヒップ。その色っぽさに文左衛門の股間が鎌首をもたげ始める。
それを見透かしたかのように文左衛門の方に向き直り、ポーズをとるお鶴。右手を頭の後ろに添え、左手で前を隠し、斜め横を向くと豊かな乳房の先にピンクの桜ん坊がつんと天を仰ぐ。突き出された尻は雄を待つ雌の姿そのもの。
雄の本能を掻き立てられた文左衛門。すっくと立ち上がると、お鶴を抱きしめ、髪の生え際から項にかけて熱い吐息を吹きかける。お鶴の口から「はぁーっ」と、桃色の吐息が漏れる。全身から力が抜け、文左衛門の腕の中に崩れ落ちる。横たえられても恥ずかしそうに背中を向けてしまうお鶴。文左衛門は高価な骨董品を磨くかのように、優しく背中から項へと舌を這わせる。
耳たぶを軽く噛まれてお鶴の肩がぴくりと震える。後ろから抱きかかえ両手で左右の乳房を揉みしだくと、乳首が固くなり、切ない吐息が激しさを増す。お鶴を仰向けにすると、その横に正座して
「お鶴、そなたは儂の宝物じゃ」
右手で髪を撫で、乳首を弾き、左手で内股からつま先まで撫で回す。それは、あたかもお鶴の体を琴に見立て、筝曲『春の海』を奏でているかのように優雅な愛撫である。右手で乳房を揉み続け、左手を土手の若草の上に滑らせる。玉門の大扉を開き、中指と薬指で小さな花びらを挟み、中の花芯を揉みもみする。お鶴はもうメロメロ。蜜壺をくじるまでもなく尊き辺りは愛の雫でしとどに濡れ渡る。禿として客と花魁の数々の濡れ場を見てきたお鶴。百戦錬磨の文左衛門に女の急所を次々に攻められ、もうどうにも我慢できない。
まっさらな処女でありながら、男を喜ばせる術を花魁から学んでいるお鶴。文左衛門の胸の内を察してそのいきり立った一物を握りしめ、大きく股を開き、膝を立て「旦那様、旦那様」と、甘える。母の禁を思い出し、瞼を閉じ、静かにその時を待つお鶴。