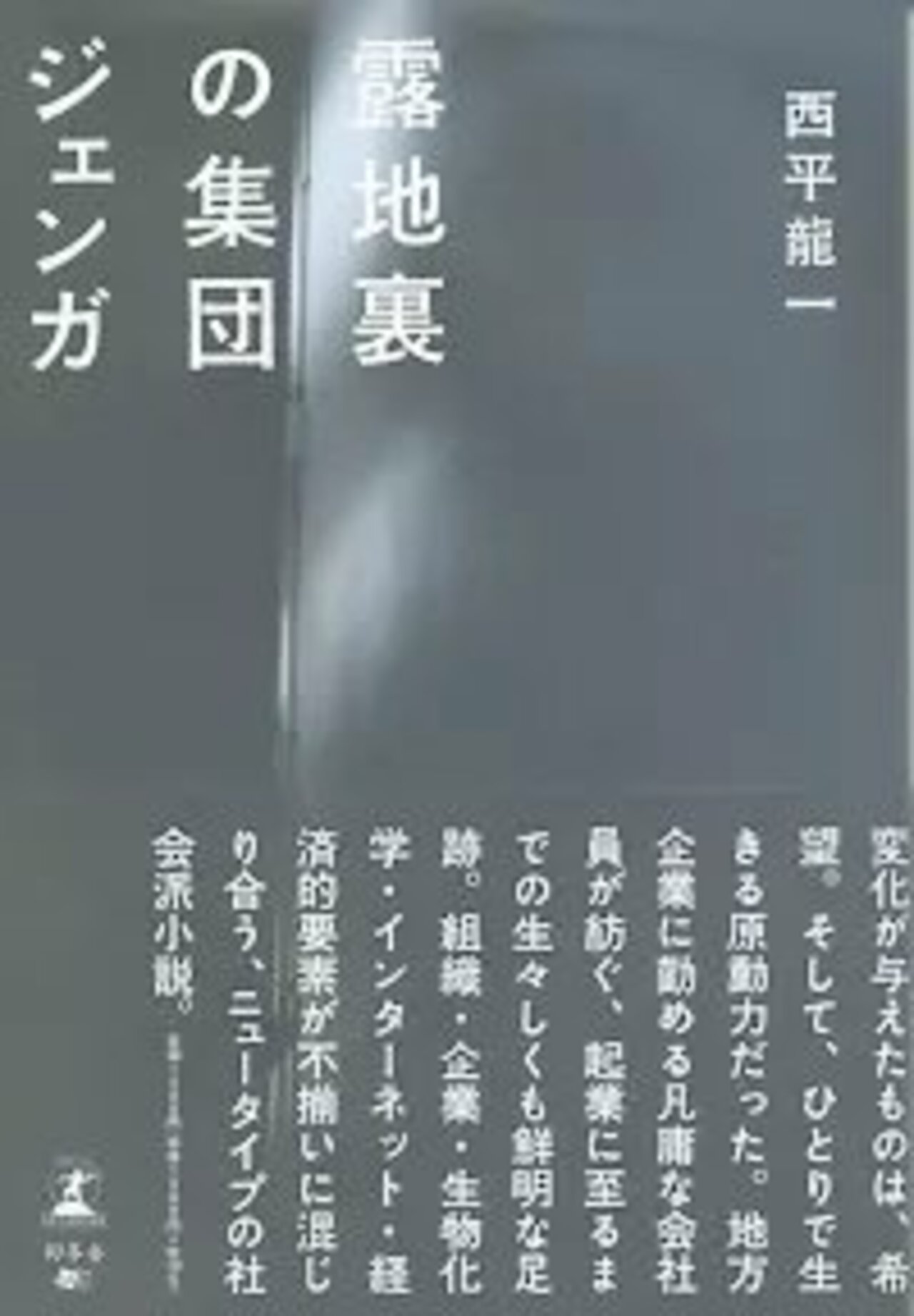森が入社して間もなくのことなので、八年も前のことだ。森は僕の六歳上で、そして部下として在籍していた。
「遅いじゃないですか。もうみんな揃っていますよ」
ある休日に、森は自宅に女を二人招待していて、僕はそれに誘われた。森の顔はすでに紅くなっていて、せせら笑いながら上下に発色した頬を動かしている。開いた口と毛穴から漂う酒の臭いが、僕の鼻にぬめるように触っていた。
二人の女は扉の奥の部屋にいた。パイル地のスリッパを履かされ部屋に入ると、そこは整然としていた。ツルッとしたテーブルに、食い減ったオードブルと、缶のビールと酎ハイ。そして紙皿が無造作に置かれている。揚げた脂の残骸が、テーブルの艶で目立って見えた。
女は一人、酷く酔っ払っているようで、流れを遮る僕に対して、嫌悪の表情が見て取れた。パイル地だけで隔てられている足の裏は、フローリングの床に接地していて冷たく感じる。浮かない顔の僕を、さあさあさあ。と、森は得意な様子で座るように促した。
「びっくりしたんじゃないですか。結構辺鄙なところでね。さあどうぞ、どうぞ」
鼻にかかったような声は、酒を飲んでも変わらないようだ。
森の渡すグラスはとても冷えていて、慣れた手つきで缶のビールを注いでいる。森はそれが例え缶であったり、ただの交遊の場であったりしても、両手を添えるとか、銘柄のラベルを上向きにするとか、姿勢は腰と両膝を落とすとか、接待の所作をとても心得ていた。僕はそれに気遣い、田舎の育ちなのでこういう街は好きな気がしますよ。と、丁重に言った。森の自宅は郊外にある高層のマンションだ。
「そう言ってもらえると嬉しいのですよ。なにせ快速電車は止まらないですしね。ダイヤも少ないもんですから。不便だ不便だ。なんていう人も、一定数はいるわけです」
まるで多くの人間を、頻繁に招く人間の口振りで話している。しかしね。と、上目遣いで森は続けた。
「近いうちにですよ。都市開発で地価も上がりますから」
「なぜ。そんなことがわかるのですか?」
「私はね。とあるスーパーゼネコンの役員と、古くから知り合いでしてね。あっ、わかりますか? スーパーというのは、大手という意味なのですよ」
買い物にもっとも重要なことは、情報ですからね。しかしその情報とは人脈次第です。と、続けた。酒で湿った下唇を、上にある歯で巻き込むように噛んでいる。そして物欲しそうに眼を回して、じっと僕を離さなかった。
「なるほど。私はこういうことには、酷く無頓着でしてね」
森は入社と同時に、私は求人広告を企業に販売する営業会社出身で、在籍時はトップセールスだったのです。そう細やかに周りに流布していた。