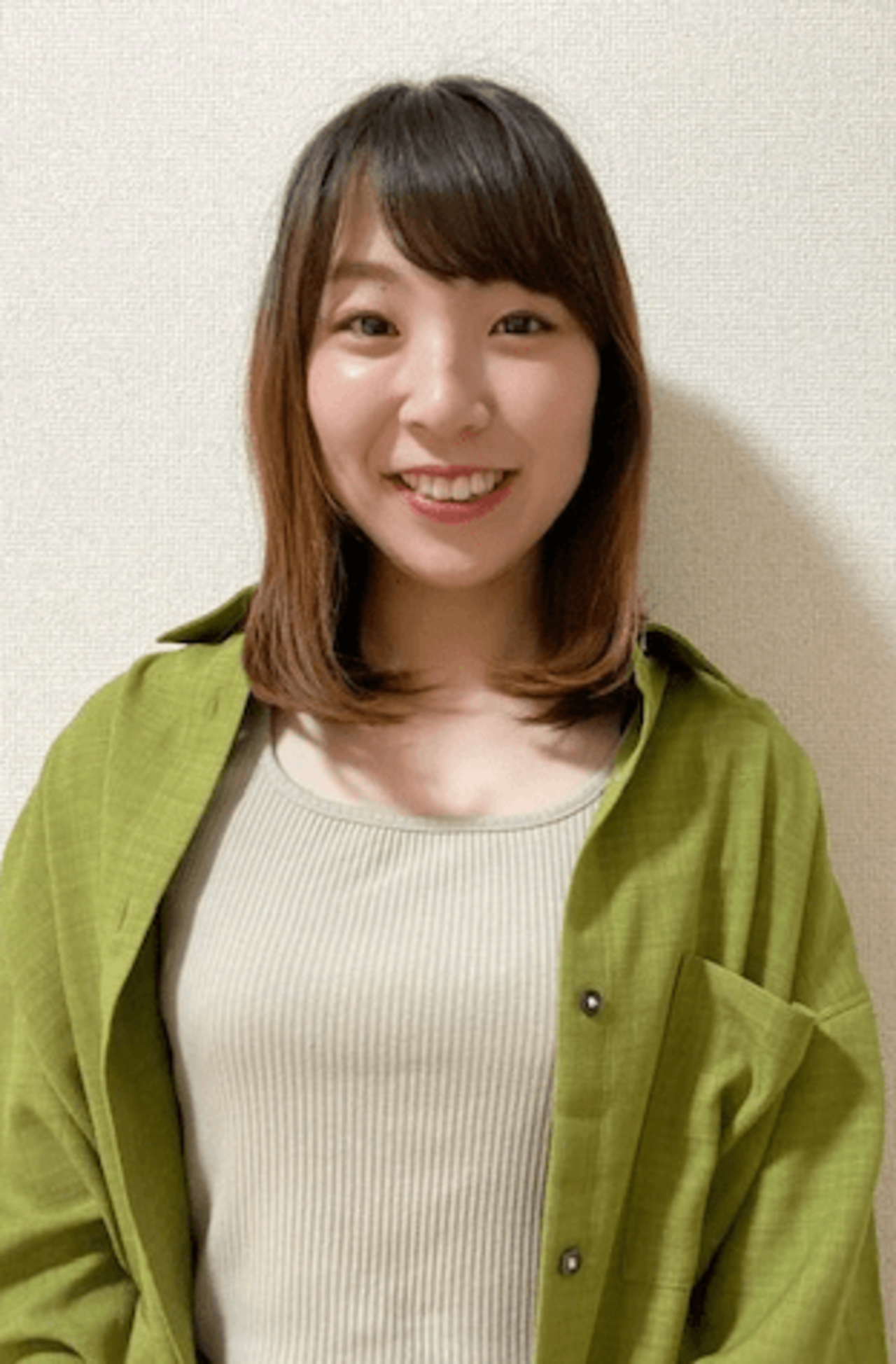彼は夕方四時から五時にあらわれた。いつも一人だった。
その時間は小学生にとってはゴールデンタイムだろう。土手の下の河川敷にも小学生が何人かキャッチボールをして遊んでいる。
ちらっと彼の方を見ると眩しそうな目をしていた。夕日が反射して川の水面がチカチカしているせいなのか、それとも河川敷の少年たちを羨んでいて本当はあっち側に行きたいのか分からなかったが、二人で土手に座っていると何かしたほうがいいかなという気になった。私は立ち上がって、
「一緒にまぜてもらう?」
と聞いたが彼は首を横に振り、空に、
「と、な、り」
とかいた。
“隣にいてほしい”
きっとそういうことだろう。
私は、
「そっか」
と言って隣に座りなおした。
季節は巡り、冬になった。その年の冬は一段と寒く、土手にも冷たい風が吹き荒れていた。
さすがにこんなに寒い時に土手には来ていないだろうと、自分の部屋の窓から雲を眺める日が続いた。彼のことは気になりながらも、土手に行くのは遠のいていた。
寒かった冬が終わり、ようやく私の好きな土手が戻ってきた頃には彼はもういなかった。夕方四時を過ぎ、五時、六時になっても、土手が黄色と白でにぎやかになっても、彼は来なかった。別に会う約束をしていたわけではなかったし、来ると信じこんでいた私の方が変だったのかもしれない。
あの時と同じように階段の半分ぐらいのところに座って、行き交う小学生たちの顔を眺めながら深いため息が出た。心の中にぽっかりと穴が開いていた。
結局大学を卒業するまで、あの日から一度も彼には会えなかった。
「となり」とかいた彼の隣には今だれがいるのだろう。もしかしたらもうしゃべれるようになっているのかもしれない。彼のことを久しぶりに思い出し、そんなことをぼんやり考えていると、
「おかあさーん!」
と遠くで呼ばれてハッと現実に戻った。