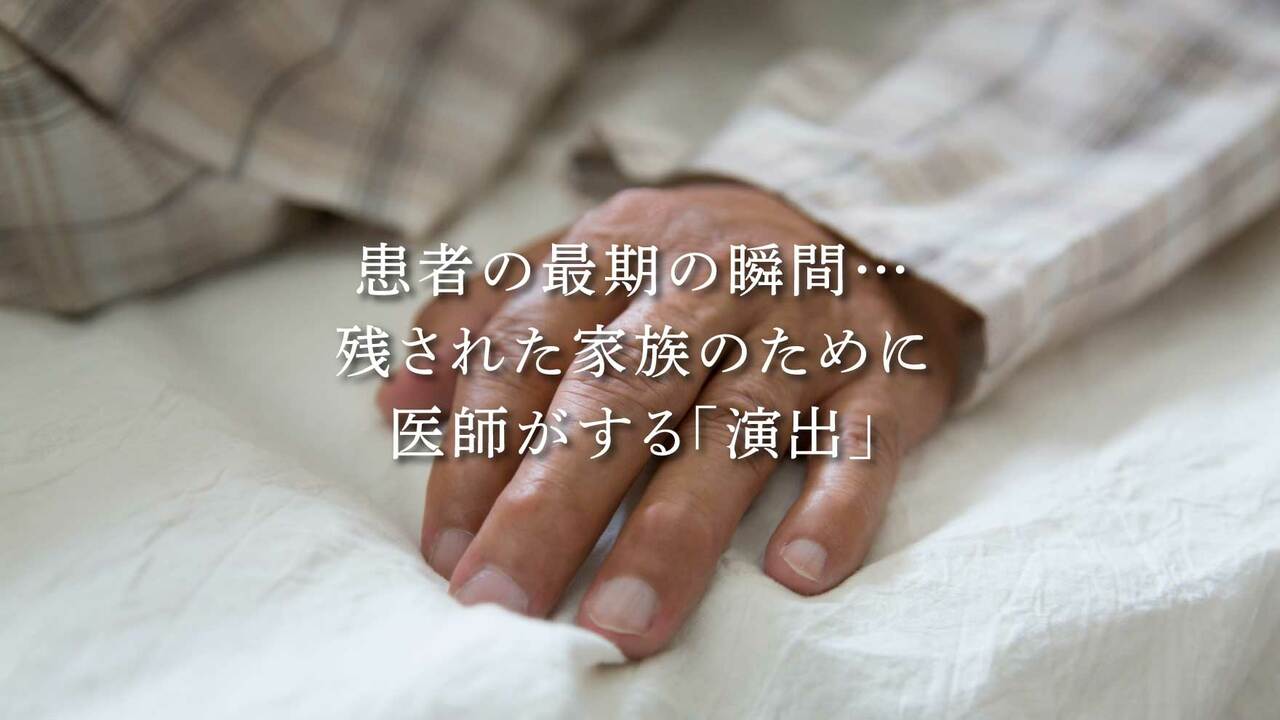【前回の記事を読む】「先生、良くなりますか?」死が間近に迫った患者と向き合うということ
Passengers ――過ぎ去りし人たちへのレクイエム
「よしよし」
二日前の夜、その日3度目の回診のため病室のドアをノックして開けると、東京に嫁いでいる娘がいた。彼女は身重だった。彼は時折襲って来る激痛に堪えつつ、苦しい呼吸の中で娘と話していた。
彼の首にできた腫瘍は気管、食道を圧迫し神経をも侵していた。彼は自分の中の苦痛と不安を振り払うように娘を見つめ、この世で最後になるかもしれない娘との時間をいとおしんでいるかのようだった。娘は途切れ途切れのかすれた小さな声しか出せない父親の口に耳をつけるようにして寄り添っていた。
かすかに「幸せになるんだよ」という言葉が聞こえ、娘が頷いた。そこには他の誰をも寄せ付けない空気があった。
彼の脳裏には娘が生まれた時、幼稚園の頃マンションの廊下から「お父さん、行ってらっしゃい」と叫んでいた姿、帰宅すると飛びついてきて抱き上げた感触、そして嫁いで行った日のまぶしいばかりに輝いていた姿などが次々に浮かび、一つ一つの記憶を大事に、二度と開けることのない引き出しの中にしまいこんでいったのだろう。
そして初孫が誕生する喜びと、おそらくその子供を自らは抱きしめることができない悔しさを感じ、いま少しの時間の猶予が与えられる奇跡を祈っていたのだろうか。
翌日、彼の意識が混濁し始めると、彼は宙をつかむような動作、何かを抱きかかえるような動作を繰り返し、かすかに「よしよし」という声が聞こえた。身重の娘が訪れていたことを知っていた年輩の看護師が言った。
「お孫さんを抱っこしておられるのでしょうね」
娘は父に訪れる死の影が信じられずに、自分をずっと暖かく包んでくれた大きな存在が消え去ろうとすることが実感できずに、残された時間にすがるように、父の顔を脳裏に刻み込むように、見つめていた。
私は面会時間を大幅に過ぎて部屋にいる娘に声をかけるように看護師から言われ、部屋の前に立った。だが垣間見える父娘の姿に、自分とまだ幼い娘とを重ねて何も言えずにただ彼らの姿を見ていた。暗い部屋で二人の周りだけがぼんやりと明るく、空気も時間も止まっているかのようだった。