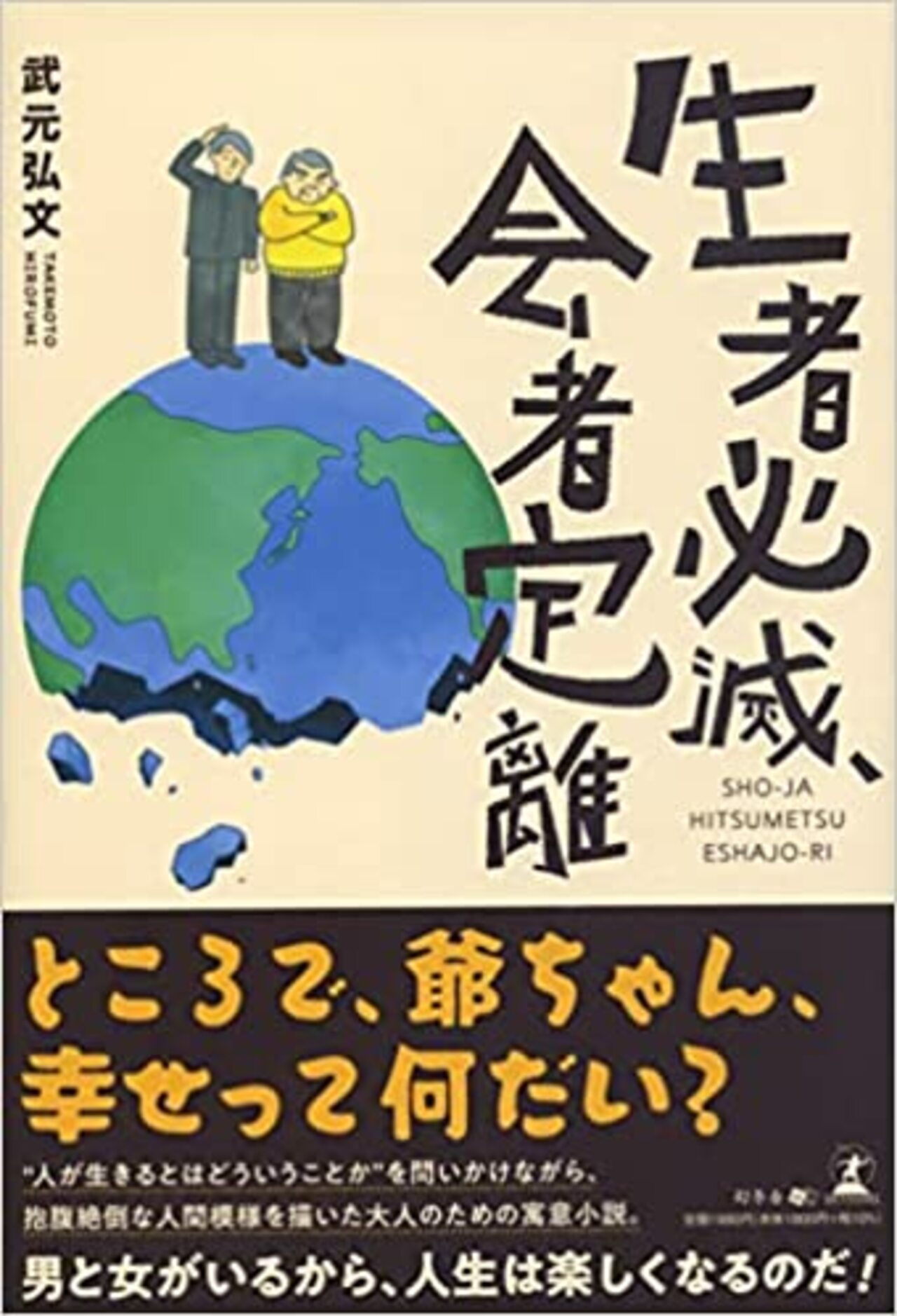プロローグ 縁は異なもの味なもの
「旦那はんも、物好きなお方やねえ」
呆れながらも、大金を懐に、笑みを噛み殺し、にんまりとする女将。
時に、文左衛門四十一歳、鶴女十六歳。鶴女の父、狸小路公麿は娘を文左衛門に身請けしてもらったお陰で、銀行から借りていた多額の借金を返済することができた。そのうえ、文左衛門から驚くほどの支度金を渡され、鶴女の両親は文左衛門が只者でないと知る。
鶴女が親孝行をしたお陰で父、公麿の役所での地位も安泰となる。文左衛門と公麿は、同い年ということもあってか馬が合い、以降、持ちつ持たれつの間柄となる。身請けされた鶴女、禿から半玉となり、昼間はお師匠さんに付いて稽古に励み、夜はお座敷と歌舞音曲の世界で芸を磨く。
夜になると、芦屋の本宅から文左衛門が通ってくる。金に飽かせて女を囲うような男だ。鶴女はおもちゃにされているのであろうと、気を揉む母、千里。予想されたことの成り行きとは申せ、娘がいたぶられているのではないかと思うと、心配せずにはいられないのが親心。
「のう、お鶴。旦那様、可愛がってくださりますかえ?」
「お布団、別々ですねん」
「じれったいのー、旦那様のお渡りが、あるじゃろうが」
「まだ、あらへん」
「毎夜、どない、しておるのや」
「父様から教わった詩歌管弦のお話、母様から習った山水画のお話など、させてもろうて、おりますねん」
鶴女が大切にされているのを知って、ほっとする千里。まだ青梅のように硬い体のお鶴と同衾せずとも、致し方ないことと納得する公麿。こうして、指一本触れぬ不思議な関係が二年あまり続く。女の徴はとうに萌している。そこはかとない色気がお鶴の胸のあたりに漂う。
家族と一緒ではその気になりにくかろうと、離れ家を建てるなど、両親は何かと気を遣う。野山の草木が芽吹き、万物が性の営みを活発にする春の宵。
「のう、お鶴。旦那様のお渡りは如何かえ?」
「旦那様は龍神様の化身なんやろか」
「それはどういうことなのかえ?」
「祇園に遊びに来る男はんとは別世界の人なんや」