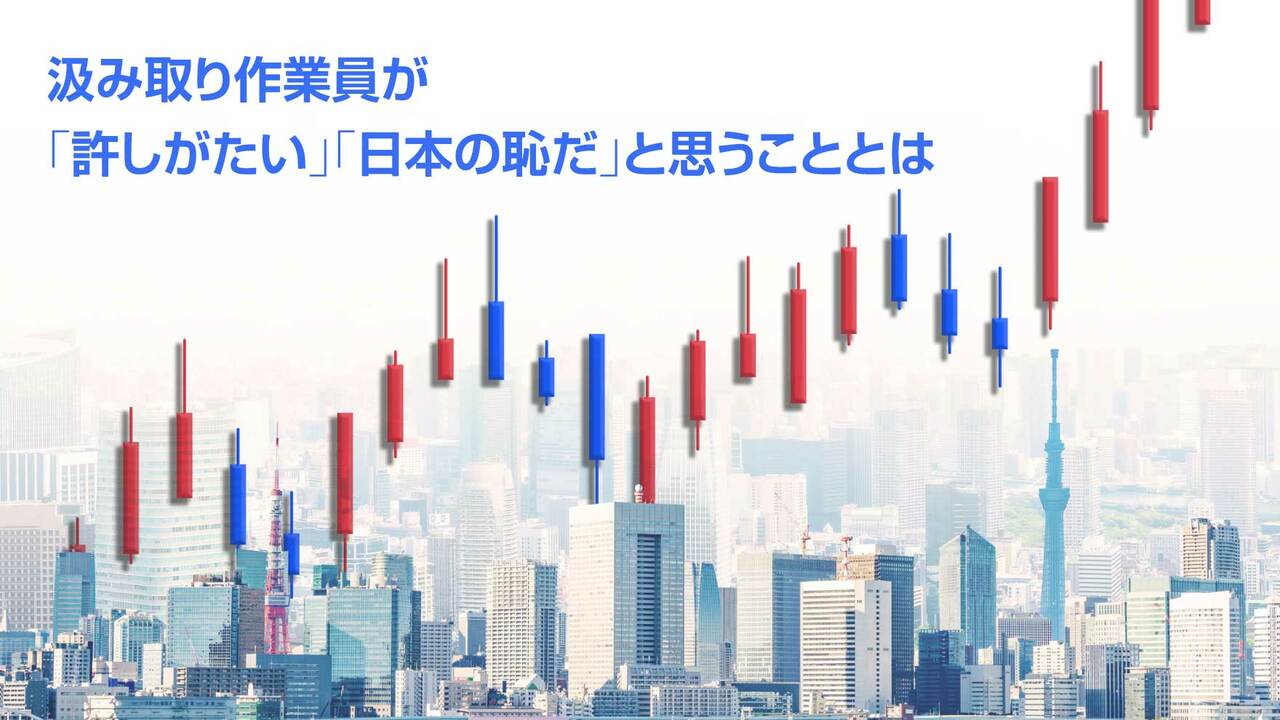そのなかでも芯から末吉を信頼し尊敬し、頼りにしていたのが峰子だった。末吉はそんな峰子といるときが、裏表を持った人の心の醜さに幻滅を感じイライラし、心を潰されるような苦しみから解き放たれる大事な時間だった。峰子の亡くなった父も埼玉県で汲み取り屋をしていた。
峰子は「汲み取り屋の子」と呼ばれ、いじめられて育った。しかし、峰子は人のいやがる仕事を、家族のために、黙々とやり切って死んでいった優しい父親が大好きだった。末吉は行きつけの居酒屋で、故郷である滋賀県の琵琶湖湖畔の蔵元、上原酒造で造られている山廃仕込・天秤搾り・木桶仕込みの銘酒「不老泉」をチビチビ飲みながら、
「人間は自身を認め、必要とする人がいて、初めて自分の存在価値を発見し安堵する。そして、それによって本当の幸福を実感できる。それは物質的、経済的な、言わば利害関係で求め合うものとはまったく違う。それは、ある特定の者同士が、本然的に惹かれ合う世界だ。また、その関係が成就することで、今度はまったくの他人をも大事にしたいという思いが、湧いてくるものなのだ。そして、その心のままに慈善行為をするときに、俺はまた違う喜びと快楽を味わうことができるのだ」
などと考えていた。
峰子と同じ時間と空間を共有することが、末吉にとって本然的な救いだった。それは微笑ましい家族との団らんとは、まったく異質のものだった。だから、それを知っている妻のフミは、末吉と峰子の関係に嫉妬を覚え悩み続けながらも、末吉がそれで少しの間だけでも救われているのだと思うと、末吉が通いつめる赤線も、浮気相手で貢ぎ先である峰子をもなんとなく許してしまうのだった。
そのことは、黒光りする金庫の札束が減ることがないことにも表れていた。そのうえおかしなことに、時には感謝の感情まで湧いてくるから、フミ自身もその感情に戸惑うことがあった。
「自分のプライドが深く傷つけられ、愛する末吉への思いが裏切られても、末吉の苦しみが少しでも癒され、一時でも安らぎを感じることができるのであれば、それは自分にとっての幸せでもある」
フミは、ついそんな風に考えてしまう。フミの末吉への愛情は、「子どもの幸せのためなら、自己犠牲をも辞さない」という、母性愛に似たものだったのかもしれない。