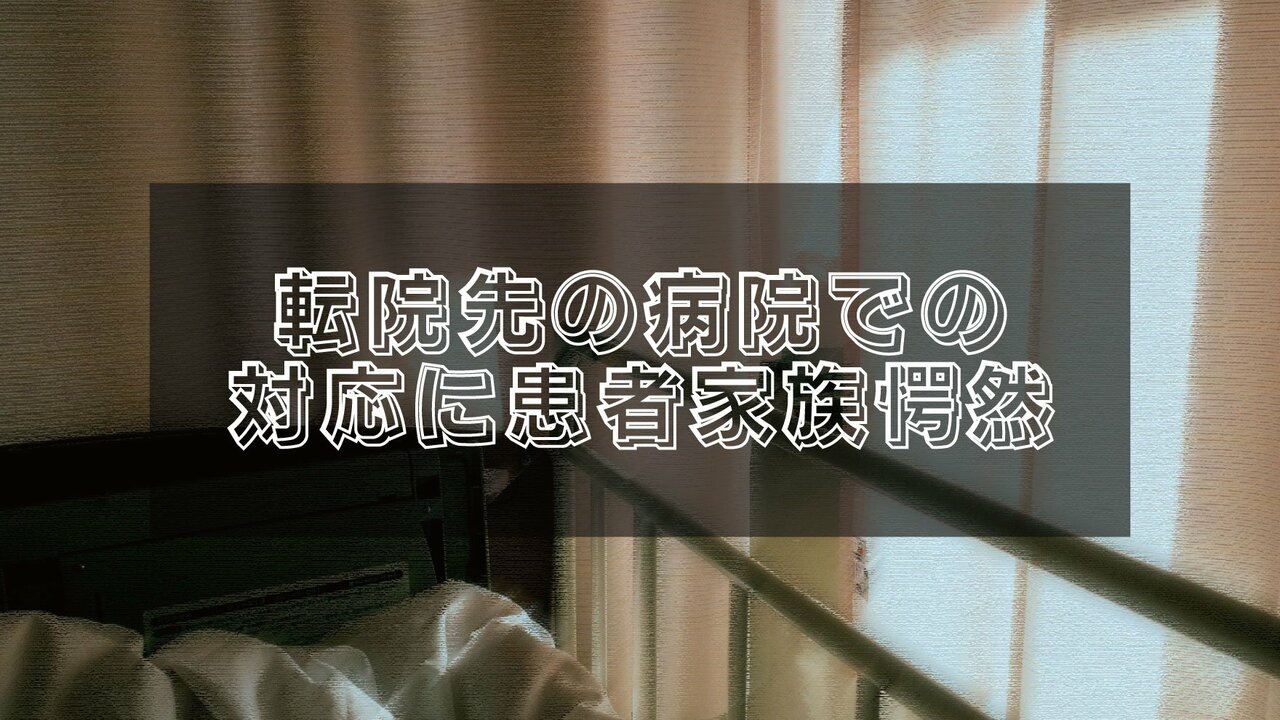ALS 五
生命維持装置を付けてから二カ月後に、京子はA病院より、家からもっと遠く離れた山の上にある、脳神経内科の専門病院に転院した。一カ月間、新入院患者の観察期間として、個室で過ごすことになった。これによって、病気の進行度を把握して、相部屋を決めるのだろう。個室は少し日当たりが悪かったが、誰に気兼ねすることもなく、私は毎日京子の介助に通った。
カニューレを通して、人工呼吸器のホースに接続された喉の刺激は大方、治まってきた。ただ、ずっと上を向いているために鼻水が喉に落ちてくるのと、ときに胃瘻からのミルクが逆流するのか、激しくむせる。その度に、身体に掛けている毛布が上下して、気が気ではなかった。
生命維持装置から出ている金属の腕木によって、空気を送る蛇腹のホースはたるみを空中で保ち、喉元のカニューレに繋がっている。このたるみの余裕がホースの二次的な振動を吸収する。これがなかったなら、身体が揺れた瞬間に喉から血が噴き出るのではないかと思った。
転院してから二週間が経過したある日、私が病室に入ると、京子があわただしく口パクをしてきた。何かいいことを思いついたときのように、京子の身体から活力が感じられ、はずんで見えた。その活力はメモ帳を見て私に実施してほしいという、京子の意思表示だった。
「右脚の膝の下に折り畳んで入れているバスタオルは、汗を吸っているので、お風呂と同じ時に取り換えてほしい。左脚に入れているそば殻枕はやめにして、これもバスタオルに替えてほしい。看護師さんは、そば殻の枕の厚さや形を手で押して、足形に調整する時間がないのでバスタオルに替えたい」
ベッドのかたわらにあるメモ帳にそう書かれていた。京子の妹が午前中に来ていたことも、妻が元気をもらった源かと思えたが、それだけではなかった。