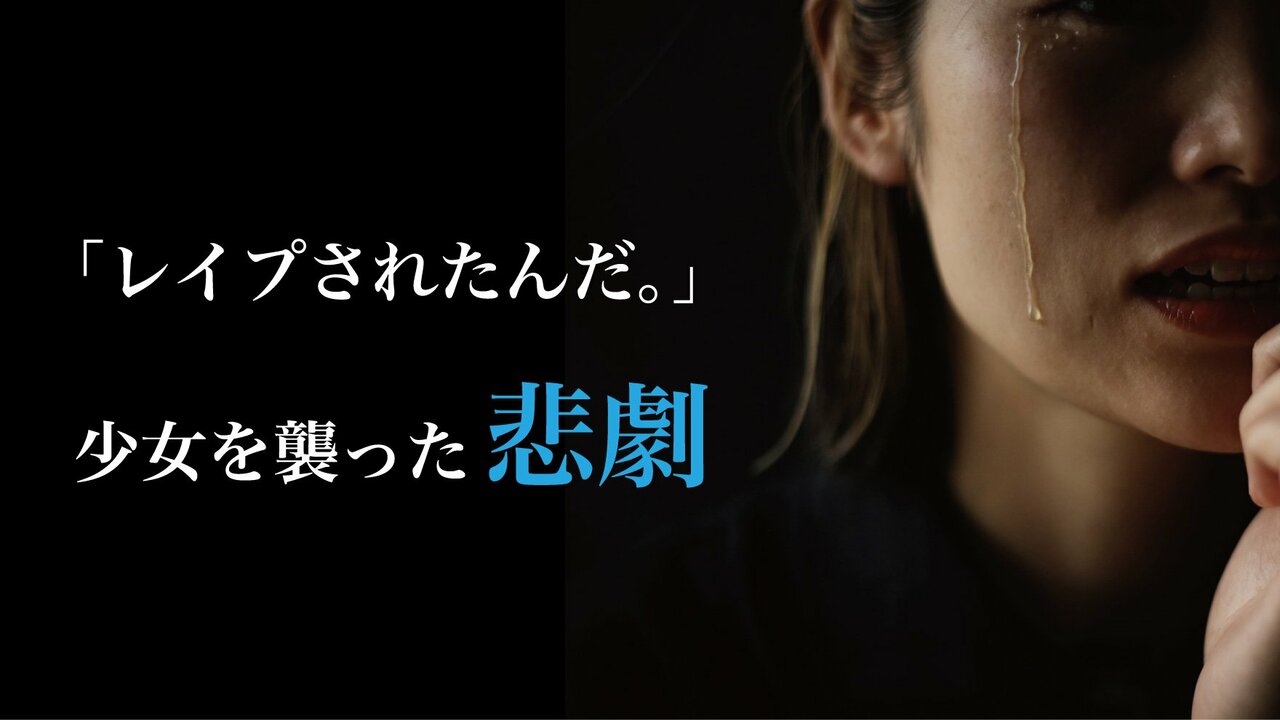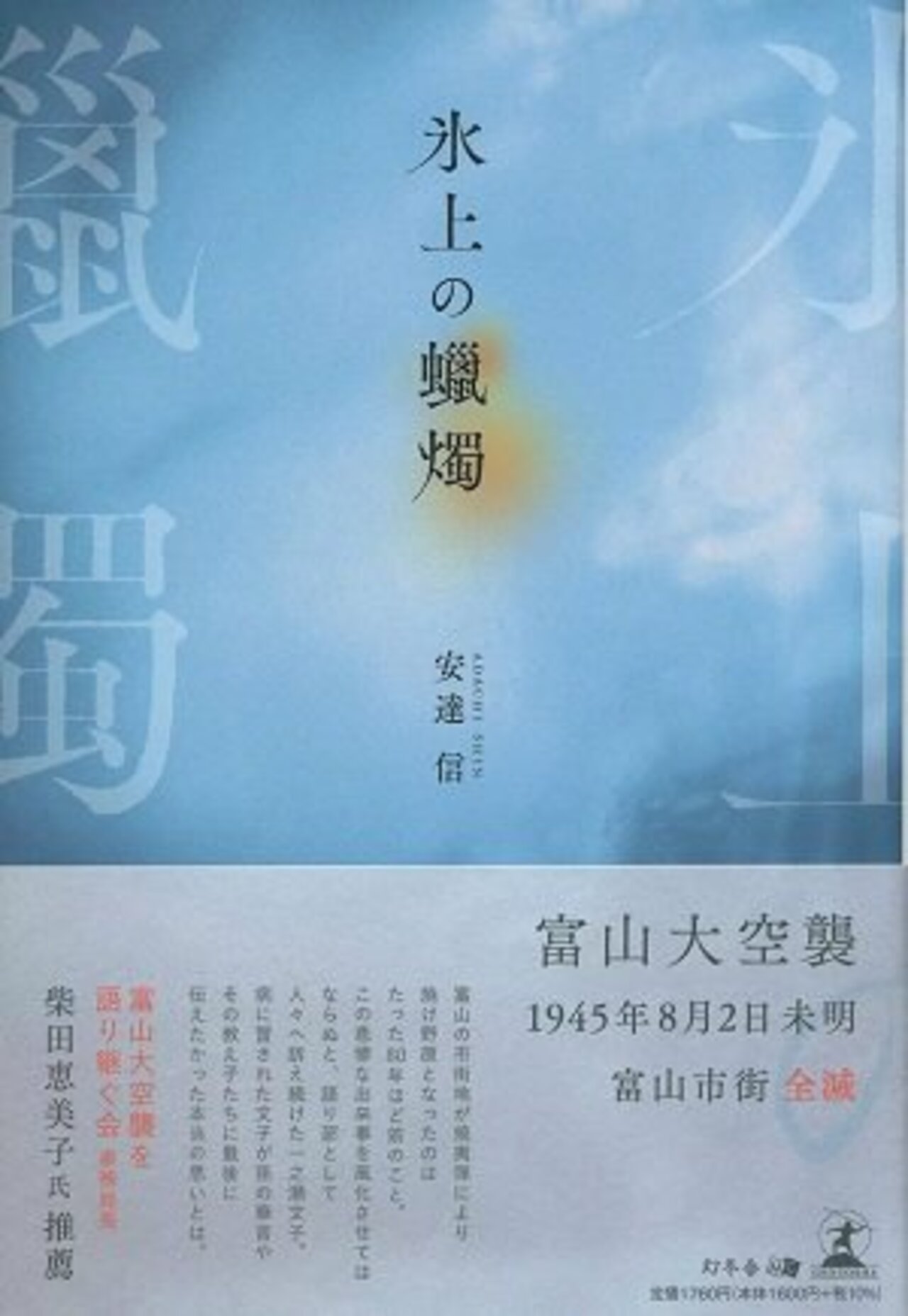【前回の記事を読む】【小説】「先生のお姿を拝見したのはそれが最後でした」
一闡提の輩
瑠衣の目は、泪で潤んでいた。坂東は瑠衣が涙ながらに話す姿を羨ましそうに見つめ、神妙な顔つきで言った。
「井上先生と僕とでは、器が違いすぎる。俺なんて、特任教授とは名ばかりで小遣いを稼がないと気位の高い嫁さんには頭が上がらないし、音大のウインドオケの指揮者といってもたかが知れてる。井上先生の後釜として、島田さんは僕を指名してきたんだろうけど無謀だね。俺は『雇われマダム』みたいなもんで、日給月給の世界で生きてるだろう。いろんな学校に教えにいっちゃ日銭を稼いでいるんだから。君は口が堅いから言うけど君の高校の謝礼は破格で、誰が賄っているか知らんが、島田さんは随分苦労したはずだ。挙句の果て君がキャプテンのとき銅賞じゃ、これから先、声かからないな。これで、大スポンサー失ったか」
坂東は自虐的なジェスチャーをした。
「音楽の世界にもいろんな人がいるけど、楽器やっている奴は大概指揮者になりたがるもんなんだ。なんといったって大勢の演奏者を束ねて自分の世界を創造できるのは、一種のエクスタシーみたいなもんなんだ。俺はその魅力を味わいたくて努力したが、そんな能力がないことは自分で一番よくわかっているから余計に始末が悪いのさ……」
こんなに捨て鉢になる坂東を瑠衣は初めて見た。
「瑠衣ちゃん。きょうは昼間からワイン飲んだせいか、酔っぱらったみたい。僕を慰めてくれない? 瑠衣ちゃん、頼むよ。今日は寂しくて、寂しくてしょうがないんだ。瑠衣ちゃん、カレシいる?」
ねだるような素振りで言い寄ってきた。
「私には、つき合っている人はいません」
とこたえたが、瑠衣は福井先輩が好きだった。しかし、彼はなかなか振り向いてくれなかった。
「だったら瑠衣ちゃん、こっちに来なよ。僕の肩にもたれかかって、ひとときのアバンチュールを楽しまないかい? 瑠衣ちゃん、奥手。バージンじゃないよね?」と坂東は突拍子もない言葉を発してきた。
瑠衣は返事に詰まり、赤い顔のままうつむいて聞き流した。