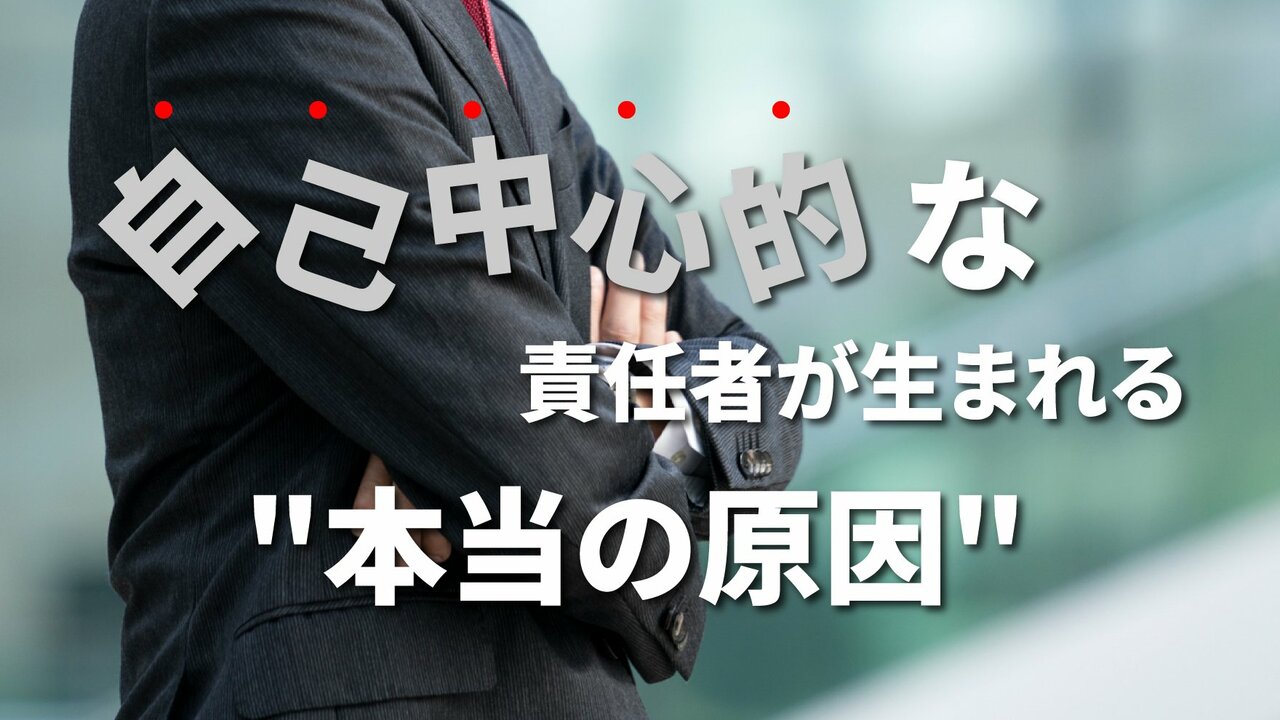それが去年、盆休み中の思わぬ腰砕けに驚かされ、唐突だと受け止めた。その場で会社を解散すると決めた。
八十までとここ数年はぼんやり思ったりしたこともあったから、たった一年が悔しかったが、やっとという安堵めいたものもあった。
当時、工場では腰をかばう跛行を見て、社員は先行きを不安がった。会社の方針があり地獄だとしても、そうだからこそ親父の、社長の不虞は心配になる。自分から親父というのは面はゆいが、初めて就職した町工場では、個性溢れる工員が十数人、本人がいない場所で一様に“おやっさん”“親父”と会話に乗せていた。
物珍しくおかしかった。そんな工員はそもそも小心で概ね投げ遣りなのだ。
仕事には、忙しいのと暇なのと『それがどうした』となる。おまけに煽てれば調子に乗るし、窘めるものなら『そんなら自分でやってみろ』とくる。それが諸刃の剣で、そのまま経営に響く。不運目覚ましい偶然がそれに覆い被さった。突然仕事が途切れたのだ。
やめると言っても、賃貸の工場スペースは解約を申し込んだあと、六ヶ月の賃料を払わなければならない。その六ヶ月が執行猶予か実刑かは微妙な情勢だった。実刑なら即、倒産。令和2年2月29日閏の尽、三十年続けた工場をなんとかかんとか畳めた。
令和初頭に、閏は吉か凶かと可否を悩むのは悪い癖。しかし、癖だらけだからこそ人間をやってこられた。