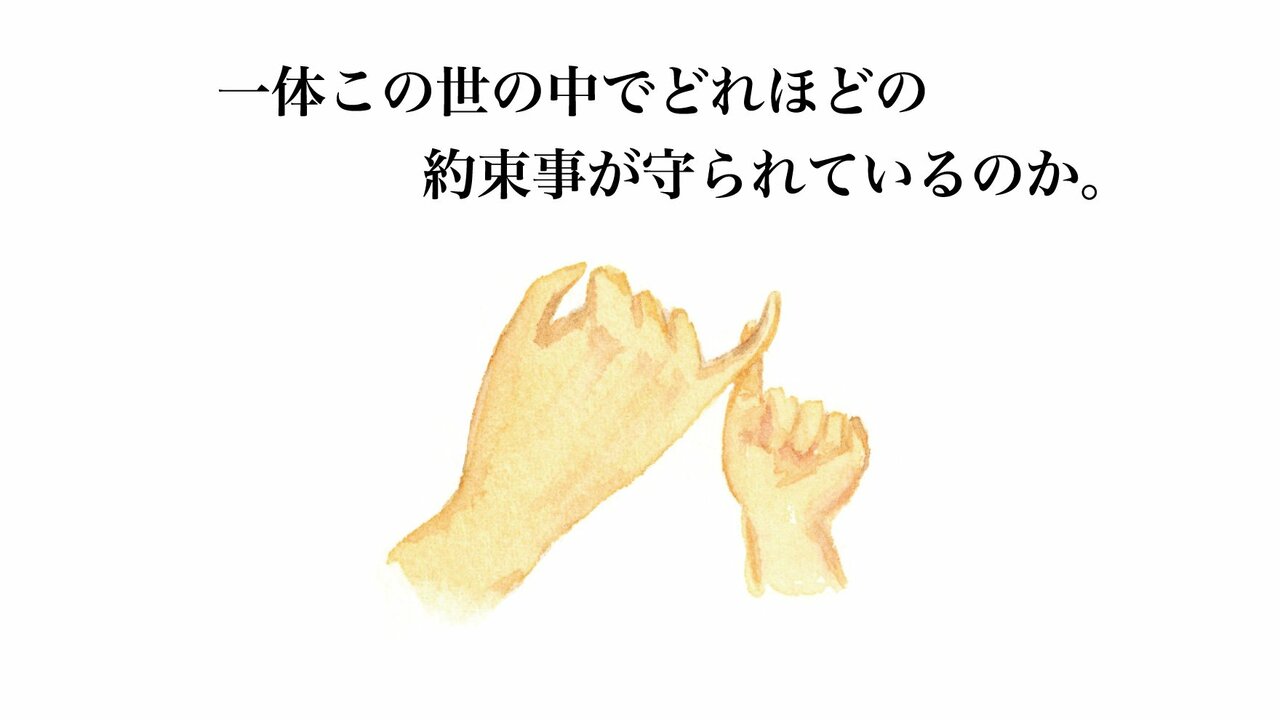年が明けて二〇一六年の正月を迎え「誰も彼も心配だけど、何とか年越しできたなあ」と家族で寛いでいると、布由子の携帯に着信があった。スマートフォンの画面に沙織の名前と電話のマークが表示されていた。念のため沙織の携帯番号を登録してあったものの、それまではほとんど諭本人とのメールでのやり取りだった。諭は自分で連絡できない容体なのだろうか。何が起こったのだろうと心臓がどきんとした。
「沙織さん?」
「お姉さん、新年早々にすみません。今日私一人が諭さんの主治医に呼ばれて、再発したって。治療の手立てがもうないと、あと一、二か月で命の危険があると言われました」
「そんな! 臍帯血移植の後は順調だと聞いていたのに」
「諭さんには、再発したことは伝えましたが、でも一、二か月ということは言えません」
沙織は泣きながら言葉を絞り出すように話し、布由子の口から漏れるうめき声は言葉にならなかった。
「あとは可能性としては新薬の治験に参加するくらいしかないんですが、諭さんはあまり乗り気ではなくて」
「少しの可能性でも、ほかに方法がないんだったら賭けてみるしかないよね。とりあえず私、週末にそっちに行くから」
「すみません、お願いします」
それから何回、沙織とメッセージの応酬をしたり、長電話をしたりしたことだろう。その週末に布由子は夫の隆平と連れ立って白金台の大学附属病院に諭を見舞った。
小さな森を思わせる鬱蒼と植物が繁る庭を通って、昭和初期に建造されたという重厚な門構えの医科学研究所の建物に足を踏み入れると、その奥には近代的なビルが聳えている不思議な病院だった。以前に比べ病室への食べ物の持ち込みが緩くなっていると聞いたので、最盛期を迎えていた地元産の完熟いちごのパックを見舞いに持っていった。
この日の諭も見た目では重篤な病気の患者には思えなかった。諭と隆平は年齢差があるが同じ高校を卒業しているので、共通の話題も多い。諭は高校時代ラグビー部だった隆平に合わせ、前年秋のワールドカップ南アフリカ戦で日本代表が想定外の活躍をしたことを称えた。そして二〇一九年に日本でワールドカップが開催されることに期待し、楽しげに振る舞っていた。
一方ずっと病室に寝泊りし付き添っている沙織には、心身の疲れが見えた。病院の近くのファミリーレストランに席を移して聞いたところでは、病状に加えて元妻の弓恵と子どもたちとの軋轢が諭を疲れさせ、沙織の神経を苛立たせていた。諭は養育費を減らしてほしいことや自宅のローン返済を一部負担してもらうことを弓恵に要望しているが、聞く耳を持たない弓恵と息子の洸太が攻撃的な態度を取っているとのことだった。
物事を理性的に解決できない弓恵の性格を見聞きしてきた布由子と隆平は「弁護士を立てて交渉するしかない」と沙織に勧めた。