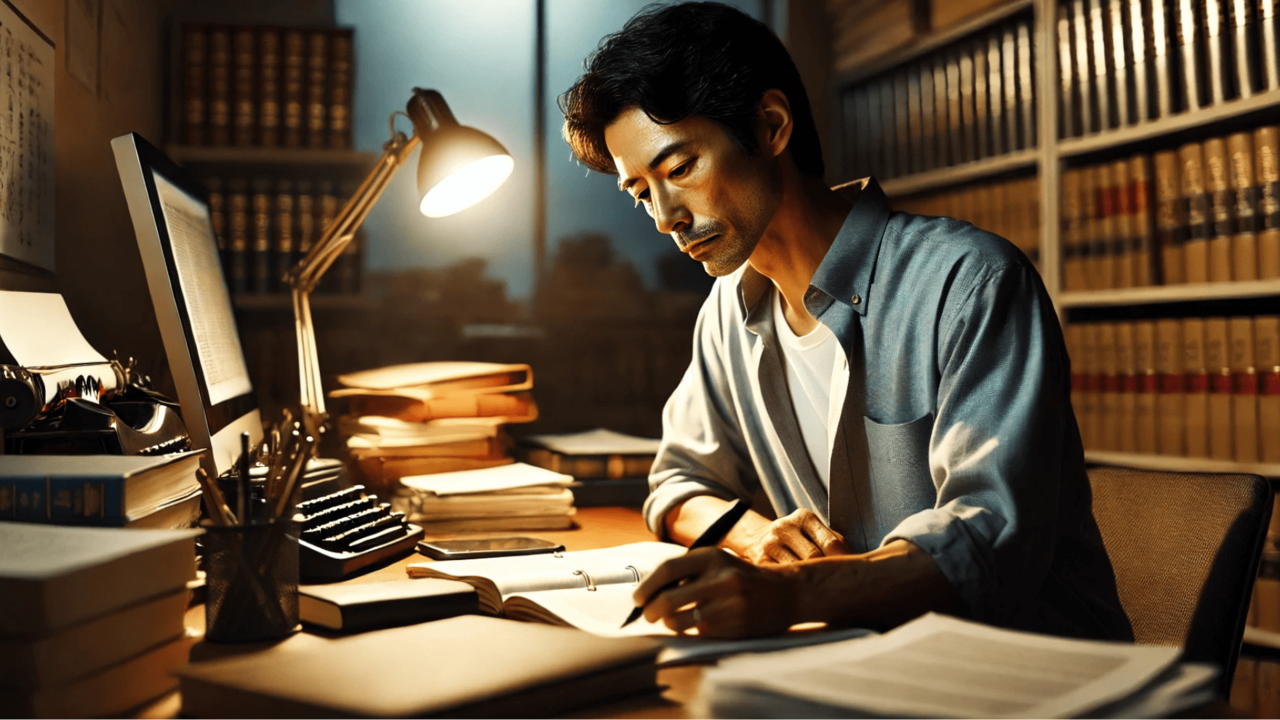結婚
十一月、京都・南禅寺近くの料亭で、双方の家族の初顔合わせの席を設けた。こうして、私たちの結婚は本決まりになった。次の日曜日、婚約したことを、母と一緒に父のお墓に報告に行った。父は、一九七五年四月、五十歳で、すい臓がんのために逝去した。体調不良を訴えてから、わずか二カ月余の闘病だった。私は大学の三年生に進級したばかりだった。
父を看取ったときのことを、あるいは父の人生を、ここで詳しく書くことはできない。それだけで一冊の本になってしまう。ただ、ここで書いておきたいのは、父が特攻隊の生き残りだったことである。
大正十四年生まれの父は、昭和の年号と一緒に歳をとり、昭和二十年には学徒動員で特攻隊員だった。二回、死ぬ予定を生き延びた。一度目は飛び立ったものの敵機に遭遇せず、二度目は飛行機がエンジン不調で飛び立てず。そして、九月に三度目の出撃命令を受けていたが、その前に終戦を迎えた。
「出撃した飛行機が帰ってくると、『何機やー?』言うて、数えるんや。一機、二機、三機……、それがだんだん帰ってくる飛行機が少のうなっていって」
特攻隊の生き残りは、歓迎されなかった。名誉の戦死者が大勢いるなかで、生きて帰った者を見る目は決して温かくはなかった。戦後、父は名前を変えた。次男なので「耕次郎」という本名だったが、「耕次郎は戦死しました。ここにいるのは耕三です」として、「耕三」という通称を名乗った。その後、長年使い続けたことによって戸籍名をも「耕三」に変えた。その父が話してくれたことがある。
「なんで隣にいた者が戦死して、自分が戦死せえへんかったのか、どう考えてもわからん。ただ、生きていたから、お母さんと結婚して、二人の子どもを授かることができた」
「戦時中は、みんなが、お国のために我慢せんとあかん、と言うて、結局はみんなが不幸になった。みんなが幸せになるためには、どうすべきやったんか。まずは、一人ひとりが自分の幸せを考えるべきやったんと違うか。自分が幸せになりたいということは、人さまも同じように、幸せになりたいと思うたはるはずや。それやったら、自分だけやのうて、人さまも一緒に幸せになるためにはどうしたらええのか。そういう方向で考えるべきやった。自分の幸せを、お国や世間に決めてもらうようになったら、あかん」
私が早稲田への進学を望んだとき、祖母が「箱根の山を越えたら鬼が棲んでるいうのに、なんで坂東なんかに下るんや」と反対したくらい古い考えの親戚の中で、父だけは背中を押してくれた。
「恭子の決めたことやったら、恭子の好きにしたらええ」
結婚について、父と話したことが一度ある。東京出身の大学の同級生が「結婚相手の身元調査なんて、絶対に嫌。私の選んだ相手なんだから信用してもらいたい。相手の親が私のことを調べるのも嫌。結婚するのは私たちなんだから」と言った。私は、なるほどと思って、この話を父にした。父は真剣に怒った。
「こちらのことをきちんと調べてもくれへんような相手に、恭子を嫁に行かせとうはない。結婚というのは、自分らだけのもんやない。お相手の方にとっても、大切に育てはった息子さんのはずや」
反論を許さない言い方だった。その剣幕に押されながら、同時に私は父に愛されていることを強く感じた。それなのに、結局は、氏素性も知らぬうちに心惹かれ、結婚する運びになった。父がいたら、なんと言っただろう。「恭子はほんまにジャジャ馬や」とあきれたかもしれない。大笑いしたかもしれない。