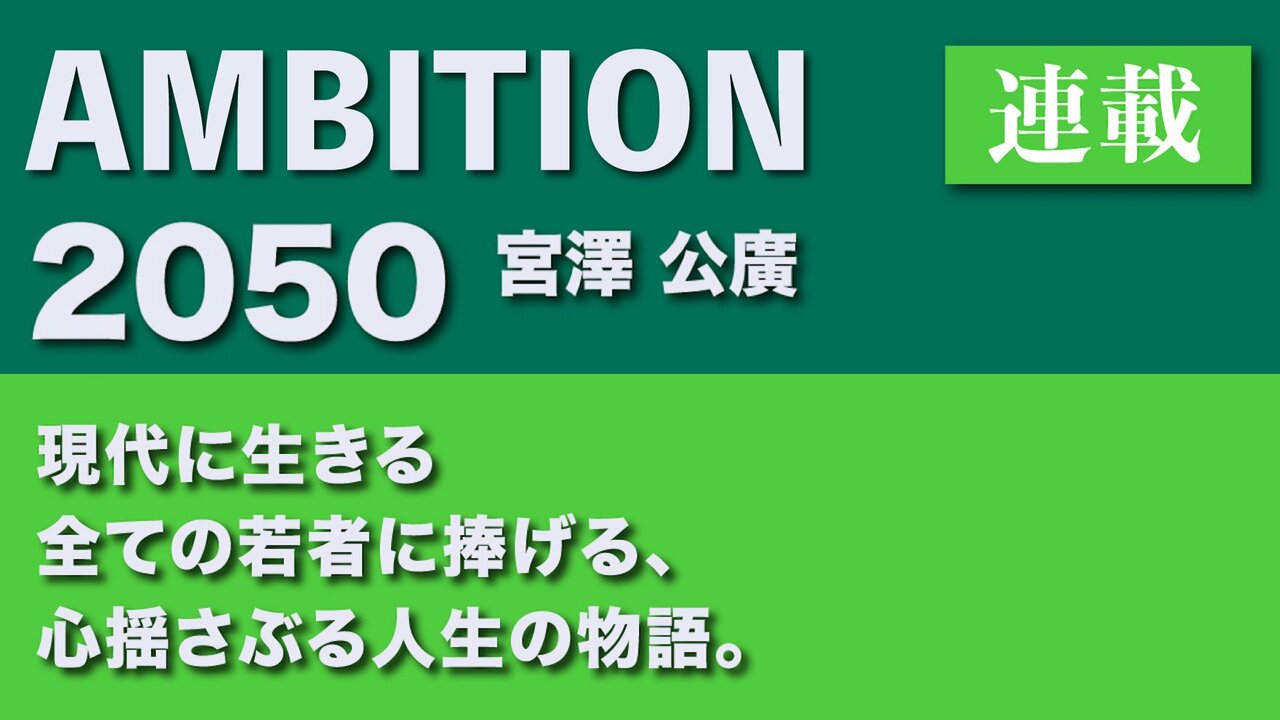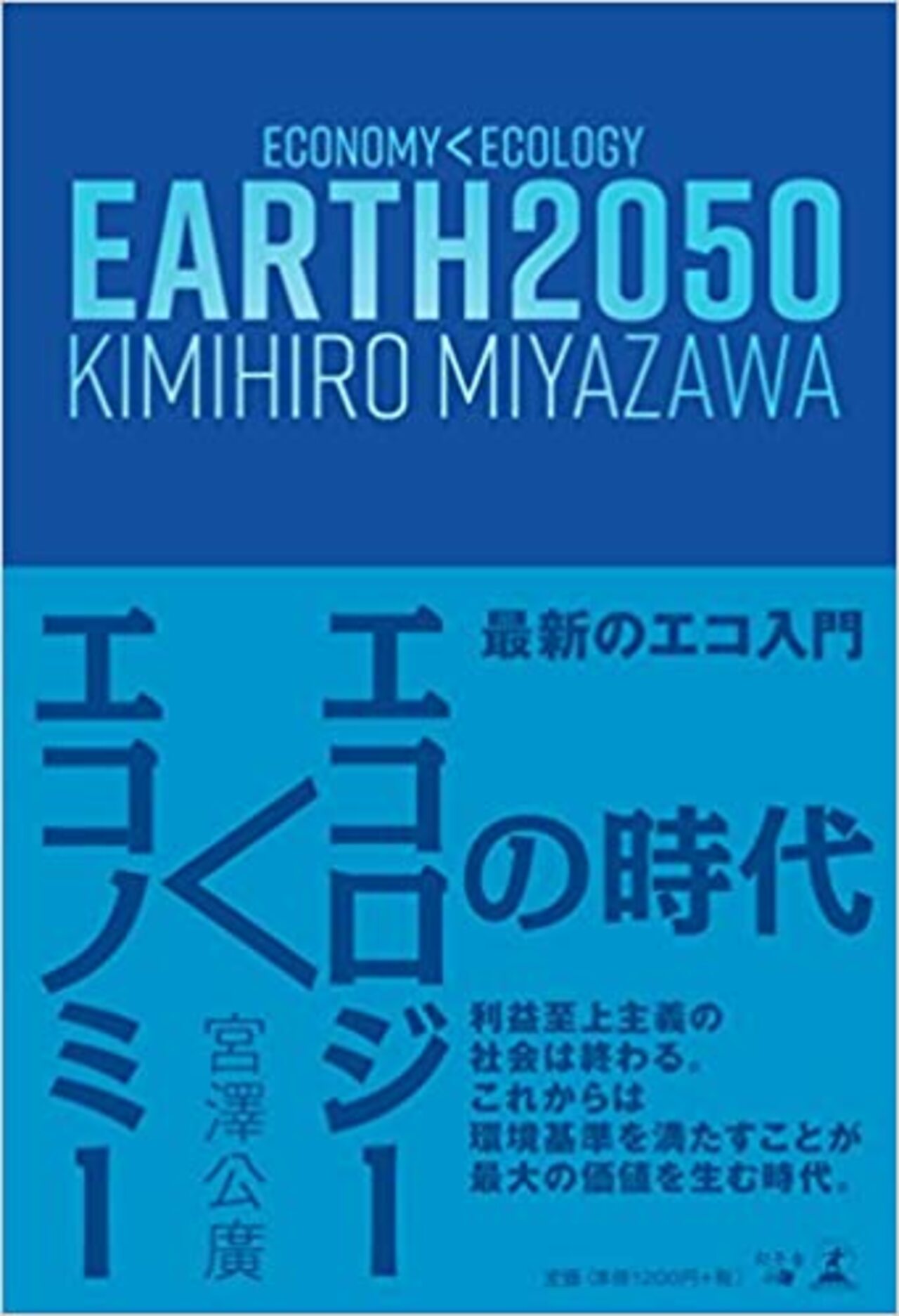第二章 奔走
【8】
足の踏み場もない会見場は、一月とは思えぬほどの熱気に包まれていた。記者席の前方ではフォトグラファーが腰をかがめ、ひたすらにシャッターを切っている。後方ではカメラクルーが陣取り、質問のマイクを渡された際、誤って立ち上がった記者に向けて「立たないで!」と怒声を浴びせている。
誰もが自分の職責をきっちり果たそうと、血眼になっている。快清食品の社長を務める飯塚は、東野の告発を事実と認め、辞任と同時に食肉業界からの完全撤退を発表した。だが、眼前で繰り広げられている光景はどこか現実味に乏しく、宮神はまるで他人ごとのように壇上を見つめていた。
「おい、宮神」
座ったまま俯いていた宮神が顔を上げると、太陽新聞の青柳が立っていた。いつの間にか、会見は終わっていたようだ。
「東野さんの件、助かったよ。電話をかけたら『宮神さんのお知り合いやったら』ってことで単独取材を受けてくれることになった」
「おお、良かったな」
「しかし、世も末だな。ここまで消費者の不安を煽ったら、快清食品は倒産も免れないんじゃないか」
「そうかもしれないな」
青柳は熱を伴った言葉を投げかけてくるが、宮神には会話を続ける気力がなかった。青柳が去ると、深々とため息をついた。初めて東野冷蔵を訪れた昨日、宮神は東野と納得がいくまで話し合い、希望どおり記事中に実名を出すと決めた。
なぜそうしたかは、今でも論理的に説明できない。東野の正直さに感化されたのは確かだろう。
総局に戻った宮神は、大森に内部告発のあらましを伝えた。実名を出したいという東野の希望についても、「東野さんを孤立させないよう、万全の態勢でバックアップせなあかん」と、心強い賛意を示してくれた。宮神はショートしそうになっている頭を冷やすため、ベランダに出て寒風に身を晒した。
自分の席に戻ると、深呼吸をしながら第一稿を書き始めた。心の裡で荒ぶる正義感を制御しつ、客観性――あくまで主観的な客観性ではあるが――を意識して取材した事実を書き連ねていく。最近では、パソコンで記事を書くことにもようやく慣れてきた。加盟社に提出する出稿メニューにおいて、牛肉偽装事件の記事は一面候補のマークが付いた。予想通り、各社からの反響は絶大だった。