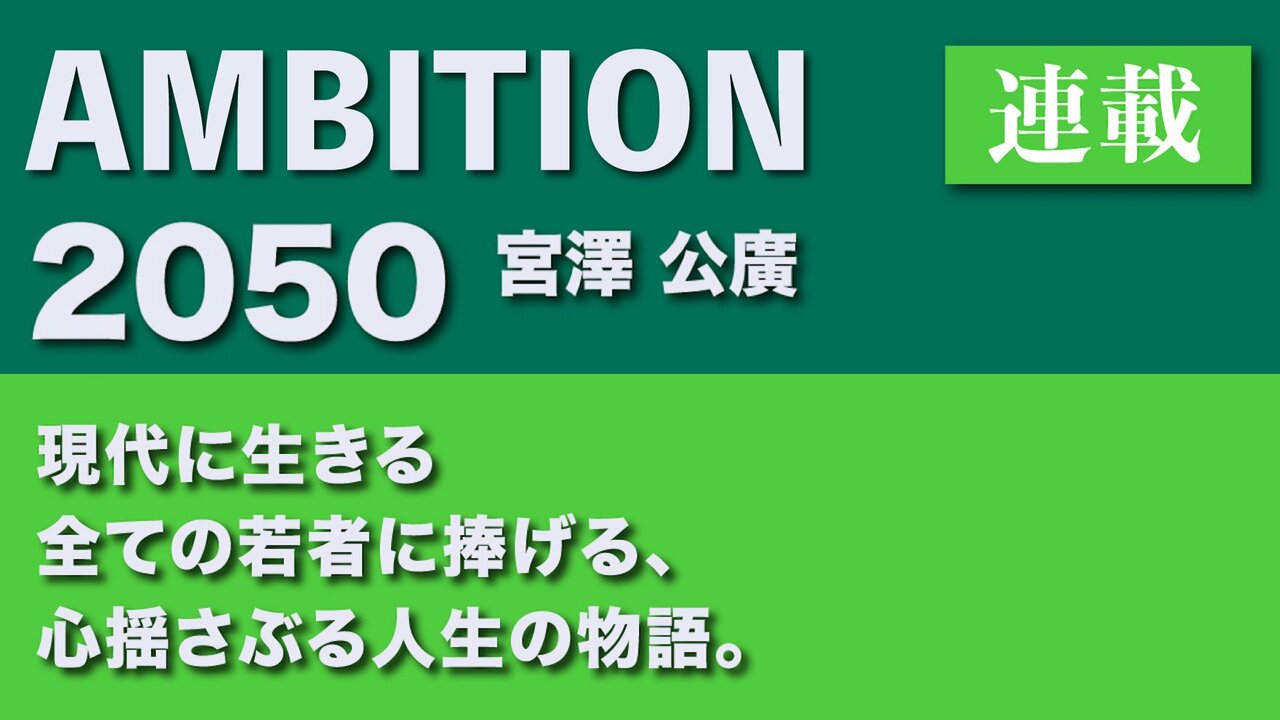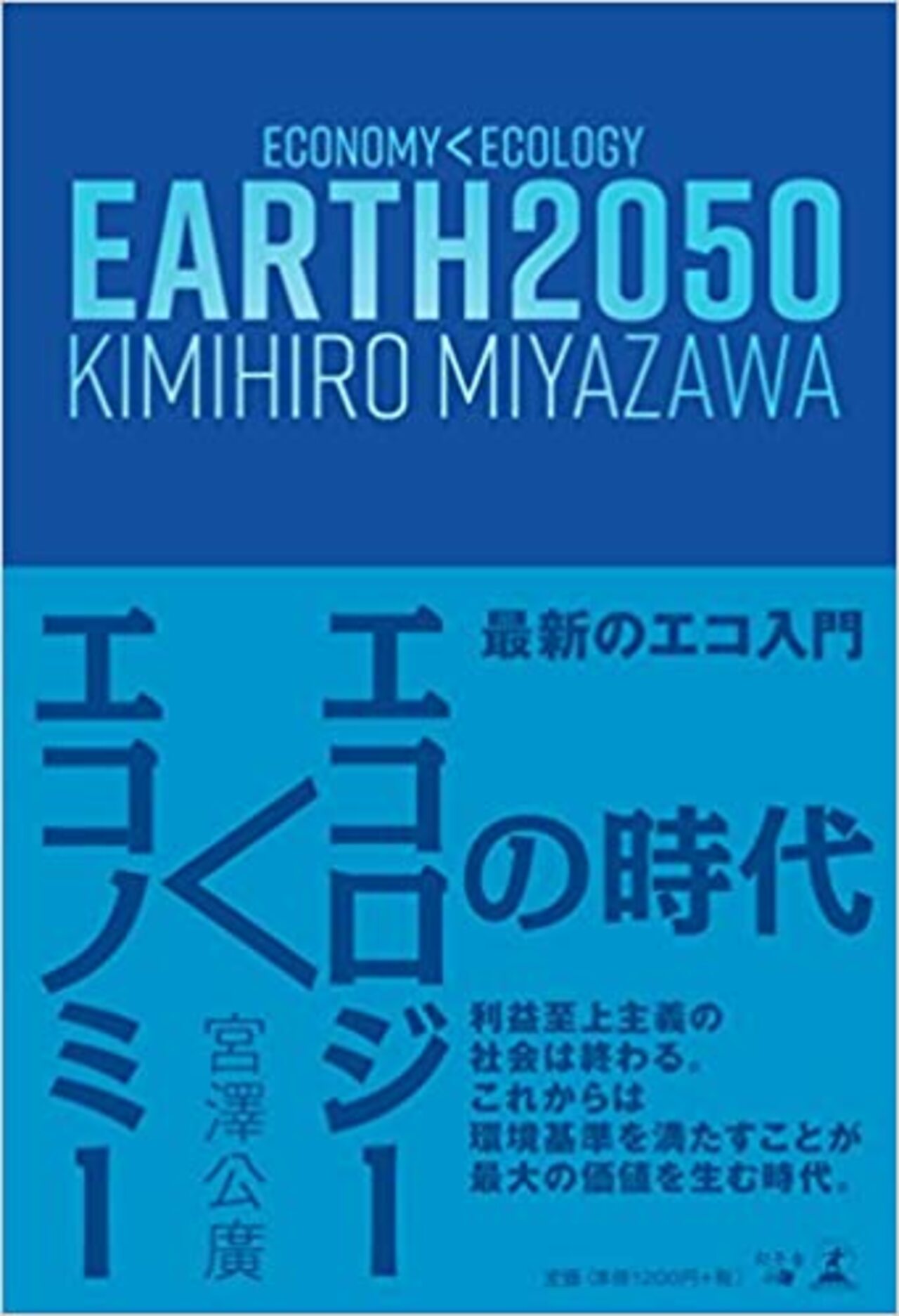第二章 奔走
【5】
「で、どのような偽装が行われたんですか?」
「これが聞いてびっくりよ。去年の十月の終わり頃に、快清食品のお偉いさんから話があるって言われて、出向いたんや。そうしたら、安いオーストラリア産の牛肉を買い取ってもらうから、国産牛肉の箱に詰めろって無茶苦茶なこと言いよった」
「協力したんですか?」
「アホを言いなさんな。そんなことしたらお天道様の下を歩けんようになる。断ったわ。結局、この話は聞かなかったことにしてくれってことでシャンシャンや」
ここで東野は、ようやく缶コーヒーのプルタブを引いた。一気に話して、喉が渇いたのだろう。今のところ、東野の話に不自然さは感じられない。
こちらをまっすぐ見つめてくるその眼にも、噓はないように思われた。取材活動をしていると、注目されたいがゆえに虚言を連ねる人間に出会う機会もあるが、東野の実直さは信用しても良さそうだ。
「ここで終わればよかったんやけど、この話には続きがあってな。話を持ち掛けられた三日後の土曜、早朝に快清食品のやつらがやってきて、うちの倉庫で詰め替え作業をやりおったんや」
「倉庫の鍵は?」
「スペアを渡しておった」
「しかし、大胆過ぎませんか」
「そう思うやろ。でも、これ見てや。あいつら、がさつにもほどがあるわ」
東野は胸ポケットから封筒を取り出し、宮神の前に一葉の写真を差し出した。ゴミ捨て場に段ボールが堆く積みあがっている写真だった。箱の文字に目を凝らすと、アルファベットで、オーストラリア産の銘柄牛の名前が印刷されている。
「撮影したのは社長ですか」
「そうや。前の晩に遅くまで書類仕事をしてて、ソファで寝てしまったんや。朝っぱらからゴソゴソうるさい思うて外に出たら、快清食品の保冷車が駐車場にあってな。倉庫へ行ったら、ちょうど詰め替えの作業をしとった」
「人数は?」
「十人くらいかのう」
「止めたんですか」
「当たり前やろ。やめろいうたけど、誰も取り合ってくれん。ダメ押しで、週明けには伝票の改ざんまで指示されたわ。さすがに怒鳴りつけてやったけどな」
「音声の録音は?」
「しとらん。証拠といえばその写真だけや」
気づけば、脇の下が汗ばんでいる。膝がかすかに震えている。社会を揺るがす特大のスクープだ。
「ご報告に感謝します。しかし、なぜ私に話をしてくれたのですか」
「東洋新聞で、あんたが書いたBSEの特集記事を読んだんや。正確な情報を伝えようとする姿勢が気に入ったし、神戸に対する気持ちも感じた。話すなら、あんたが適任やと思った」
宮神の肌が粟立った。自分の署名記事がスクープにつながるとは、思ってもみなかった。記者冥利に尽きる話だ。しかし、東野は宮神を感慨に浸らせず、続けざまに衝撃的な一言を告げた。
「この告発は、実名でさせてもらう」
時刻は午後八時を過ぎていた。石油ストーブにのっている薬缶から湯気が立ち上り、シュンシュンという音が聞こえてくる。
宮神は東野に内部告発のリスクを延々と話し続けたが、東野は正義感に燃えており、話は平行線をたどっていた。日本の企業は共同体意識が強く、告発者は組織から排除される傾向にある。
アメリカでは、一九八九年に内部告発者保護法が、イギリスでは一九九八年に公益開示法が制定されたが、日本では同様の法律がない。東野が実名を出した場合、その心意気に共感こそ集まるかもしれないが、潮が引くように取引先が離れていき、経営が立ち行かなくなる可能性もある。
「どうしても実名でないといけませんか」
「譲れんな。そもそも、悪いことをしているのは快清食品や。ワシがこそこそする必要はないやろ」
東野は一本気な性格であるうえに、腹が据わっている。宮神がいくら匿名による告発を勧めても糠に釘だった。しかし、宮神もすぐに折れることはできなかった。宮神は、数年前に体験したひと夏の記憶を思い出していた。