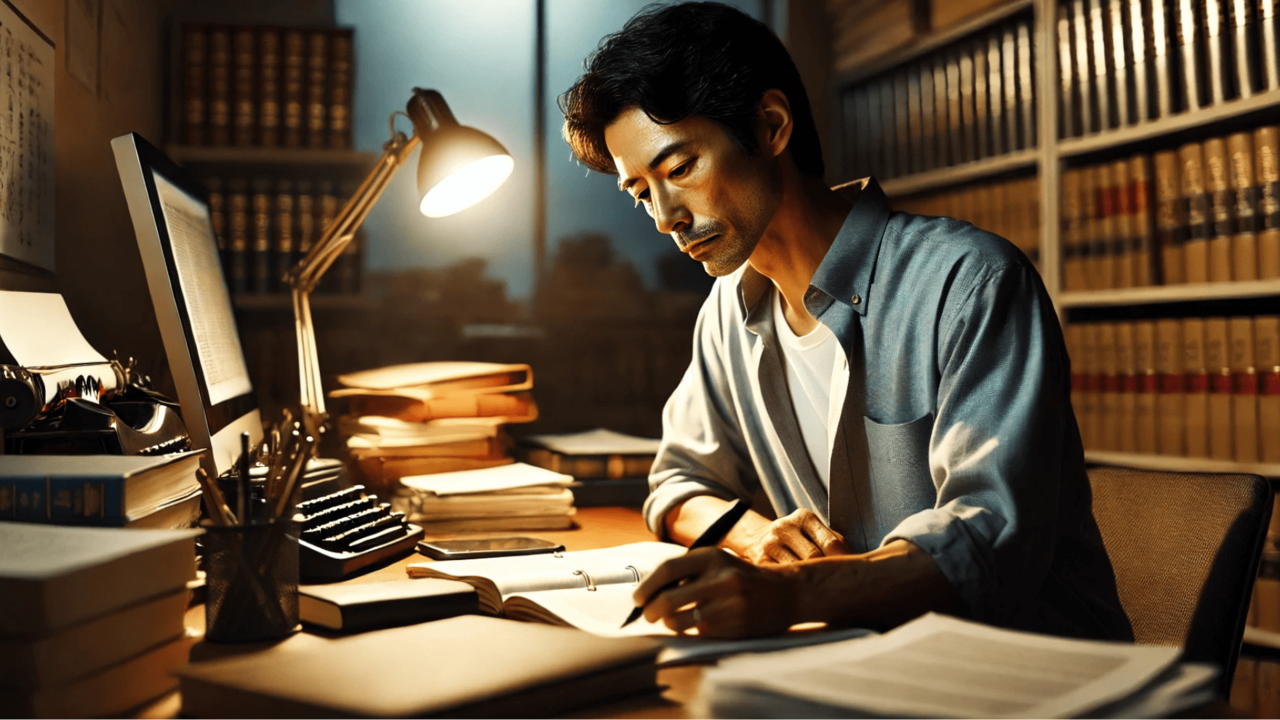後日譚になるが、結婚後、ある勉強会から帰宅した博史が「今日の講義、難しくて、さっぱりわからなかった」と、頭を抱えていたことがある。
「わかっている人に教えてもらえば?」
「みんな、わからなかったんだ」
「全員がわからなかったの?」
「いや、〇×さんだけは、理解していたみたいだ。……僕はまだまだダメだなあ」
しきりに溜息をつく。
慰めたくて「よかったわね。そんなすごい場にいられるなんて、幸せなことじゃない。ありがたいわねえ」と言うと、「うん。本当にそう思うよ。僕は恵まれてるよなあ」
心底、うれしそうだった。
一九八九年、博史は博士課程在学のまま早稲田大学社会科学部の助手に採用され、論文を大学の『紀要』などに発表していった。
論文は、推敲の連続である。まじめで一本気な博史は、法律について書くのに誤解される余地があってはならないと一字一句にこだわって、何度でも書き直す。新しい情報を仕入れることにも熱心で、次々に書き入れていく。
博史が大学院生の頃にはワープロもパソコンもまだ高嶺の花で、原稿は手書きが主流だった。かりに原稿用紙の一枚目に修正や挿入をした場合、たとえ原稿用紙二百枚まで書き上がっていたとしても、字数をそろえるために残りをまるまる書き写していくことになる。
書き直しを嫌う人や朱筆で済ませる人もいたが、博史は「若手の論文は、きちんとした原稿でなければ読んでもらえない」と、清書にこだわっていた。
彼らしいエピソードがある。博史の修士論文は、四百字詰め原稿用紙に五百五十枚超、分厚いファイリングで上下二冊。ところが、ページ番号の筆跡が、途中で変わっている。論文の書き直しに追われた博史がページの記入を後輩に頼んだのだが、原稿を書き直すたびにページ番号も書き直さなければならず、とうとうその後輩が音を上げ、別の後輩にバトンタッチしたのだそうだ。
そんな博史だったから、助手になって給料が入ると、すぐにパソコンを購入した。書き直しもページの打ち込みも、キー操作一つでできる。大喜びで、のめり込んだ。