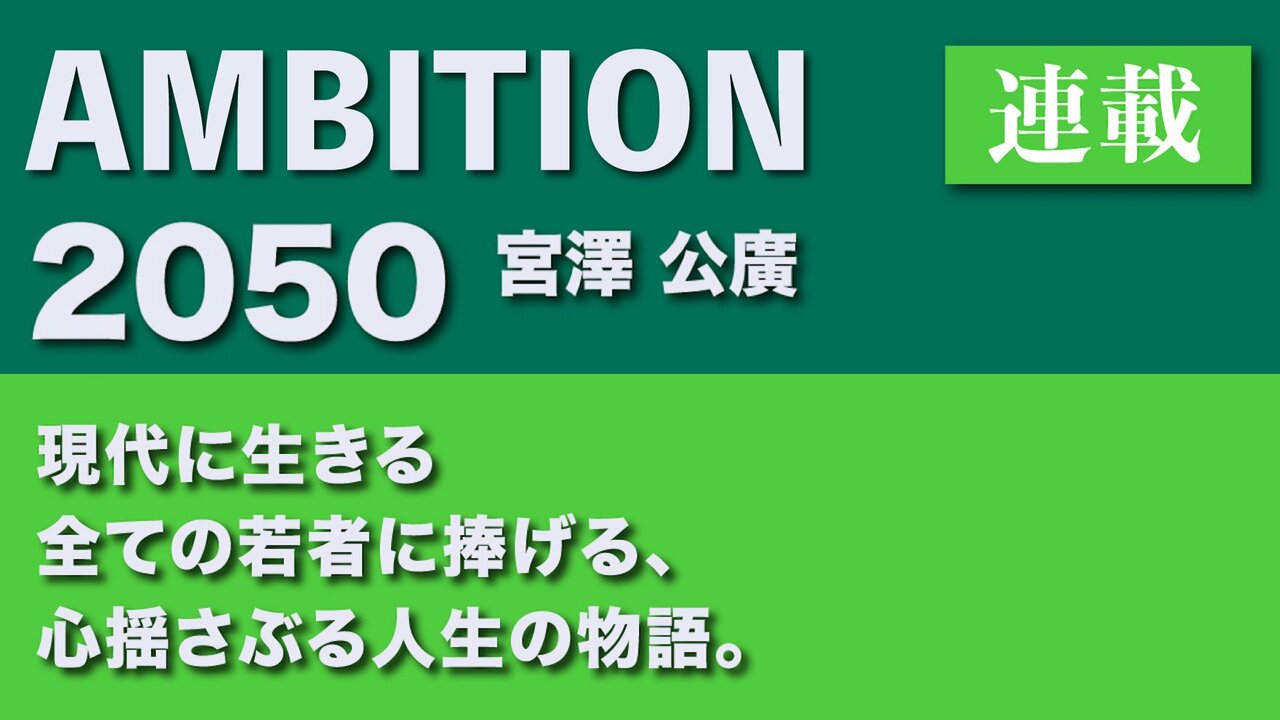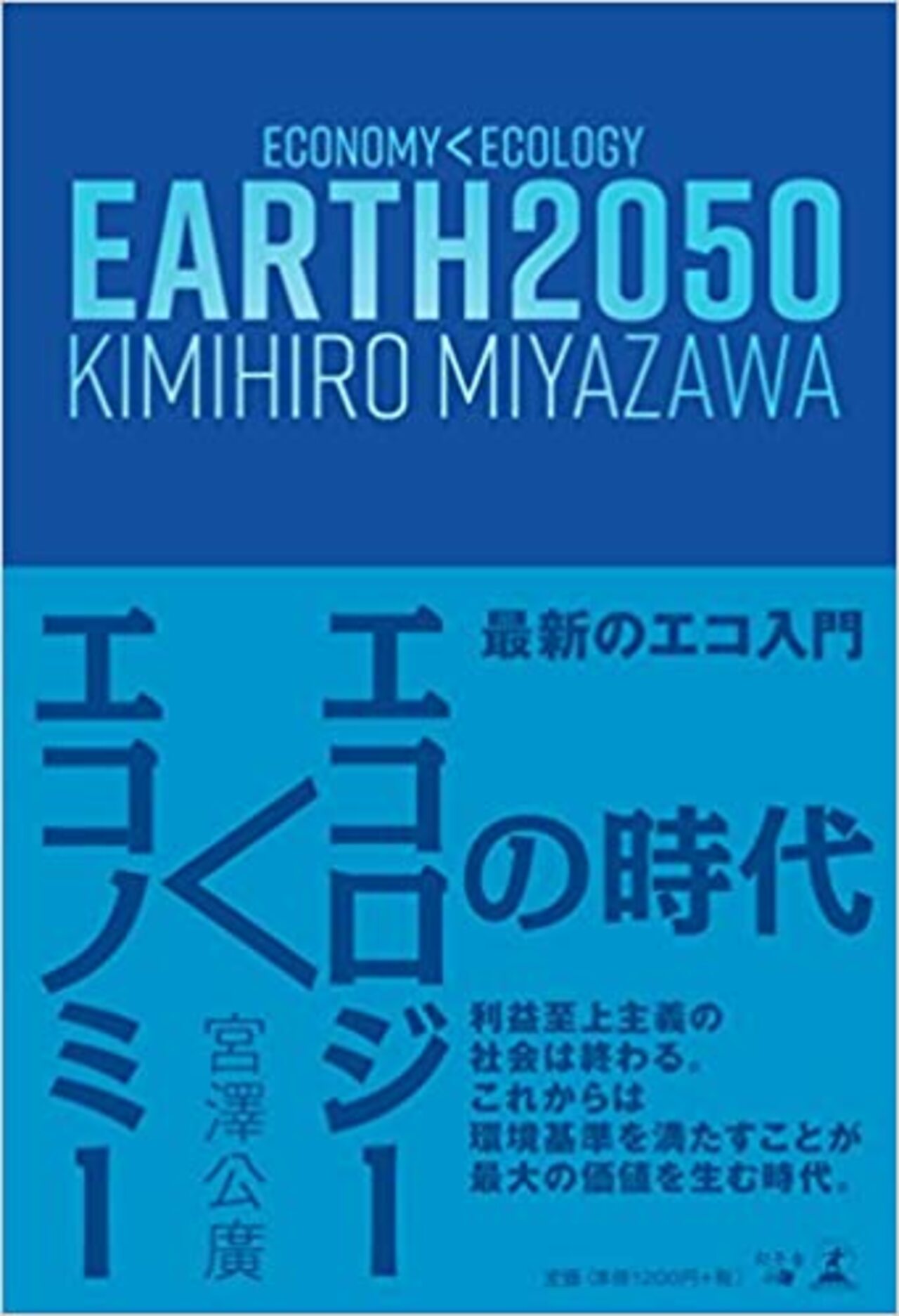第二章 奔走
【4】
二〇〇二年一月下旬の午後、取材を終えた宮神は、遅めの昼食に牛丼をかき込んでから社に上がった。
「宮神、飯は食うたか?」
自分の席につくと、キャップの大森が話しかけてきた。学生時代にラグビーで鍛えた大森の体軀はがっしりしており、寒さにもとことん強いようだ。寒さが身にしみる一日にもかかわらず、今日もシャツの袖をまくっている。
「はい、牛丼を食べてきました」
「そうか、蕎麦でも奢ってやろうかと思ったんやけどな」
「大森さんが奢るだなんて、珍しいですね。明日は雪になるんじゃないですか」
「おうおう、言うたな。お前には今後一切ご馳走せえへんぞ」
財布の紐が固いことで知られる大森は、右手で自慢の顎鬚を触りながらニヤリと笑った。宮神にとって上司ではあるのだが、普段から冗談ばかり飛ばしている大森は部下の堅苦しい態度を好まず、いつの間にかフランクな会話をするようになっていた。
「それにしても、宮神よ。お前さんは牛丼食うのに抵抗ないんか?」
「抵抗、ですか?」
「BSEや。俺な、あの発表があってから牛肉を食うのが怖なったわ」
「あんな発表の後だからこそ、検査に力が入っていて安全なんじゃないですかね」
「危険がないのはわかっとるが、どうしても体が受け付けん。ま、俺は蕎麦を食うてくるわ」
大森はそう言い残してフロアを出ていった。記者であるならば、読者の不安を扇動するような言動は慎むべきだが、今の発言は非公式だ。騒動を受けて牛肉を忌避したくなる心情は、理解できなくもなかった。
「宮神さん、電話です」
一年生記者の岡田が電話を取り次いでくれた。
「誰だ?」
「ヒガシノさんです」
「ヒガシノさん? どこの?」
宮神には、ヒガシノという名前にまるで心当たりがなかった。
「あれ、お知り合いじゃないんですか」
「お前な、今度から所属先までちゃんと確認してくれよ」
「すみません」
気分が顔に出やすい岡田は仏頂面になってしまったが、気にせず受話器を取り上げた。
「宮神さんか?」
電話口の男は、酒灼けしたようなかすれた声の持ち主だった。年齢は四十代後半といったところか。
「はい、そうです」
「食品関連の記事をよう書いとる、ユニオン通信の宮神さんやな?」
「間違いありません」
「ワシは東野いうて、市内で冷蔵倉庫の会社をやっとる者や」
「冷蔵倉庫、ですか」
「そうや。急やけど、話したいことがある。直接会えんか?」
「どのようなお話ですか」
「正味の話、食品安全に関係することやな」
「伺います」
宮神は即答した。
「ご都合がいいのはいつですか」
「今からワシの会社に来てもらえるか」
「結構です。場所はどちらですか」
「タウンページで東野冷蔵を探せば住所もわかるはずや。五時を過ぎればちょうど仕事も終わる。ほいじゃ、待っとるで」
「あ、ちょっと待ってください!」
宮神は声を張り上げたが、すでに電話は切れていた。岡田が怪訝そうな顔で「どうかしましたか」と聞いてきたが、宮神は質問には答えず「電話帳はどこだ?」と尋ねた。その勢いに気圧されたのか、岡田は何も言わず分厚い電話帳を差し出してくれた。
デスクの上で開き、は行のページを捲っていくと、東野冷蔵で登録されている番号は一社しかなかった。所在地の西宮浜までは、ここからタクシーで二十分程度だ。さっそく一階へ降りていくと、エレベーターホールで楊枝をくわえた大森と出くわした。
「どこに行くんや?」
「ネタ元と会ってきます」
「何か摑んだら必ず報告やぞ」
「もちろんです」
無駄話をしていた先ほどとは打って変わり、大森の眼光が鋭い。獲物を捕食しようとする肉食動物のような威圧感がある。宮神は国道へ出てタクシーを捕まえ、運転手に目的地を告げた。
車が走り出すと、ひとつの疑問が頭をもたげた。これからタレコミをする人間が、事前に身分を明かすものだろうか。もしかすると、無駄足に終わるかもしれないぞ――。
そう思う反面、スクープへの期待で胸が高鳴っているのも事実だった。刑事との駆け引きでやっと得られるネタもあれば、たった一本の電話でスクープが書けるケースもあるのだから、記者という仕事は本当に奥が深い。宮神は、車窓越しに暮れ行く街並みを眺めながら、深く深呼吸して心を落ち着かせた。