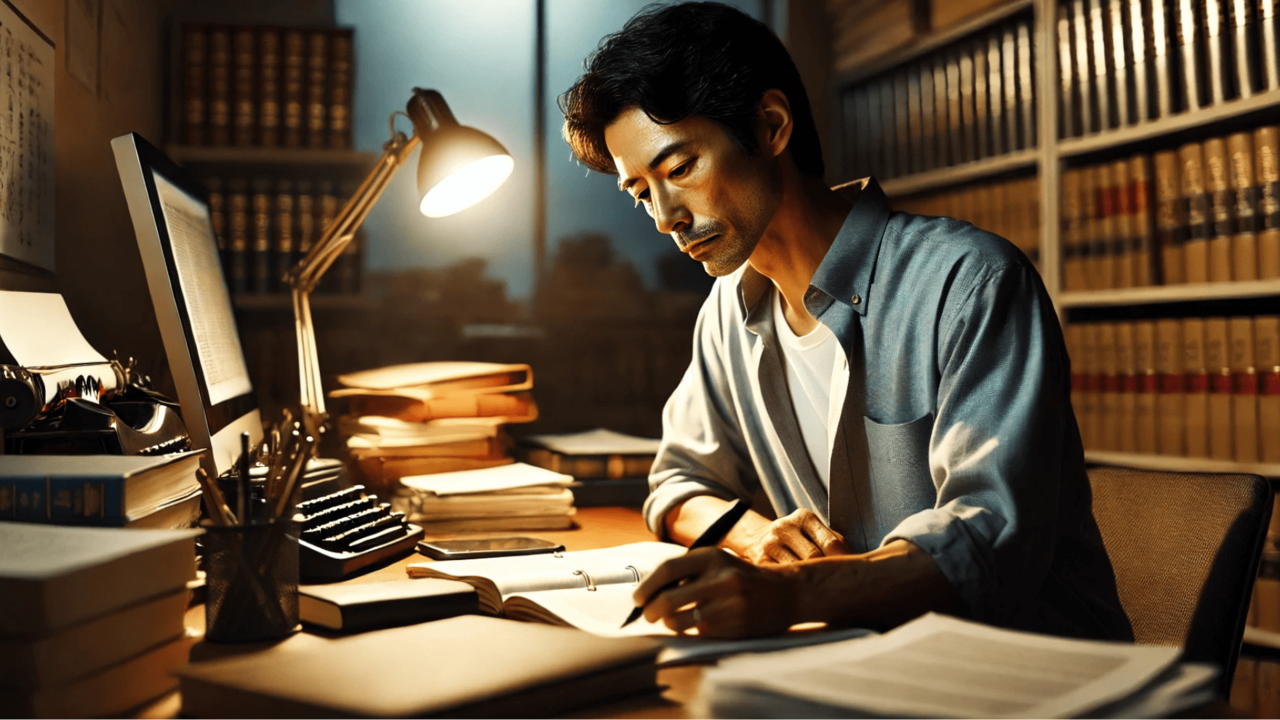博史との再会
予定より一時間以上遅れて、着陸態勢に入った。飛行機が地面に触れてガクンと揺れたその瞬間、「博史を追いかけなきゃ、博史を探しに行かなきゃ」という訳のわからない意識が脳に浮かんだ。間髪をいれず、「バカッ、何を言ってるのッ」と別の意識がよぎった。
そこで気づいた。私が向かっている先に、博史はいない。博史の体があるだけだ。私は今、博史に会いに行くのではない。博史の血の通わぬ体を引き取りに行くだけだ。博史の声を聞くこともない、どんなに急いだとしても待ち合わせのように「遅れてごめん」と言う相手はいない。それでも行かねばならない。これからの仕事は、私が博史にしてあげられる最後の仕事だ。妻としての最後の務めだ。きっちり務めを果たす。夫、西原博史をしっかりお見送りする。
飛行機は、午前十一時三十分過ぎに、予定より一時間ほど遅れて成田に到着した。到着ロビーは混んでいて、思いがけず大勢の日本人による日本語の洪水に巻き込まれた。大雪のせいで都心への交通網がガタガタだった。成田エクスプレスも京急も、チケットを求める人々で長蛇の列。タクシーは論外で動いていない。
予定では、私は病院に駆けつけて博史に会い、そこで少しなりとも二人だけの時間を過ごした後に、葬儀社の車に同乗して帰宅する手はずだった。しかし、病院にも自宅にも移動する手段がない。娘に電話した。
「家まで帰る方法がないのよ」
できるだけ冷静に言ったつもりだが、悲鳴のような高い声になってしまった。娘は、忙しそうだった。朝から病院に行って説明を受けてきたと言い、「病院には、正午までしかいられないの。今はオーパが付き添ってる。私と正博は、お迎えの準備のために、先に家に帰ってきたところ。家の前の道路も雪が積もってて、車もノロノロしか走れない。それから、和室とリビングの掃除、お隣さんがやってくださった」
お隣の奥さんが掃除機とゴミ袋を持ってきて、和室も台所もきれいにしてくださったという。庭続きの家の奥さんは、食事を届けてくださった。出版社・成文堂の社長も駆けつけてきて、家の前の道を雪かき最中とのこと。
「正博は何をしてるの?」
「電話番。電話の前に座りこんで、『母が今日、帰ってくるので、いろいろなことはそれから決める、ということになっています。すみません』と、ずうっと言い続けてる」
息子も、非常事態に必死に対処しているようだ。私は成田で動けない。十分おきくらいに娘と電話で話す。博史を自宅に搬送する寝台車が病院に来るまでに、病院へ行けるか、間に合わないか。
とうとう、「葬儀社の方から、寝台車がもうすぐ病院に着く、という電話があった。ママは直接家に帰ってきて。パパには、オーパが付き添ってるから」ということになってしまった。
「わかった。病院には行かないで、家に帰るわ」(ああ、二人だけで過ごすお別れの時間が、なくなってしまった)
重い宣告を受け入れる気持ちで、自分に言い聞かせた。
後から思い返せば、夫と二人きりの時間が持てなかった結果、取り乱さずに済んだのかもしれない。もしも彼の変わってしまった姿に会っていたら「何か言ってよ!」と泣き崩れていたかもしれない。取りすがる機会をなくしてしまったことが、よかったのかどうかは、今もわからない。最後にもう一度、誰も見ていないところで、思い切りハグしたかったのだけれど。