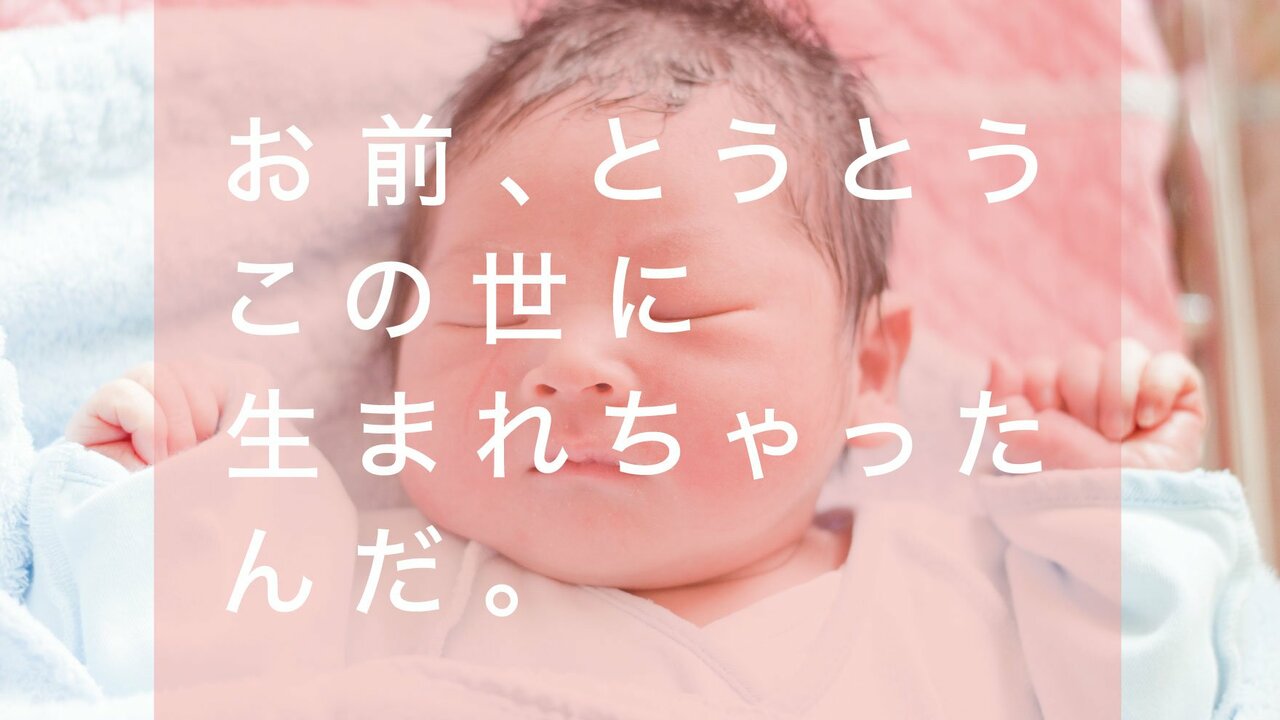うちに来てもらいましょう、毎晩でも。それからバンケットにしましょう。お義父さんと太洋くんに気の毒だわ。あなたが毎日会っているのにちっとも知らないでいきなり二十週の嫁の親と食事なんて。
親父は気の毒というか可笑しいと言うか、外階段を上がったり下りたり、この階段は危ないなと呟いたり、太洋を呼んだり。何だって?と太洋に訊くと首を振って耳の所で掌をぱあ。その太洋は糞っ、糞っと機械を叩いて回るし。
俺たちも真似して割烹を頼んで、俺が少し金持っているので、手作りはしないから淳さんの負担にはならないから、と噛み砕いて言うまで親父は恐縮していた。
「わたしが自信なくて黙っているように頼んだものだから」
淳さんの助け舟で親父は大分リラックスした。太洋はピンクのシクラメンの鉢を持ってきて部屋の隅に置いて、嬉しそうじゃなかった。結構なご馳走なのに食欲も見せない。
「わたしは一人っ子だから、この子の叔父さんは太洋くんだけなの」と聴いてから「俺だけか……貴重だね」
独り合点してやっと真面に淳さんのお腹を視た。
「男だって? 幸せにしてやろうぜ」
親父が身の程を弁えろと叱ると「淳さんには通じるんだ」
親父はサンルームを覗いて、アトリエ増築するか、と独り言した。
太洋の奴、帰りがけ、やっぱりショックだ、やっぱりショックだ、と悄気ていた。
本当だ。俺たちはほんの小さな家族なんだ。親父とも太洋とも引き合ったり弾き合ったりしてきたが、貴重なんだ。とにかく近い。
親父は電話してから来る。淳さんは躊躇いもせずお腹に触らせる。親父はどんどん爺ちゃん顔になってくる。太洋は兄貴を無視して、赤ん坊は元気? と言って来るんだ。