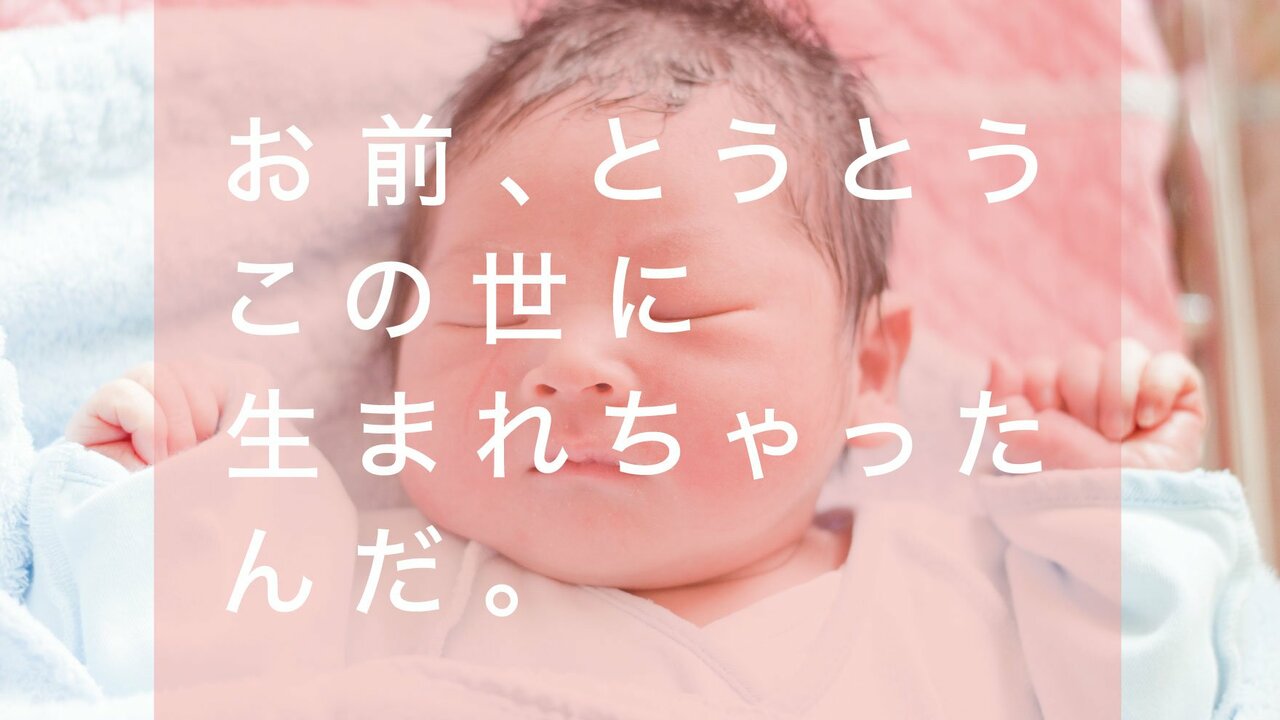義父からの電話
日の出が遅くなる。照明を昼白色に変える。昼間に確かめて色とタッチを修正する。
木工所の応接コーナーの壁に『工房の隅のジム』が掛かる。除幕式だと浮かれる。それは勘弁してもらったが、一時間ほど社で祝ってくれた。十人、住み込んでいるから、盛況だった。親父の笑顔の含羞にふっと打たれた。太洋が、父ちゃんの理屈だと、兄ちゃんの絵は全部うちの物になる。兄ちゃん、額縁の注文早めに出せよ。本業が先だからな。冬は海に出ない。全部作ってやる。
「絵を本業にしてもいいぞ」
親父が寄ってきてさり気なく言う。
「辞めたくない」
淳さんがベッドで抱かせてくれる。大の男になった気がして、堂々と乗って、ゆっくりと腰を入れる。
日は速やかに移り行く。時は淳の躰に密やかに積もる。その膨らみの眩しさ。生い立ちの痛みはもう蜃気楼のように消えていき、今、八汐は春の潮に満たされるように感じる。筆遣いは優しくなっているだろう。淳は時々悩ましそうだが、悪阻は軽かったようだし、カルシウム、カルシウムと食事の度に唱えている。軽い音楽をかけ、胎教だと言ってクラシックを聴き、室町の母親から聞き覚えた子守歌や可愛い童謡を口遊むのである。八汐の生い立ちに欠けていたものが今、遠過ぎたところからやっと届いたみたいに。
「うるさいだろう? 退屈になったもんで」
と言っては義父から電話がくる。いつも重信がいっしょで。
「今年は外苑止めて、君らの家に行こうか、こっちに来るか」
向こうは来たいし、こちらは行きたい。
「そりゃ君たちが優先だよ」
淳に
「高谷からの伝言だ。高谷、生方くんの義理の兄さん、生方くんは元気になって東京に戻ったそうだ。君に伝えてくれと本人が言ったそうだ」
「そう。よかった……」
伝聞なのも。
「躰が重くならないうちに来ないか」
勝手の上がり口に発泡スチロールの箱が積んである。割烹からの祝い膳である。淳を使わないこと、八汐に飲ませないことが今日の約束。
「重くならないうちにと思ったが、結構重そうだね」
「もうすっかり人間様で、羊水がたくさん要るのですって」
「人間様って、男か女か」
「男」
「右利きか左利きか」
「今度医者に聴いてみます」
「そんな変なこと」
男三人が笑う。
「こいつの好物というのが」
八汐が『麴屋の甘酒』の瓶を取り出す。一斉に笑う。
「聴こえてるのよ、きっと」
「辛党なのか? 甘党なのか?」
爺さんがお腹に向かって聴く。
「どこにいても麴の匂いがするとふらふらと行ってしまうの」
「もう暴れるのか?」