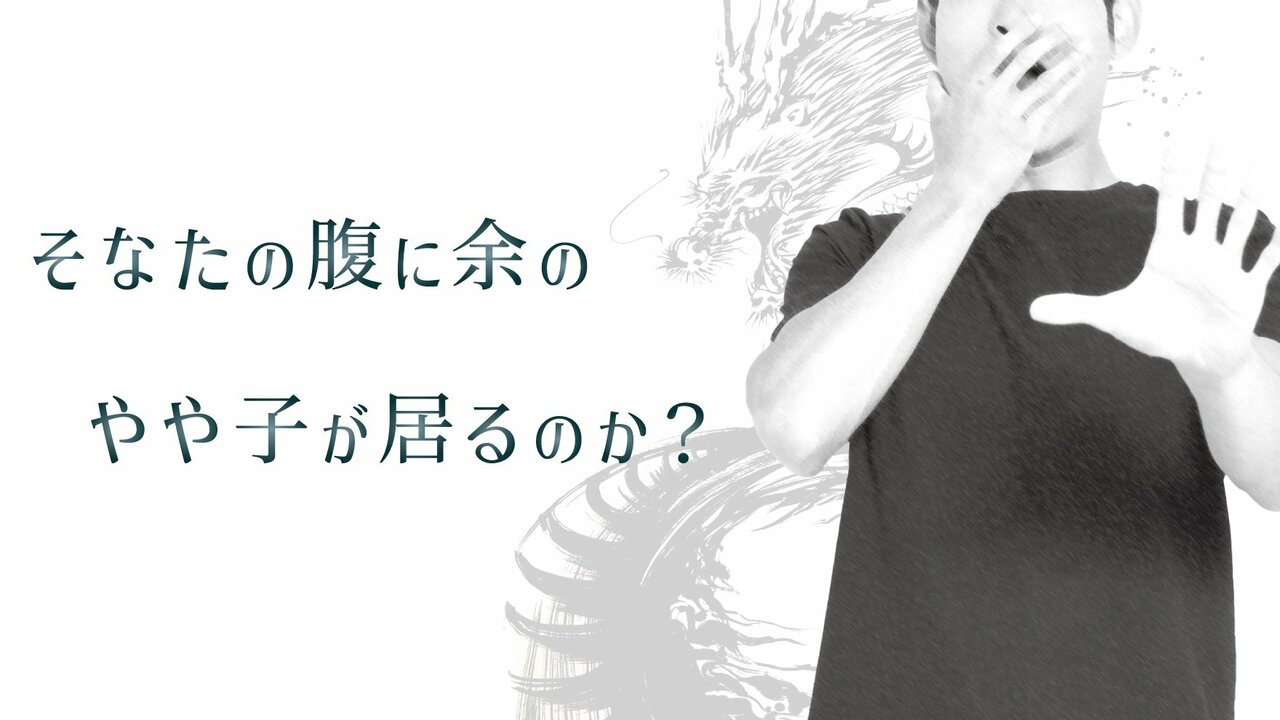羅技が後ろを振り返ると、赤い髪の毛に、異様に青白い肌、そして金色の瞳をした若い男がニヤニヤと含み笑いをし、岩の上に立っていた。羅技は男を睨み、
「異様な姿をしている……。そなたは何者だ? それに何所から来たのだ? この森には誰一人容易に近寄れぬ筈だが。まあ良い。即刻この場より立ち去れ。さもなければ我が切り捨てる」
と言い放った。
「あはは! 余を切り捨てると申すか! さて、そなたのその細腕で余が切れるかな?」
羅技達は木刀を木に立てかけていた剣に持ち変えた。
「羅技姫様に向かって笑うとは無礼な奴め!」
中根は男をめがけて剣を振り下ろした。すると、男は素早く身を躱した。
「やれやれ。人間とは真に厄介な生き物だ……。やたら戦いを好む。余はまだ切り殺される訳にはいかぬ」
男は大儀そうにしぶしぶ腰に携えている剣を抜いた。重使主と仲根はそれぞれに男を目がけてかかりに行ったものの、呆気無く峰打ちをくらいその場に倒れた。
「そなたは人間では無いのか? では手加減せぬ」
羅技は剣を構えると、男に切りかかり、幾度となく男と剣を交わした。それは日の光が傾き、辺りが薄暗くなるまで続いた。

「剣の扱いがとても上手い! 普通、体力も尽きるのだが……。そなたは強いな! それにとても美しい! 余はそなたが気に入った! 余の妃になれ!」
「ちっ」
羅技は男の言葉に怒りで涙を流し、身体を震わせた。
「おのれー。二度とその様な言葉を発せない様にぶった切ってやる」
すかさず高く舞い上がると、再び二度三度と激しく剣を打ち合ったが、羅技の振り下ろす剣は全て男に躱されてしまった。男の剣の腕は数段も勝っており、そのうち羅技の腕は重い剣を持つ手が痺れ出した。一方、男は何も無かったかのように涼やかな顔をし、剣で自分の肩をポンポンと軽く叩いて笑っていた。
「ふっ! まだ打ち合いをするか? その細い腕は剣をもう持てぬと言っているぞ」
「何をっ……!」
羅技は両手で剣を持つと再度、男に切りかかろうとしたが、剣を落してしまった。
「うっ……」
「もう止めぬか? そなたは強い! だが、余には勝てぬ。これ以上剣の打ち合いをすると身体に傷を負う……」
羅技の目に涙が溢れ、袖で拭うと剣を拾い、再度剣を構えた。
「我は龍神守の里の羅技だ。妹姫の幸、父上、そして里の武人達の仇を討たなければならぬ。我がお前のものにだと? その言葉、断じて許さぬぞ」
羅技は剣で突きかかったが、男に呆気なく剣を叩き落とされ、額飾りを男に奪われた。
「ああっ……」
男は剣を鞘に納め、
「そなたは女の身でありながら何故男の様に剣を持つ?」
と言うと、羅技はその場に崩れるように座り込んだ。
「我は次期当主となり、里を守る様に定められて育った。だが、阿修の国の保繁に里を攻め落とされてしまった。父上や里の武人達も殺され、妹姫の幸姫も自害した。我は眠らされて里から出されたのだ……」
男に叩き落とされた剣を拾い手に持つと、羅技の瞳から涙の滴がポタポタと止めどなく零れ落ち、剣に当たった。