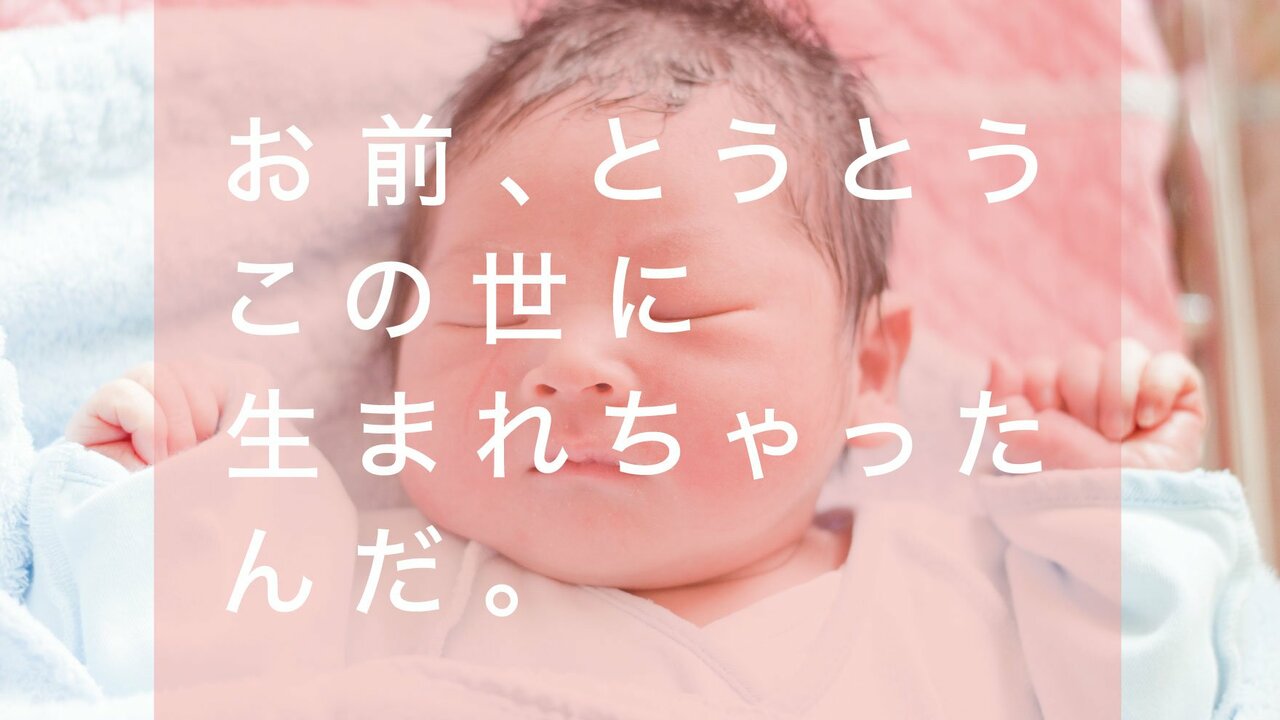『八汐の海』
僕は自分が何者かわからなかったが深刻には考えなかった。草太は生まれてくれただけでいいんだ。父が言ったんだもの。父は西洋美術史家だった。僕は小さい小さい自分を天使のようなものだと思っていた。
四人姉妹の弟だった。一番上の姉とは十五、すぐ上の姉とは三つ離れている。母は諦めないで男の子ができるまで頑張った。親父はそう言うが、親父の方が頑張ったかもしれない。僕が女の子だったらまだ頑張った? 誕生日を祝ってくれる度にそう訊いた。笑いの種だった。母はスリル満点だったわと誇らしげに言うのだった。
女たちに草ちゃん草ちゃんと猫可愛がりされた。二番目の姉は厳しくて、甘やかされて育ったらいい男にならないからねと脅した。それを実証した。
最後まで構ってくれたのはすぐ上の姉だった。形だけにしろ彼女は高校受験で僕は中学受験だった頃、まだいっしょに寝ていた。人には言えないが。親も咎めなかった。風呂には執着しなかったが、この姉が旅行なんかで留守になると、僕は姉のベッドに独りで寝て、優しさを楽しんだ。姉が僕のベッドに寝に来ることもあった。
僕は姉たちの生理を知っていたから、当然この姉のこともわかっていた。自分の性徴も気付くから、もう天使じゃなくなったと、寂しかった。晩熟も自乗倍だと二番目の姉が辛口だった。晩飯の時に、もういっしょに寝ないと言ったら、両親は自分で決められて偉いと言うんだ。その姉が、親莫迦のグランプリと。
確かに親莫迦には違いない。しかし、姉たちだって僕を近習に連れ歩きたくて重なると喧嘩したほどだ。
こんな年になって、姉たちの合わせて九人の姪や甥が思春期になっても、この叔父貴は姉たちが好きだ。義兄たちには悪いが。だが、義兄たちだって僕を贔屓してくれる。競って。妻の点数上げたいからだけじゃないだろう。特に二番目の義兄は。