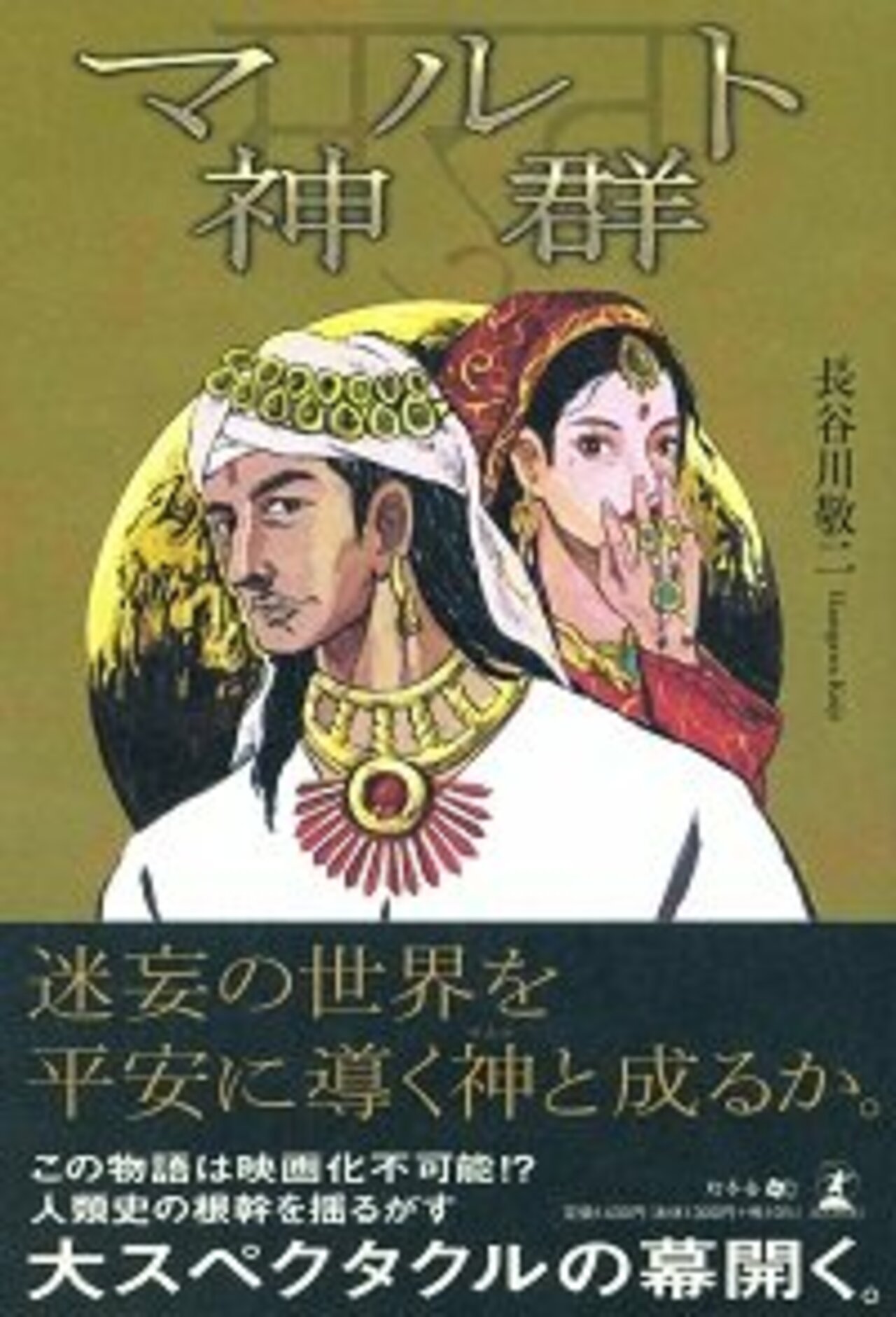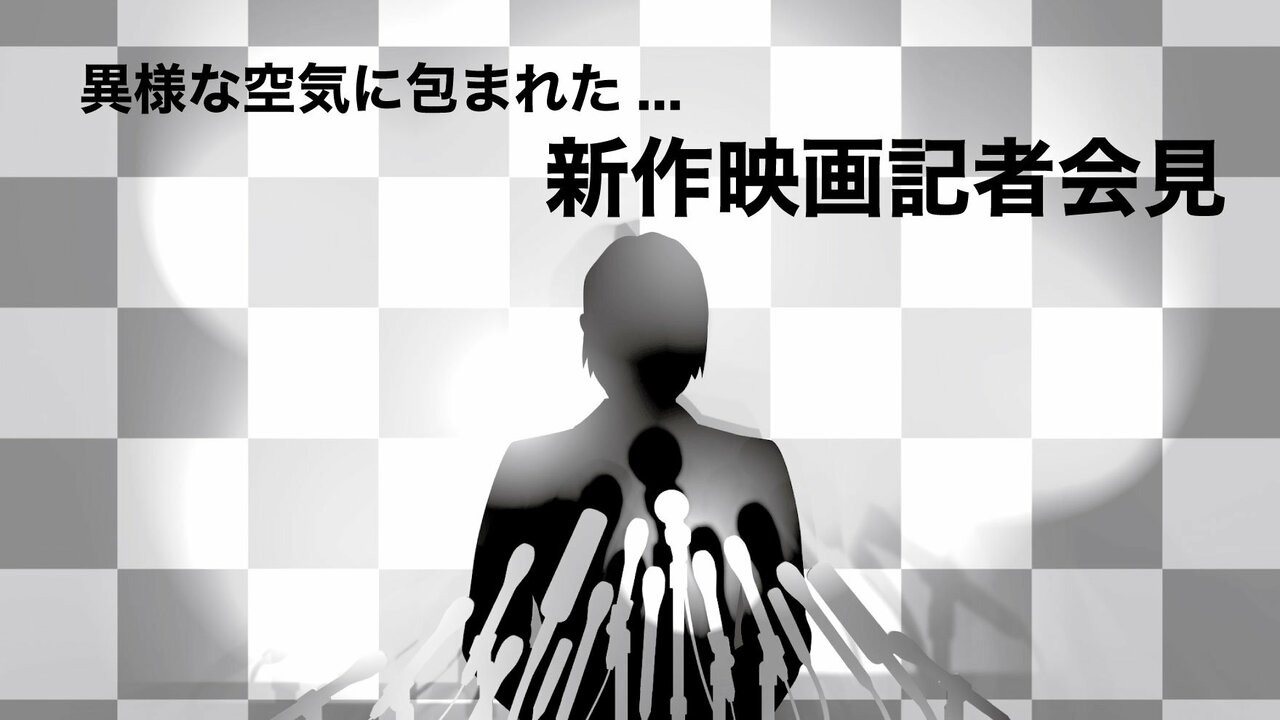「そうとっていただいても結構です。先ほど話に出ました宮市蓮台ですが、マルト神群の共通の恋人ローダシーの役を彼女に振り当てたところ、婆須槃頭君がひどく怒りまして、絶対に嫌だ、彼女がこの役をやるのなら自分は絶対に降りる、とひどい剣幕で怒るのです。
訳を聞いてみると、彼女をマルト達の恋人役にしてはあまりにご都合的すぎる、自分は彼女を体を張って保護する役目があるのだ、とこうです。やむを得ずインド女優をその役にあてがいましたが、撮影の始まった段階で彼女が脚を骨折するアクシデントが起こり、やはりということで蓮台にその役を振ったら、婆須槃頭君も、これは運命だな、と観念したように事態を受け入れました。
ローダシーは青年マルト達全体の共有されるべき恋人ではありますが、彼女がどういう女性でどうマルト達と関わっていったのか、さっぱり見えてこない。少なくともリグ・ヴェーダ賛歌からは伺い知ることができないのです。そうだ、あなた方はリグ・ヴェーダ賛歌を読まれたことがありますか? 読まれておられないなら話はこれ以上進まない、とお考え下さい」
急に会話の腰を折られて笹野は答えに窮したが、苦し紛れに、
「涯監督、私はインド文明に昔から只ならぬ好奇心を抱いてきた者です。インド人の根幹をなすヒンドゥー教、その最大の経典リグ・ヴェーダにも目を通しました。しかし、日本人の目からは何か吹っ切れぬものを感じてなりませんでした。登場するヴェーダの神々はインド人の現世利益を受け持つ存在のようにしか私には見えませんが、監督はどうお考えでしょうか」
「私にはそれにお答えする力はない。ただ、リグ・ヴェーダをひたすら読め、としか申しあげられようがない。映画『マルト神群』で私がマルト達に主人公の地位を与えたのは、今あなたの疑問に沿った私の答えだとお考え頂こう。マルトはその存在位置から十分にヴェーダの神々と渡り合い、批判し争いを起こし、また、人類と運命を共にしてゆく、実に好位置にいる、願ってもない個性集団なのです。映画の完成時にそのことがお分かりになると思います」ここで沈黙していた内山が口を開いた。
「映画雑誌記者として私がお聞きしたいのは、あくまで完成なさろうとしている今の映画についてですが、従来のインド映画の枠を打ち破ろうとするその意気込みについて涯監督にお伺いしたいと思います。いかがでしょうか」
「インド映画は今すごいスピードで様変わりしています。なんとなれば、世界のすべての諸相を飲み込んでどこへ行くのかさえも分からないほどの勢いで変化し続けているからです。私がインド映画を撮ることさえ一つの些末な事象に過ぎない。ここでお二人に先ほど述べた宮市蓮台嬢をじかにお引き合わせいたしましょう。彼女はすぐ間近に来ています。彼女を見れば私の言っていることの何分の一かの意味がお分かりになるでしょう」