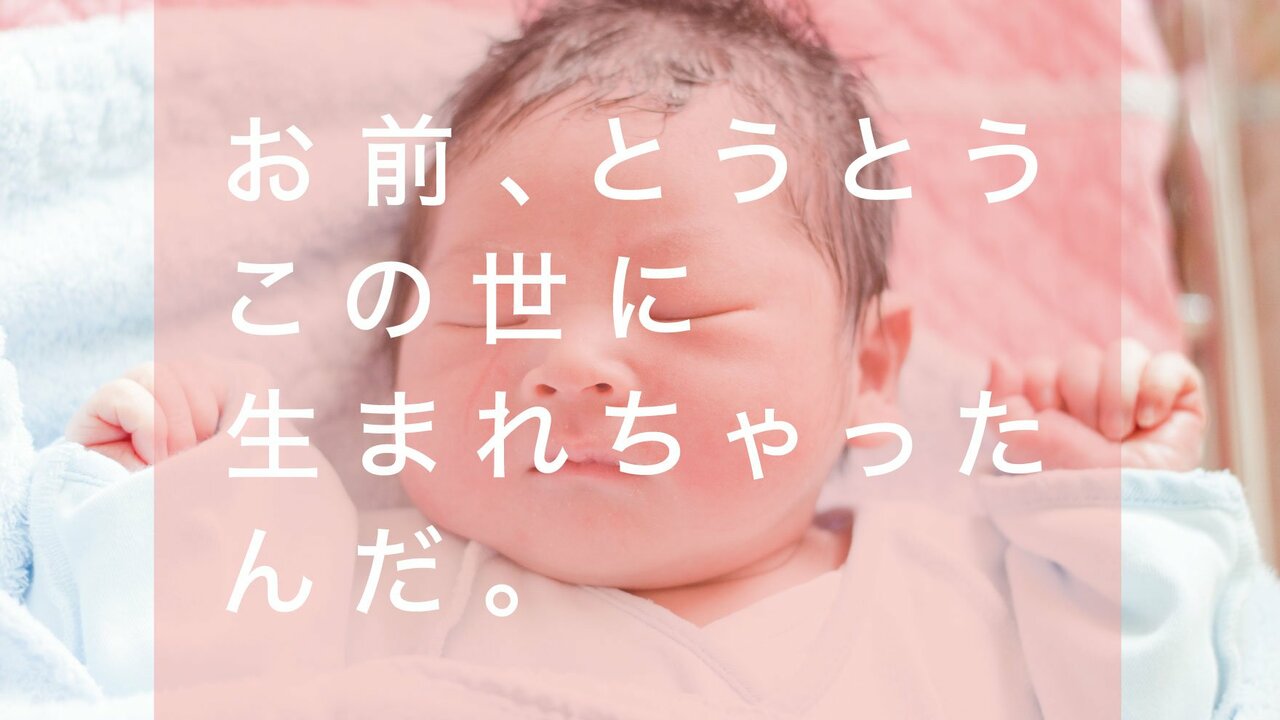目覚めは夢現である。仄明るい。肌寒さが躰の熱さを気付かせる。肌掛けを弄って身動きしようとすると先に肩まで引き上げられる。視ている昏い半眼が和らぐ。
「僕の、女房になって」
室町の母が言うには、お父さんの微笑が素敵なのは、口元がまっすぐなままなのね。
眠気は消し飛ぶがううーんと呻いて寝返ると、躰を越して反対側に来て、頬をそおっと叩きながら
「僕の、女房になって」
八汐の微笑は優しくて女性的だ。
「そういうのは……ちゃんと起きて……」
「うん……それから?」
「……服を着て……」
「うん……それから?」
「……口漱いで……」
「今日は日曜だ。一日中こうしている」
「……そういう眼の時は譫言しか言わない」
「あなたを思うときは、死ぬまでこういう眼だ」
八汐が躰を引き剥がして起き上がったのは「やっぱり腹減った」から。
シャワーに飛んでいく。淳もシャツだけ身に着けてシーツも肌掛けも全部洗濯機に入れる。カーテンを開ける。くらくらする日差し。昼を回っている。敷物のない床。ポスターや写真を重ね貼りした壁。大きいデスク。壁際に寄せてカンバスやスツールやイーゼル、多分。全部カバーで蔽っている。デスクの上は筆立て瓶や絵の具の箱や皿やバケツやノートパソコン。
枕の奥にあった小さいカンバスをベッドに腰かけて視ていたら、素裸で出てきた八汐が慌てて引ったくって
「ほら、さっさと流してこい」
シャワーに押し込む。
日焼けの他外見は変わらないと思う。鏡では乳首が膨らんだ。奥の方を、気を付けて流す。疼くのは腹の芯。触ってみられない。
さっぱりして戻ってみると、珈琲と、丸ごとの胡瓜とフランクフルト。
「これだけしかなかった」
「さっきの絵。わたしだった。見せて」
「あとで」
「絵を描くのね。ラ・ボエームやスーとジョンジーの部屋とそっくりだから」
「止めたんだ。絵描きになれなかったんだ。そんな大昔の……」
八汐は口を噤む。
「ちょっと外歩いてこよう」
荷物を持って出ようとするとポシェットだけ持たせて
「まだ帰せない」