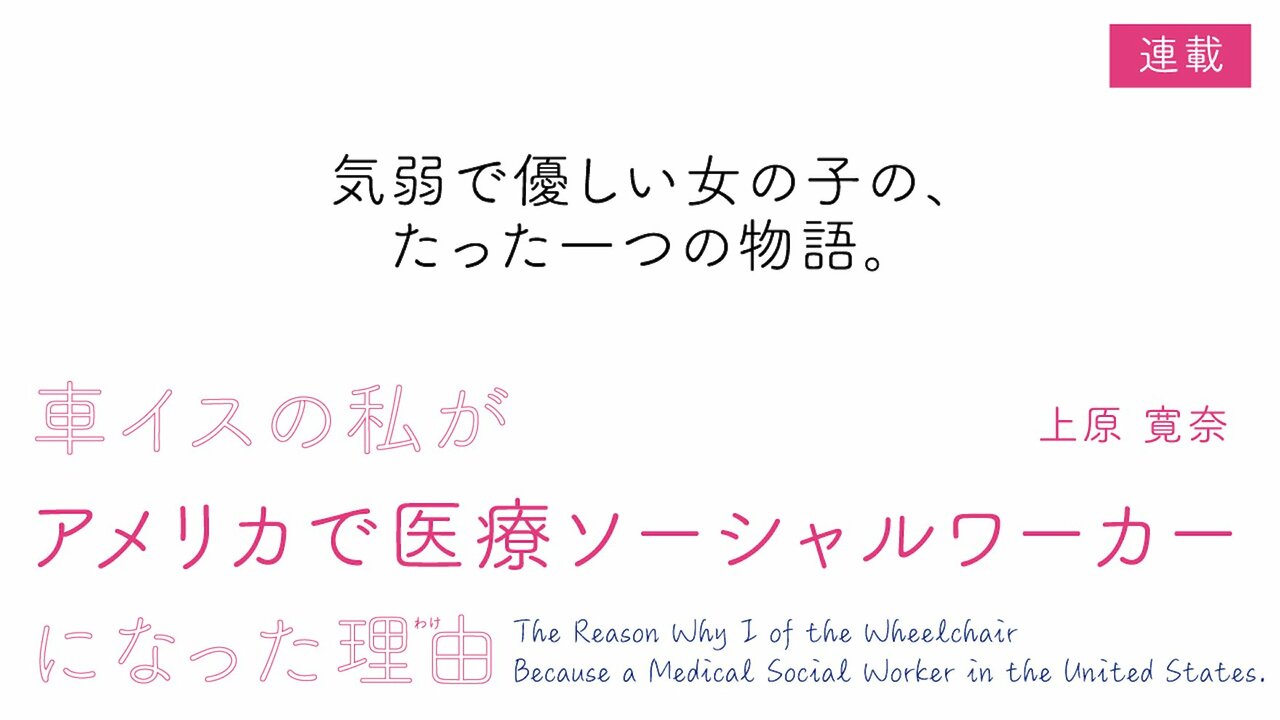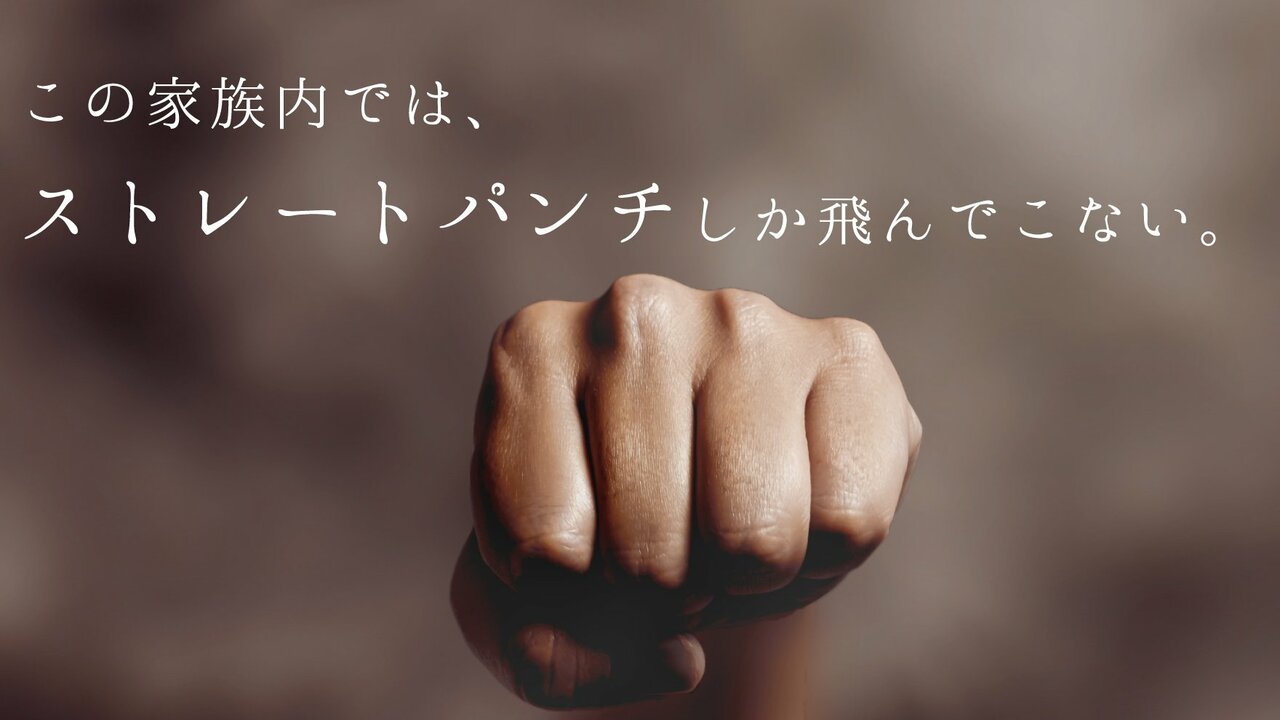5章 私の家族
私は六人家族、上原家の次女として生まれた。私が五歳の時に「若年性多関節リウマチ」を発症してからは、昔も今も家族全員ひとりひとりが私中心の生活になっている。
大阪警察病院と大阪大学附属病院に合わせて約五年間入院していた。私の耐えながら前進してきた努力は「さすが、カンナ様!」と今でも自画自賛している。
それは半分冗談とし、言うまでもなく家族のサポートなしでは、長きにわたる闘病生活を乗り越えられなかったと確信している。
警察病院と阪大病院入院中は、家族には本当に心配や迷惑をかけた。特に私が病気になった当初の父の困った悲しそうな顔や、母の疲れきった表情は、今でも覚えている。
そういう父と母を見るたびに、これ以上困らせないために、「泣かない強い子になるっ!」と決心した。両親に対してその効果があったのかは分からないが、良くも悪くも、私は、“頑張り屋さん”、“努力家” というイメージがついたみたいだ。
この頃から私は人の顔色をうかがう術を身につけたと思う。
上原家全員が、私を腫れものに触るような扱いは決してしなかった。今もそれは変わらない。ステロイドの副作用で太っていた頃は、“関取” と呼ばれていた。毛深い時は “ゴリラ” だった(もう少しひねりの効いたニックネームがよかった)。
白内障の手術後、私は牛乳瓶の底のような眼鏡をかけていた。姉と弟に初お披露目をした時、姉に「なにそれぇ~。恐竜みたいで気持ち悪い。こっち向かんといてー」と言われた。
弟は、その眼鏡を使って太陽の光を集めて黒い紙が焼けるかどうか試したいと言ってきた。弟は頭脳明晰で雑学王だ。今でも時々、うんちくレクチャーをしてくる。
この家族内では、ストレートパンチしか飛んでこない。今も逆にそれが私を救ってくれている。祖母は私たち姉弟をいつも褒めてくれ、面白くて笑顔の素敵な優しいお婆ちゃんだった。
前項にも述べたが、警察病院入院中は祖母が付き添ってくれた。入院中に祖母の暗い表情は見たことがない。退院後も私たちと一緒に暮し、働いていた母の代わりに面倒をみてくれていた。
ある日、私のおねだりで、料理番組で見た豚肉のチーズはさみ揚げを試行錯誤しながら作ってくれた。最高に美味しかった。姉と弟にも好評だった。
次はミートスパゲッティに挑戦してくれた。だが、なぜだが和風の味がした(笑)。
途中から祖母は一緒に住まなくなったが、私たちが会いに行くと食べきれないほどのご馳走で出迎えてくれた。よく話を聞いてくれる明るいホッとさせてくれるお婆ちゃんだった。祖母は二〇一七年の年の瀬に亡くなった。
父は仕事が忙しいのを理由に、私が入院中はあまりお見舞いには来なかった。きっと、父の少し弱い部分が私のしんどい姿を直視できなかったのだろう。それは現在も変わっていない。
父は、私がベストな環境でベストの治療を受けられるように一生懸命働いてくれた。それに加え、父は私に生きていく術を身に付けて欲しいと言いながらも、私がつまずかないように先回りして石橋を何度も叩いてくれている。
昔も今も、この矛盾は変わらない。私は父に過保護にされ愛されているのだ。
母はパワフルな厳しい人だ。警察病院で若年性多関節リウマチの症状が顕著に現れ始めた時、特に指の関節に痛みがあった。ご飯をスプーンで食べていたら、「箸を使いなさい、努力をおこたりなさんな」、「人の何倍もかかってもいいから」と。
阪大病院では、私は激しい関節痛に襲われ泣いていると、母が「泣きなさんな、泣いても痛みはようならへん」と喝を入れてくれた。阪大病院で三年間も付き添ってくれた母に感謝している。
後に話すが、私がアメリカ留学をしたいと言った時も、母が父を説得してくれたそうだ。母の優しさは厳しい。私の勝気なところは母譲りかもしれない。
私は姉と弟にも過保護にされ愛されている。阪大病院入院、私が外泊できない時は、二人はバスと電車を乗り継いで会いに来てくれていた。時々持ってきてくれるハンバーガーショップで一緒に食べるのが嬉しかった。
そして、二人の学校生活の話を、絵本を読むようにワクワクしながら聞いていた。
私の好きな話題は体育と給食の話だった。給食を食べられる二人が羨ましかった。私が一時退院していた頃、姉が人気メニューのマグロの竜田揚げを作ってくれた。あまりの美味しさに驚いた。
後にも先にも、この竜田揚げが私の食べた唯一の給食だった。
私は友達を一度も欲しいと思ったことがなかった。なぜなら姉と弟が友達だったからだ。