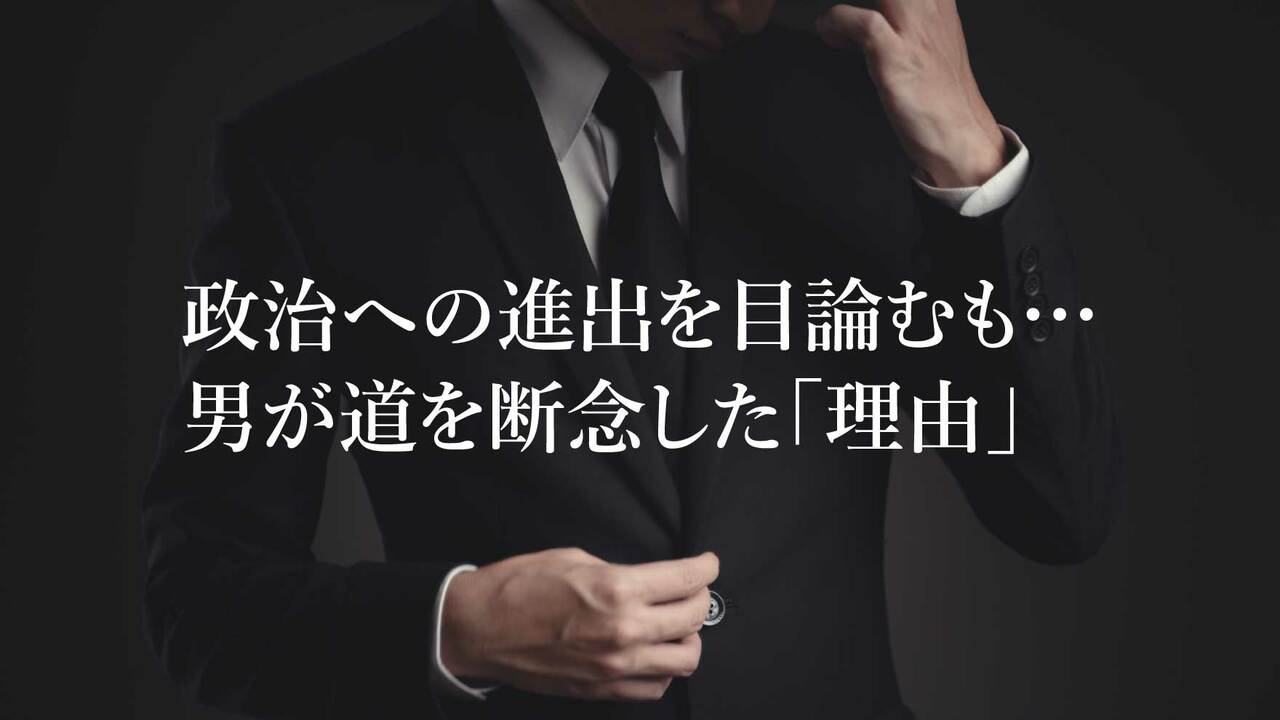Ⅱ
時代ごとに異なる政治や経済の動きというものがあるとすると、一九七〇年代末から八〇年代前半の頃には政治塾や経済セミナーなど、政界や財界の将来を託せる人材育成の私塾は揺籃期にあたりその数もそう多くなかった。
その当時はまだ理想主義に基づいて政治改革をめざし、経済や社会の問題に真剣に取り組もうと修業に励む塾生も結構いたようだ。その政治塾でも塾生たちが模擬の形で立案する政治理論や経済振興政策には、将来に向けてのビジョンを打ち出す内容のものも多かった。その当時は保守政党派のものであれ、革新派のものであれ、塾指導者たちのほうも好感をもってそのような政策や理論に含まれる理想主義を受け入れる余裕があった。
ところが八〇年代後半にバブル経済が破綻し、さらに二〇〇七年から八年にかけての金融危機(いわゆるリーマンショック)を経た後の時代には、理論上のこととはいえ将来の展望などを加味して日本の政治や経済の動向を見極めたいという意欲を持つ塾生達は徐々に少なくなり、現実路線に転向していくようになっていった。
来栖は既に入塾初年度に二宮守と塾の運営方針の是非を巡って議論を闘わせたことがあった。対立関係がはっきりしたのは日本の対外向け経済振興政策の立案で、互いの考え方が根本的に違うということがわかってからである。彼が守の紹介で入塾したのは二〇〇九年の秋で、紹介者のほうは春から在籍していたので、先輩後輩とはいうものの同年度の入塾だった。
彼らが入塾した直前に世界の先進国で起こったリーマンショック以降、労働市場では非正規の労働者がブルーカラー、さらにはホワイトカラーの階層に至るまで増え続けていく時代となり、その傾向は現在まで続いている。
いかに経済を立て直し雇用形態を改善していくかということで、塾では勉強会が開かれた。共同討論ではまず所得格差と、矛盾に満ち複雑多岐になりすぎた雇用形態の問題とを解決しなければ経済は上向きに転じないとの意見を述べたのが来栖で、守のほうは国の経済政策を擁護する意見を繰り返し述べていた。
守にはよく言って大局的な見地に基づき自身の考えを導き出す傾向があったが、対して雇用形態の不備やほころびそのものが経済停滞の元凶で、これを解決しなければ生産性も高まらず、経済効果を生み出せないというのが来栖の改善案だった。
これは同時に彼の時代状況の診断でもあった。後になって彼は大局的見地に立って判断を下せないところは短所であり、それに対し喫緊の問題の解決をめざす方向を定められるところは長所になるのではないかと考えるようになった。自らの政治的資質を客観的に捉える契機となったのがこの頃の守との論争だった。