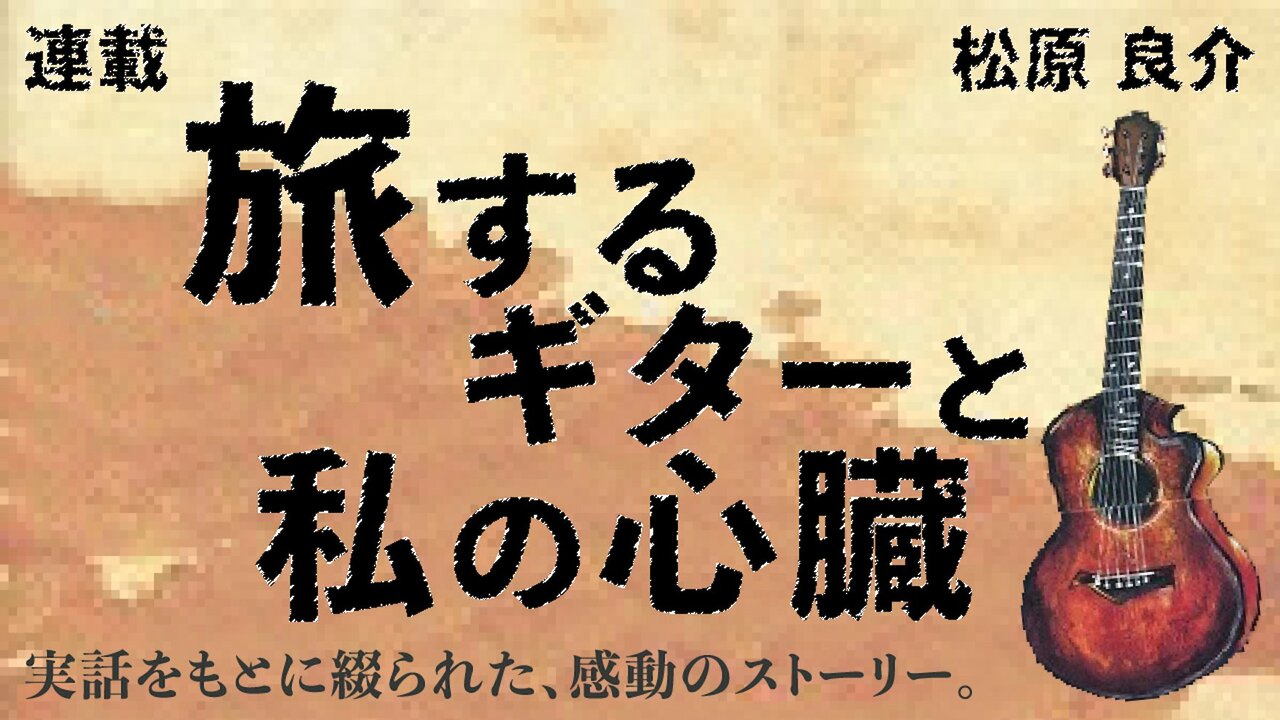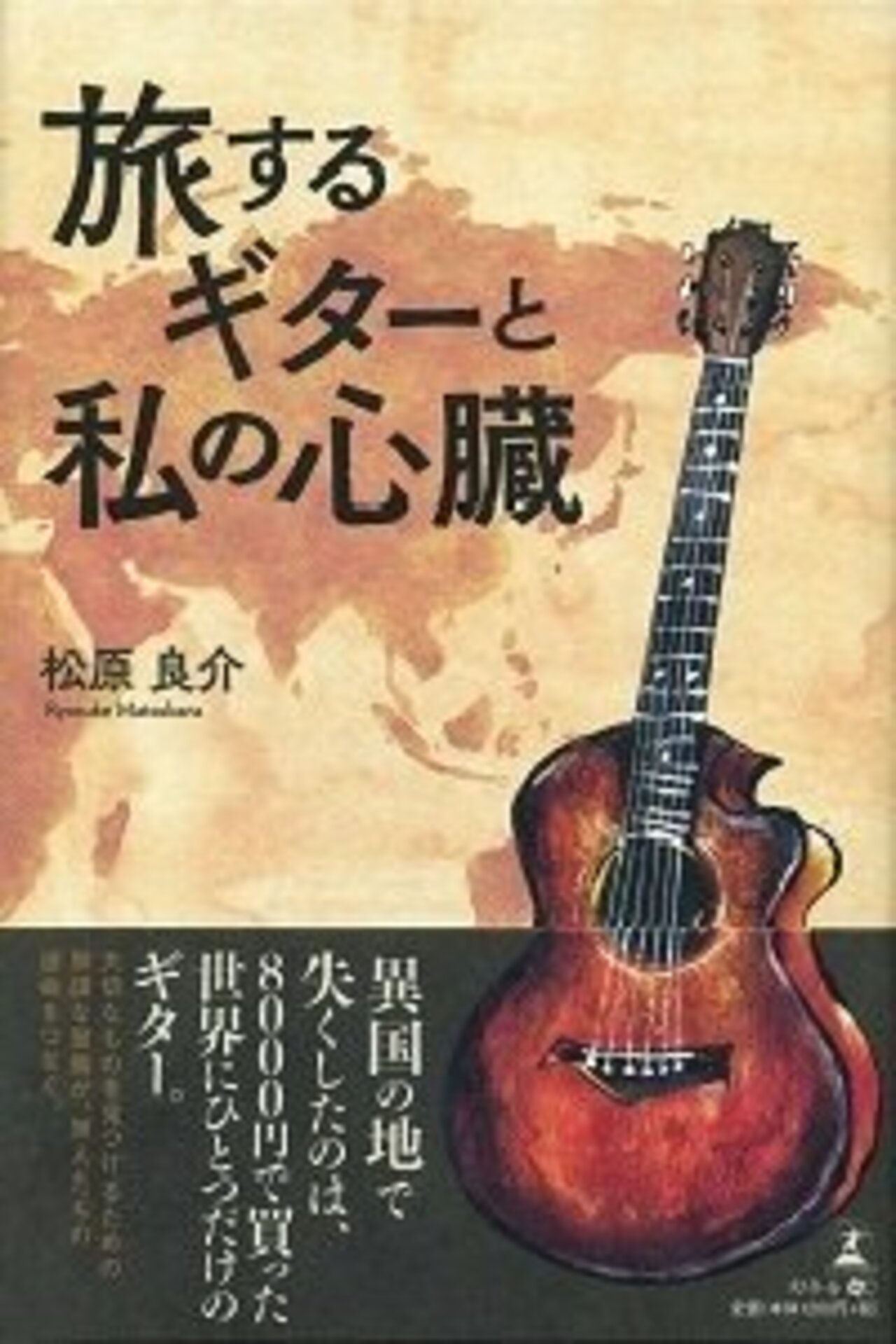〈野崎哲也の事情〉最悪の日
すべては私(野崎哲也)の思惑通りに進んでいた。いや、それ以上と言っていい。
駅前に構えた私の音楽教室には老若男女の生徒たちが集まり、数ヵ月先まで予約はびっしりだった。スタッフ同士の雰囲気もいいし、今のところこれと言ったクレームもない。自分でも怖いくらい完ぺきだった。何より、気心知れた昔からの友人である祐介を講師として招くことができたのは嬉しい誤算だった。
祐介には申しわけないが、彼の勤めていた会社の経営が危ういという噂を耳にしたときから彼を引き入れる算段をしていた。誰とでも器用に接することができる祐介が、この教室でレッスンする様子が私にはイメージできた。何より彼の人を惹きつける得体のしれない能力が、ここでどう発揮されるのか私自身見てみたかった。
祐介を講師として招きたかった理由はほかにもあった。
彼は昨年、6年連れ添った妻と離婚した。
2歳年上の彼の妻は知的で美しい女性だった。
ハワイで行われた身内だけの挙式には私も参列した。海外での挙式にもかかわらず多くの友人が訪れ、二人の人望の厚さがうかがえた。
二人の間に子供はいなかった。それでも外から見ていた私にとって彼らの生活は十分幸せそうに見えた。
しかし、仕事を独立させ、子供を作って家庭を築きたいという理想を持っていた祐介と、積み上げてきたキャリアを捨てず仕事を続けたいという妻との間ですれ違いが起こっていることを彼から聞かされ、すでに二人の間に修復できないほどの溝ができていることを知った。
二人は逃げるように仕事に没頭し、はじめは相談に乗っていた友人たちも次第に彼らから遠のいていった。
誰かが悪いことをしたわけではない。
しかし結果的に独りになった祐介はどん底にいた。離婚後はまるで抜け殻のようになってしまい、それに追い打ちをかけるように勤め先の会社の経営も傾いた。かつての生き生きとしていた祐介の姿を知る私にとって、目標もなく生きる彼の姿は見るに堪えなかった。
立ち上げたばかりの教室で大した給料を払えるわけでもなく、来てくれる確信もなかったが、ダメもとで祐介を誘ってみた。すると始めは渋っていたものの、彼が最終的に承諾してくれたときの喜びは表現しがたいものがあった。
「1ヵ月だけだからな」
そう言っていた祐介が、ここで働き始めてもうすぐ3ヵ月になろうとしていた。
2012年9月4日。
その日は火曜日で教室は休みだったが、午前中だけエアコンのある事務所で残務を行うのが日課だった。おそらく祐介もそろそろ来る頃だ。
私は事務所に来る途中で買ったドーナツとコーヒーの容器を紙袋から出して机に並べた。
アイスコーヒーが入ったプラスチック容器の蓋を外して一口飲むと、コーヒーの酸味が口に広がる。酸味を十分に楽しんだところでミルクを入れる。かき混ぜない。砂糖は入れない。この飲み方は私に影響を与えたミュージシャンがやっていた飲み方で、なんとなく真似をしていたところ、いつの間にか癖のようになった。今ではこの飲み方が一番おいしいと思っている。
薄くBGMをかけて、大きく椅子に寄り掛かった。
この日は朝から体調がすぐれなかった。
昨夜久しぶりに大谷と飲みに行ったが、それほど酒を飲んだわけでもなかった。
東京の大学に進んだ大谷は、今は都内のライブハウスで働いている。非常勤講師としてスカウトしてみたが、『いつかそんなことになったら面白いな』と笑ってごまかされた。昔は彼を毛嫌いしていたが、一緒に音楽をやるようになってからは仲が良く、大人になった今では一緒に仕事をしたいと思うまでになった。
大谷は付き合ったばかりの年下の彼女にフラれたらしく、まだ飲み足りなさそうな顔をしていたが、酒癖の悪いあいつに付き合っていたら、今頃もっと体調が悪くなっていたことだろう。
私は机の上のドーナツに手を伸ばした。一口それを口にすると、シナモンの香りが鼻を通った。机に肘をついて大きくため息を漏らしながら、頭が重く気だるいのを感じていた。
それからしばらくしてエアコンで室内が冷やされてきた頃、左手に違和感を感じた。指先がしびれているようで感覚がほとんどない。私は椅子に腰かけたまま顔を横に向けると、扉の開いた応接室に来客用のソファが見えた。終電を逃すと、このソファで良く寝ている。棚にはブランケットも入っている。
(やれやれ、風邪でもひいたか)
そう思いながら、ソファに身体を移そうと椅子から腰を上げたときだった。まるで胸の奥を直接鈍器で殴られたような強い衝撃が身体をめぐり、ナイフでえぐられるような痛みが襲った。
声が出せないどころか、呼吸すらできないほどの痛み。開けた口を閉じることができず、動悸が激しくなった胸を押さえながら、逃げるようにしてその場にうずくまった。額からは今まで流したことのない類の汗がジワリと湧き出した。
私は呼吸を整えようとしながら、冷静になるよう必死に努めた。しかし、不規則に襲ってくる胸の痛みはおさまることがなく、そのまま床に転がりこんでしまった。私は自分の身体にただならぬことが起こっていることを理解し、何とか楽になる姿勢を模索した。
震えていた手は鉛のように重たくなり、身体を起こすこともできない。それでもなんとか身を起こして、机の上にあるスマホに手を伸ばした。しかし、ようやく手にしたスマホも指先に力が入らず、あっさりと手からすり抜けてしまう。
バランスを崩して再び床に倒れこむと、その勢いで机の上の資料や譜面が、あたり一面にぶちまけられた。やがてとてつもない睡魔が襲ってきた。意識が遠くなっていくのを振り払いながら、譜面が散乱した床の上を這いずり、事務所の入り口へ向かった。
入り口まで行ったところで、この状態ではドアノブに手をかけることすらできないだろう、と思ったが、とにかくあがくことにした。
どれくらい時間が経っただろう。今いるのが夢のなかなのか、現実なのかはわからなかったが、どこからか懐かしい声が聞こえた。やかましく耳の横で声を上げている。
薄れた意識のなかで、本当にこいつは予定がない男だとつくづく思った。