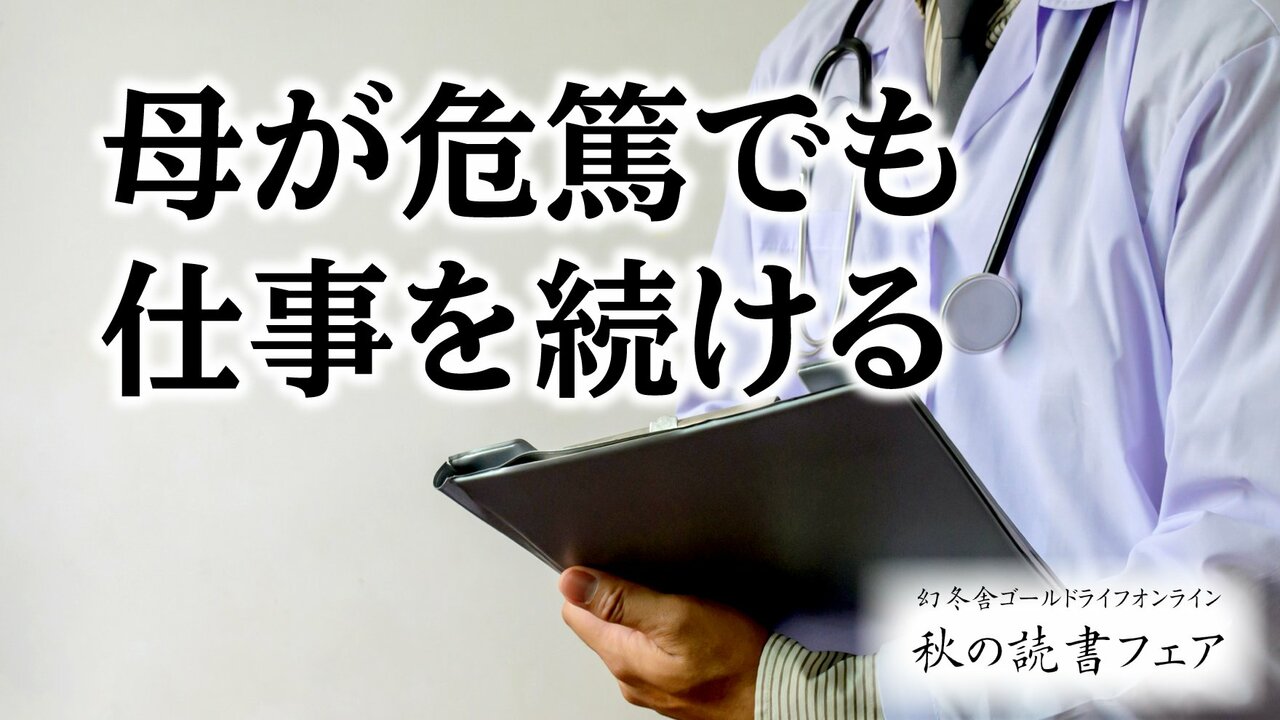「俺のせいなんだ」
母が危篤となった翌日。わたしは通常どおり外来診療をこなしていた。母のところには、わたしの代わりに多恵と陽菜を向かわせた。陽菜はわたしの母である祖母が大好きだ。
母に抱きかかえられるのを特に気に入っており、同居していた頃はいつも「おばあちゃん、抱っこして」とせがんだものだ。母はそんな陽菜をそれはそれは可愛がり、眼に入れても痛くないというように甘やかした。幼稚園の送り迎えは母の日課で、わたしが陽菜を叱りつけるときに真っ先に逃げ込む駆け込み寺は、いつも母の部屋だった。
「陽菜ちゃんは悪くない。諌が悪い」
そうやって言いくるめられると、なにも言えなくなってしまう。だが母からの愛情を受けてすくすく育つ陽菜を見るにつけ、かつての自分もそんなふうに成長したのだと懐かしくもあった。母はいくら月日が流れて季節が移ろいでも、母だった。
だがわたしは。わたしは果たして、良い息子であり続けられただろうか。滲む視界が曇らないように、カルテを睨む眼を細める。
七歳の娘にとって、初めての死別になる。さぞつらい体験になるだろうが、強くなって欲しい。受け入れがたいけれど、人はいつか死を迎える。それは避けられない道なんだ。わたしの愛する母だからこそ、愛娘の陽菜に立ち会って欲しかった。なぜならその人は。わたしの、世界でたったひとりの、かけがえのない母だから。
目頭に熱いものが込みあげながらも、紙カルテの文字の羅列で紛らわせる。まわりのスタッフも事情を察しているのか、わたしにつとめて明るくふる舞った。ここは優しい世界だ。そのぬるま湯のなかで、果たすべき医師としての役目を果たそうとした。
ただ唯一、そんな世界には染まらない、空気の読めない男がいた。そいつは外来の合間をぬって、医療スタッフ専用の扉からわたしの診察室に割り込んできた。