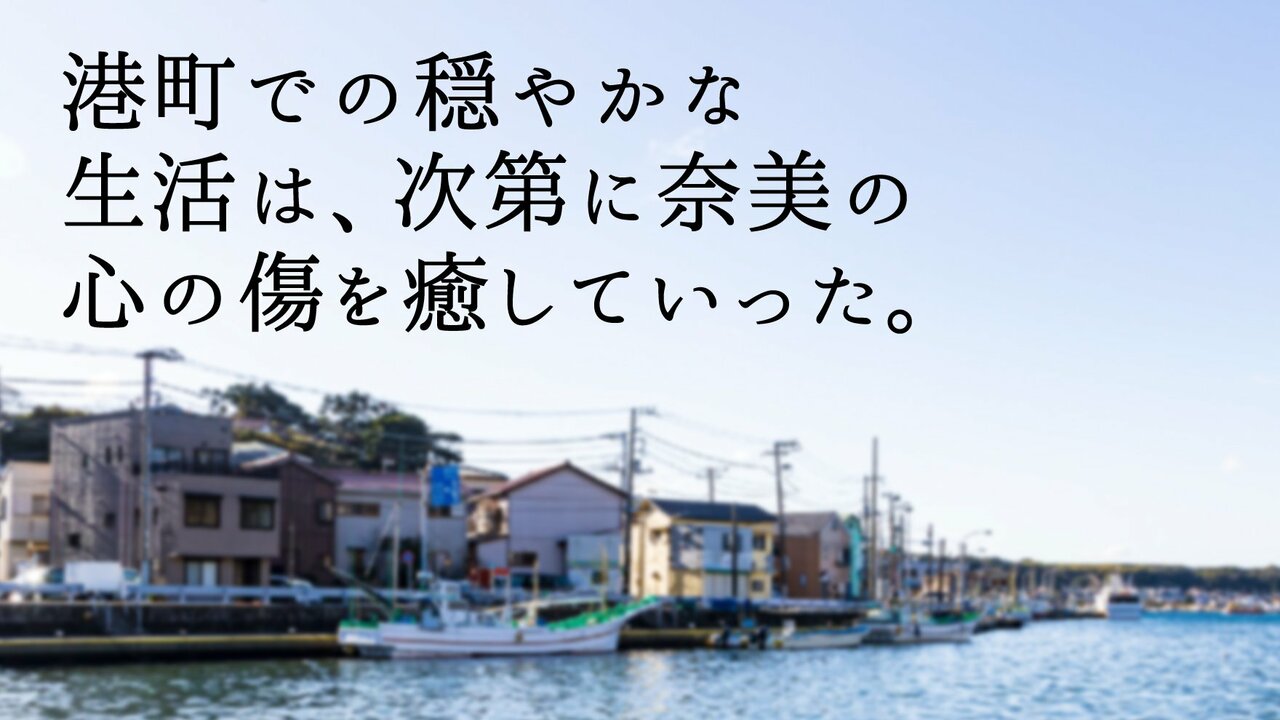第二章 拾って来た女
そんな沙耶は、午後四時に水産会社の仕事を終えると車で五、六分も走れば家に着くが途中でスーパーマーケットに立ち寄り夕食の食材を買う。
家に着くと掃除と洗濯を手早く済ます。午後五時を少し回り漁火への出勤まであと二時間足らずとなると夕食を作り始める。
台所で夕食の準備をする沙耶の傍に立ち、母はまるで小さな子が母親のしぐさを眺めるように手際よく包丁を動かす沙耶の手元を黙って見詰めている。
母の好みを考えて作った夕食を台所のテーブルに並べる。母を促し父親と一緒にテーブルに着かす。何が気に入らないのか母は夫を睨むようにしてぶつぶつと何かを言っている。沙耶はそんな母の態度にもすっかり慣れ、今は気にも留めない。
母は「食事はもう終わり」と周りが注意をしないといつまでも箸を置かなかった。父親がその役割を担っていた。
自分の夕食も一緒に済ますと後片づけをし、少し濃い目の化粧をして漁火に出掛けて行くのが日課であった。漁火の仕事は、夜は遅いが果てることのない両親の介護から解放される時間であり、体にはきついものがあったが気分的には嫌ではなかった。
沙耶は、漁火では康代ともよく話をするが、康代の子育てをしている苦労と私の苦労はわけが違うとよく嘆いた。子は何れ親を捨てて巣立つかもしれないが、子育ては手が掛かってもまだ未来という望みがある。
しかし、老いた両親の目処のつかない介護には何の望みも無いと言うのだ。認知症が進み、母親はどれだけ世話をしても、もう優しい言葉など返してくれることは無い。
介護に疲れると何もかも放り出して逃げたくなるが、体が弱り伏せたり起きたりを繰り返す父親の「いつも済まんな」との言葉に残った僅かな気の張りを引き摺り出し、その場の疲れを体の芯に押し込める気持ちがわかりますかとも語った。
しかし、沙耶が奈美に話す認知症の母親の話は愚痴とは違い、昔のことはよく喋るし、よく覚えている。少し怒りっぽいが小さい駄々っ子みたいよと娘と母親の立場が逆転したような話ぶりで楽しそうなのであった。
「大変ですね」
奈美は二人からそんな話を聞く度にそう言った。
「人生ってね、くよくよしても始まらないの。なるようにしかならないからね」
申し合わせたように二人からはそんな答えが返って来るのだった。誰も恨まず誰も憎まずただ天に召されるまで命がある限り精一杯生きる。
漁火の二人のホステスはそんな風な生き方しかできないと話の端々で嘆いて見せるが、奈美には羨ましい限りの生き方のように思えるのだった。