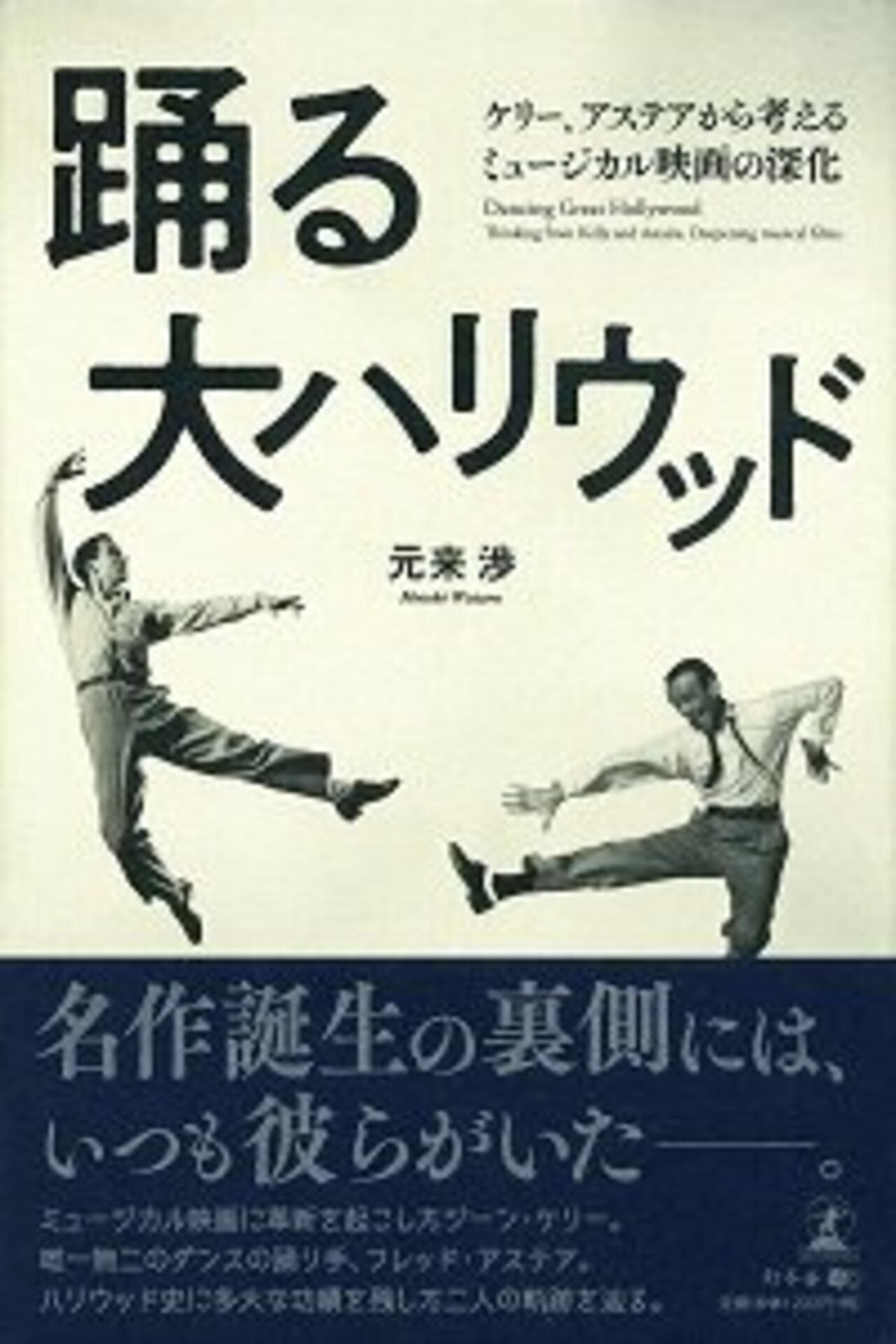続いてパウエルの持ち馬を障害レースに出すための訓練シーン。チャールズ・イゴル・ゴリンが今度は歌劇「セビリアの理髪師」から“私は町の何でも屋”を歌うが、これもストーリーとの関連はない。終いには馬の訓練のバックグラウンド・ミュージックになってしまう。ここでとってつけたように挿入されるのが、ジュディ・ガーランドがクラーク・ゲーブルへの憧れを歌う“恋をしたのはあなたのせいよ” 。思春期の彼女を代表するパフォーマンスとして有名なシーンだが、ストーリーとは全く関連がない。
フィナーレは約十二分間の舞台場面。パウエルとマーフィーのダンス、イプセンとガーランドのタップ、タッカーの歌と続き、最後はパウエルの見事なタップで締める。
芸自体はどれも素晴らしいが、撮影はほとんど舞台正面に据えられたカメラで行われ、画面から躍動感を感じることはない。舞台上の動きも奥の階段を使って多少変化を出すが、あとは背景を工夫しているに過ぎない。
いくら例を挙げてもきりがないので、比較の対象はこれぐらいにしておきたい。上記の例からわかるように、一般的にこの頃のミュージカル映画では挿入される歌やダンスと物語の展開との間に関連性が乏しく、ましてや登場人物の心理を掘り下げることなど考慮されていない。あくまでナンバーや芸自体を見せることを主眼においている。
さらにスタジオが推している俳優や見せたい芸のシーンを挿入するため、物語の進行は止まり、テンポは落ちる。ドラマの部分の撮影は、フルショットからクロースアップまでを必要に応じて使い分けながら、人物を正面から固定して撮っている。観客にとって非常に安定感がありわかりやすいが、その反面、映画の流れにリズムが欠けどうしても平板になりがちである。