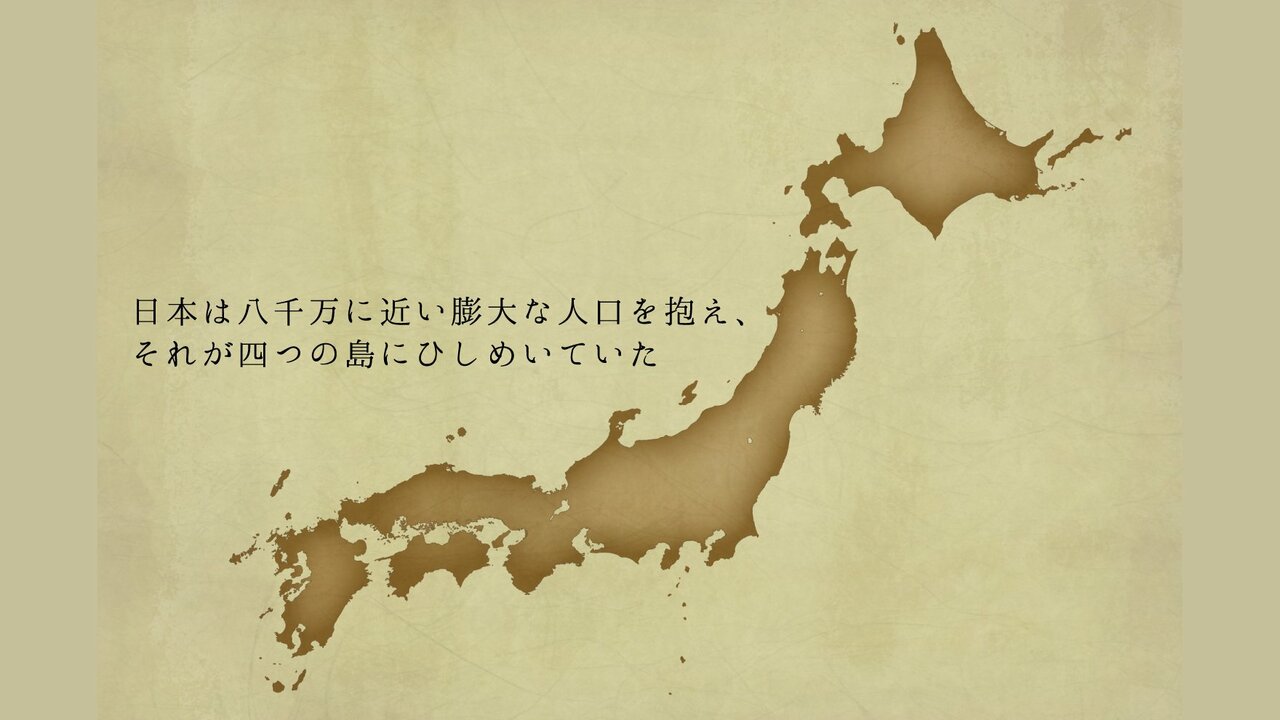第二章 破 絶歌
「この世の学者、利根川 進」を聖書から糺す
一九八七年ノーベル医学生理学賞を受賞。論文のタイトルは『抗体の多様性生成の遺伝的原理の解明』だそうです。選考にあたったスウェーデンのカロリンスカ研究所によれば一〇〇年に一度の大研究と絶賛です。
では、進化論を信奉する分子生物学の学者である「この世の学者」は結果として、その人の思想からどのような信条と行動が演繹されるのか、帰納的に検証してみたいと思います。論拠は利根川 進・立花 隆 共著、文藝春秋刊の『精神と物質』です。
曰く「大発見の前には山のような間違いの積み重ねがある。どこで間違うかというと、大きくいって二つある。実験科学の研究というのは、みんなまず仮説をたてて、それを実験で検証していくわけですね。
こうなってるんじゃないかなと考えて、本当にそうなっているかどうかを調べる。その最初の仮説のたて方で間違う可能性がある。これがいちばん大きい。
次に、検証の方法で間違うことがある。こちらは失敗してもやり直しがきくけど、はじめの仮説で間違ったら、もうどうしようもない。はじめにこうなってるんじゃないかと考えたときに間違った方向で考えていたら、あとはどんな実験をやっても無意味ですよ。いくらやっても意味あるデータがでてこない。
だけど、はじめに間違った方向に頭がこりかたまっていると、それでも、これは仮説のたて方が誤っていたんだということに気がつかないで、実験の方法が悪かったんだと思いこんで、方法だけ変えて別の実験をしたりする。(中略)結局、ないものをいくら一生懸命探しても、絶対ないんですよ。(中略)結局、運とセンスだろうね、ぼくもラッキーですよ」(七六~七七頁)。然り、その通りです。
利根川博士は実験科学における間違いの可能性に関し、二つの視点から述べました。それが仮説と検証です。科学者は研究の前に仮説という形であるアイデアを立てて、自らの進むべき方向性を自律的に決定します。
それは言ってみれば「思い」つきであって、科学ではありません。つまり「こうなってるんじゃないかな」という仮説の下に、次に「本当にそうなっているかどうか」を検証する作業があり、そこからが科学です。彼は二つの場面における間違いの可能性を指摘したのです。
分子生物学というジャンルは始まったばかりの研究分野だそうです。それは「生き物」そのもの、あるいは「生きている」という事実、そのことを物質レベルに還元して「命」というものを解明し、解釈しようとする分野です。
ですから、医学とか生物学、即ち科学と言うよりはむしろ哲学に分類されるべき範疇ではなかったでしょうか。当人は根っからの進化論者ですから創造主には興味もありません。目的論的発想は単なる宗教でしかないと割り切ってしまった科学万能主義の信者です。
彼にとっての「命」とは単なる物質代謝と運動にすぎない研究「材料」でしかありません。彼の知性には命に対する畏敬というものは寸毫も感じられません。ですから結論である本音を、彼は語り始めるのです。