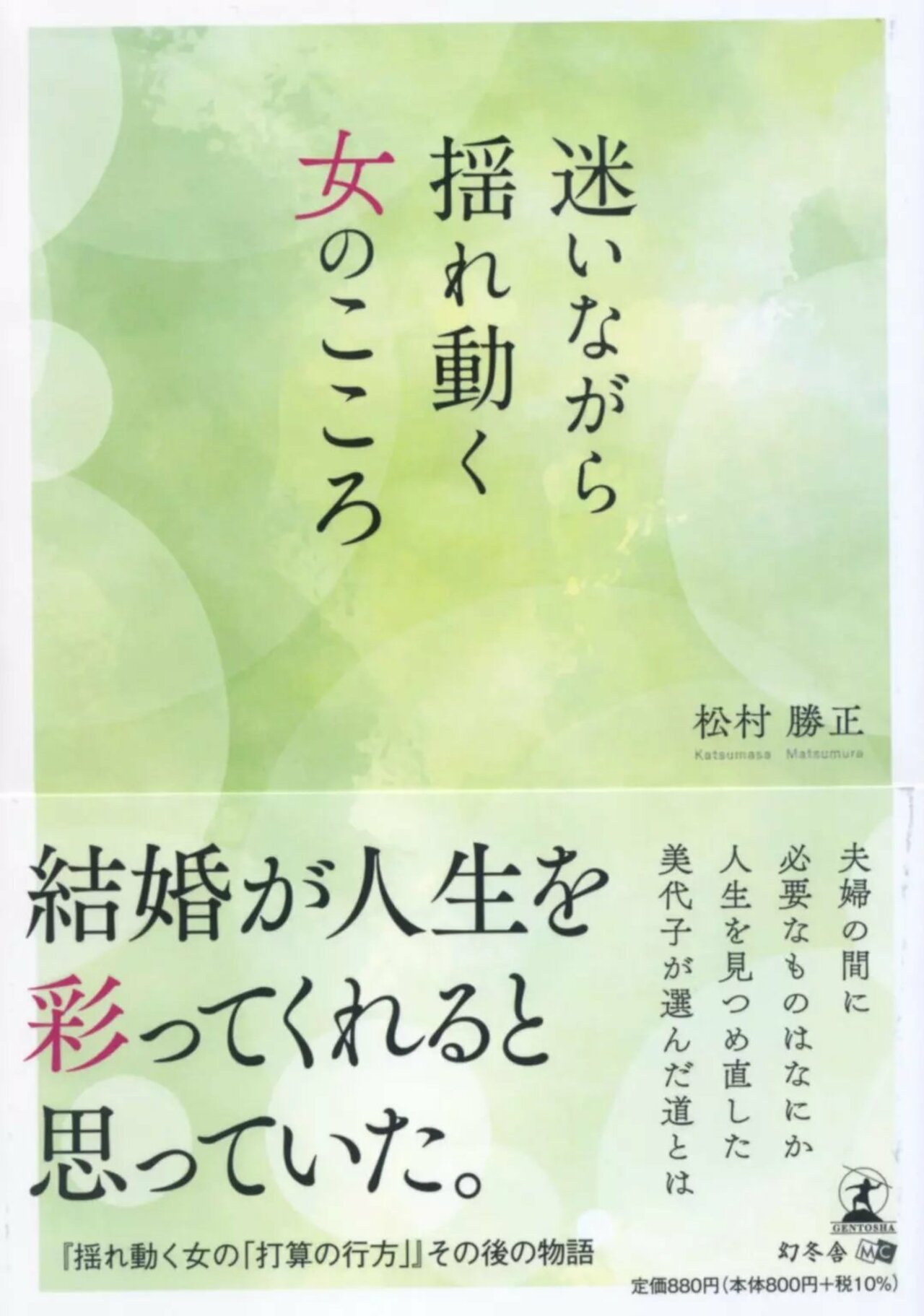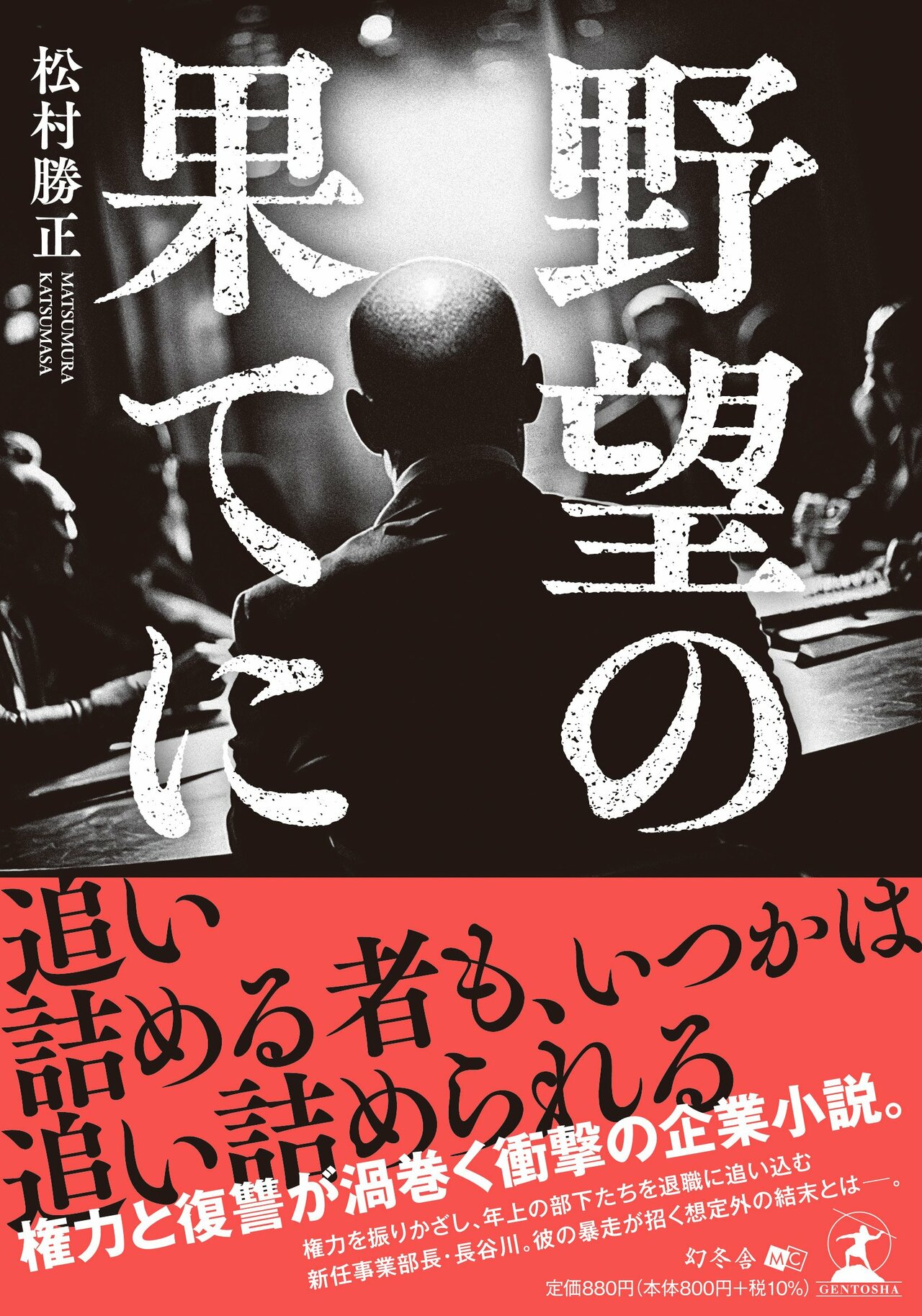「うそでしょう、私だけ何も知らなかったのね」
「本当よ、貴女も誰かを好きになっても近視眼的になり盲目にならないことよ」
「私は、もうすぐゴールインするとばかり思っていた」
「詳しいことは、今度お話しするわ、今日は御苦労さま、早く帰って頂戴」
「お茶も出ないのね」
「そうよ、お客様じゃないからね」
「私は、英国の美味しい紅茶のサービス期待して来たのに」
「そうだったの、気が付かないでごめんね、少し待ってて」
美代子はそう言い残して席を立った。そしてすぐ戻ってきた。
「今、特別に頼んできたから、少し待っていて、ところで英子の会社は情報通信系の会社と言っていたね、そして貴女は映像クリエーターの仕事をしているのでしょう、なんだか難しそうね」
「簡単に言うとビデオの編集の仕事で、映画会社やTV局そして新聞社が相手になるお客様、ということ。だから相手の会社業務時間にこちらもある程度ペースを合わせなければならないから家に帰るのがどうしても遅くなるの」
「だったらお給料いっぱいもらえるでしょう」
「そうでもないの、残業は付かなくて労働裁量性だから、過重労働だよね」
ノックがありドアが開いた。途端に香りが会議室いっぱいに広がった。テーブルに置かれたのはミントンの花柄のハドンホールのカップに入れられた香り高いオレンジペコーのアールグレイだった。
「お姉さんありがとう、この紅茶の香りがよくて大好き」
「良かったわね、飲み干したら帰って」