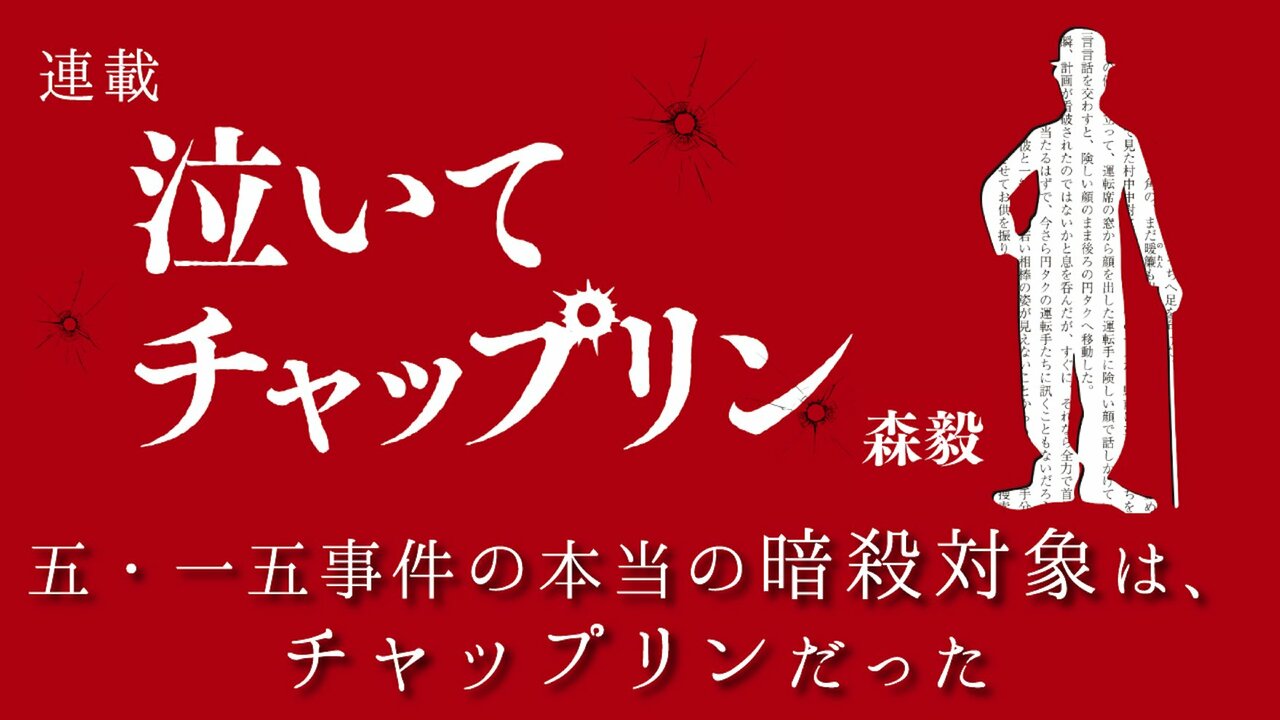フォードは悲鳴を上げて止まった。
木坂は転げ込むようにそれに乗り込み、
「あの円タクを追ってくれ」
と、前部シートに身を乗りだして、三、四十メートル先の、遠ざかってゆくシボレーを指差した。
分かりました、と若い運転手は、瞬時に何事かを察したようにニヤリと笑った。そして、その自信ありげな言葉どおり、付かず離れず一定の間隔をたもって、その後を追った。
先を行くシボレーは、そのまま真っ直ぐ坂を下り、谷底の省線渋谷駅を左に見て、通称「花の円山町」に到る、色とりどりのイルミネーションや、赤提灯に彩られた道玄坂を駆け上がった。が、盛り場の灯(ひ)もその辺りまでで、シボレーの黒い車体は夜の闇に溶け込み、それから先は、さらに深まる漆黒の闇に浮遊する、赤いテールランプだけが頼りだった。
ほどなく、東京市の郊外をぐるりと一周する環状道路の整備拡張工事が急がれている、通称「山の手通り」の交差点を右折した。そして、いまだ武蔵野の面影をわずかながらも留めている雑木林を切り拓いて建てられていく、いわゆる「文化住宅」の団地を右に左に見ながら走ること、およそ二十分。シボレーは鉄道の踏切の遮断機で止められた。
踏切警手が振っている赤色灯を見て、それを事前に読んでいた運転手は、シボレーとの間隔をたもったまま、車を道路の左端に寄せて停め、ライトも消した。若いながらも口数もすくなく、円タクの運転手にしておくのは惜しいような男だ、と、木坂も感心しながら訊いた。
「あの踏切は?」
「中央線と京王電車の、《初台(はつだい)踏切》ですね」
「すると、淀橋の近くだね」
「ええ、淀橋は、この先の青梅街道の、中野坂上(なかのさかうえ)の交差点を右折して、新宿方面へ一キロほど行ったところです」
木坂は、途中から予想していた通り、田島中尉が自宅へ帰ることを確信した。東京郊外の新興住宅地へ向かう満員の京王電車が通過し、遮断機が上がり、シボレーは住宅の密度が次第にましていく街中にはいった。
予想通り中野坂上の交差点を右折した。木坂は、運転手にスピードを落とすよう命じ、そして、頃合を計ってその交差点を右折した。
どんぴしゃりのタイミングだった。神田上水に架る淀橋の手前で、田島中尉を降ろしたシボレーは、今まさに走り去っていくところだった。
田島中尉は通りを横断し、そのまま真っ直ぐ横丁の暗い路地に消えた。
木坂も路地の入り口の手前で円タクを捨て、その曲がり角へゆっくりと足を運んだ。谷口と桜木の二人のことだから、まだ粘っているにちがいないと思ったからであったが、案の定、路地から小走りに出てきた二人と、鉢合わせになった。
「あれっ、主任……」
と、桜木が目を剝いた。谷口とて驚かないはずはなかったが、すぐに事情を察したようにいった。
「やはり主任の読み通りだったというわけですか?」
「いや、そっちは外れたが、運が良かったのか悪かったのか、中尉さんが思わぬ所で降って湧いたんで、ご挨拶するヒマもなかったよ」
と、木坂は苦笑した。
「ということは、丸っきり見当違いではなかったというわけですね」
「まあ、怪我の功名といったところだな。それより、中尉さんの家はどうだった?」
「は、これといったことは何一つありませんでした。それで三十分ばかり前に、一度、そこの酒屋から主任のご自宅に電話を入れたんですが、まだご帰宅じゃなかったし、中尉さんもまだご帰還あそばされていなかったので、それならわたしらも、せめて主任がご帰宅されるまではと粘っていたんです。
主任がいわれたように、ひょっとすると中尉さんが仲間を引き連れて帰ってくるんじゃないかと思いましたので。そしたら、豈図(あにはか)らんや、主任がご一緒だったとは、これにはわたしも、正直びっくりして声も出なかったですよ」
「いや、わたしもこういうことになるとは夢にも思わなかったが。そうか、それじゃあ、やっぱり飯はまだ喰ってないんだな」
「ええ。ですが、そこの酒屋へ電話をかりにいった時に、アンパンと、それに、ミルクコーヒーを御馳(ごち)になりましたので……」
と谷口は、路地の角から四、五軒先の中野坂上寄りにある酒屋へチラと視線をやった。通りに軒を連ねる商店は、すでに戸を閉め灯りも落としていたが、その酒屋だけは、カーテンを引いたガラス戸に店内の灯りを映していた。
「それじゃあ、何時までも店を開けさせておいては気の毒ですので、電話を借りた礼がてら、ちょっと挨拶してきます」
と、桜木が思い出したようにいって、その酒屋へ向かった。
「ついでにアンパンの礼もな。また今度ということもあるだろうからな」
と、谷口はその背に、いかにもついでにといった調子で言葉をかけ、また木坂に訊いた。
「中尉さんが降って湧いたのは、何処ですか?」
「青山通りの、陸大前だ」
「ということは、例の竜土軒か、古巣の歩一へでも行ったということでしょうか?」
「まあそんなところだろう。だがその話は、今後のこともあるし、何処かで飯でも喰いながらにしようか……とはいっても、この辺の店はみんな閉まってるようだし、新宿へ出るしかないようだな」
と木坂は、辺りを見回しながらいった。
「ええ、ご覧の通りですから……しかし、そういうことであれば、中尉さんから目を離さないほうがいいのでは?」
「なあに、あの中尉さんが、今夜すぐに、何か事を起こすような様子に見えたか。そのかわり、明日からは飯を喰ってるヒマもないかもしれんぞ」
と木坂は笑った。
そこへ桜木が戻り、待つほどのこともなくやってきた円タクを捕まえた。この青梅街道もまた、新宿の盛り場へ飛んで返る空車に事欠くようなことはなかった。三人が乗り込んだ円タクが淀橋を渡り、夜の街に消え去るのを待っていたかのように、酒屋の灯りが消えた。が、それを待っていたのは酒屋だけではなかった。