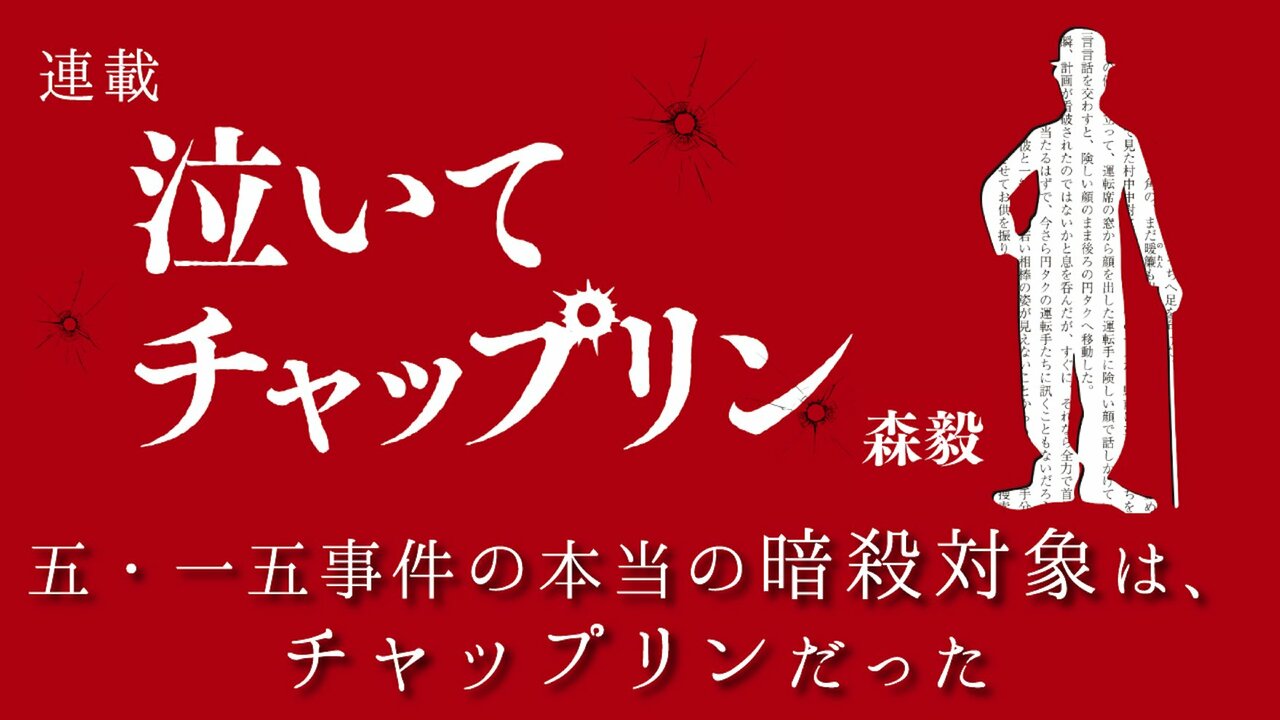六
月明かりに浮かび上がる白亜の絵画館。夜の底に樹木のあいだを縫うように曲線を描いている、コンクリートで舗装された白い幾条かの遊歩道。いかにも絵画的で幻想的だったが、その現実感の希薄さが寒々しかった。
陸軍の練兵場だった代々木ヶ原が、西欧風の広大な公園を模したような、異国情緒漂うモダンな神宮外苑に生まれ変わってから十年。わずかながらも武蔵野(むさしの)の面影をとどめていたここにも、急速に変貌する帝都東京の、否、遮二無二近代化を急ぐ帝国日本の一端を見てとることができた。
このままいったら はたして十年後の日本は……と、そんなことは考えないことにして木坂は足を急がせた。
大手町(おおてまち)や銀座であればまだしも、庶民の暮らす屋根瓦が犇(ひしめ)く町並みや、いまだ舗装もされていない、一雨あると忽(たちま)ち水溜りや、足をとられてしまうぬかるみができてしまうような一般道路には、およそ不似合いな、近代化の最先端のフォードやシボレーが並走できる、コンクリートで舗装された外苑の外周道路に出て、間近に見える陸軍大学の裏手を右へ折れると、陸軍省と参謀本部が鎮座する三宅坂から渋谷に到る、帝都東京の主要道路の一つ、「上通り」通称「青山通り」を望むことができた。
自動車のヘッドライトが右に左に矢のように往き交う通りに軒を並べた商店の背後には、「青山墓地」の森が、峨々と連なる岩山のように夜空を抉(えぐ)って立ちはだかっていた。目指す《竜土軒》は その森のすぐ向こう側だった。
通りに出ると、三宅坂方面からやってきた市電と鉢合わせになった。それをやり過ごして通りを渡ろうと、車道に一歩踏み出た時だった。
心拍が二つ三つ飛んだ。
反対側の歩道を、硬式軍帽を目深にかぶり、マントを羽織った若い陸軍将校が渋谷方面に向かって歩いていた。
いかにも山の手「青山通り」ならではのモダンなパン屋の前だった。目映(まばゆ)いばかりの照明の下、折り目のついた白い仕事着の若い店員が、出たり入ったり忙しそうに店仕舞いをしていた。
若い陸軍将校は、歩道に溢れ出ている照明を浴びながら、その前を横切った。田島中尉に間違いなかった。
憲兵隊も近代化に遅れてはならじと、小さな家が一軒建つほどの大金を投じて仕入れた、ドイツ製の《ライカ》で盗み撮りした、ちょっとピンボケの写真では見ていたが、実際に目にするのは初めてだった。
写楽の「大首絵」と、谷口軍曹がいっていたほどひどいご面相ではなかった。剣道か柔道の稽古でつぶされたといわれる右耳も、聞いていたようにひしゃげ、側頭部に張りついていた。にしても、肩を落とし、日頃の青年将校の覇気やブライドもどこかに置き忘れてきたような、大きな悩み事をかかえて彷徨(さまよ)い歩いているといった力ない足取りだった。
店員が店仕舞いの手を止めて、慌てて道をゆずったことにも気づいた様子はなかった。目深に被った硬式軍帽が、その横顔をいっそう暗くしていた。
木坂は、ご挨拶するつもりだったことも忘れ、通りを挟んだままその後を追った。行き交う円タクや、時に巨体をゆすりながら通る市電が格好の遮蔽物(しゃへいぶつ)になったが、伏し目がちに黙々と足を運んでいる田島中尉には、そんなものはまったく不要だった。
ほどなく、市電の《明治神宮前》の停留所が見えてきた。その右側の歩道には、神宮の表参道の入り口を示す、左右一対の見上げるような石灯籠が建っていたが、田島中尉はそれも目に入らぬように素通りした。堅苦しいことをいえば、明治大帝の御霊(みたま)を祀る社(やしろ)の門前を素通りするなど、軍人としてはモッテノホカだったが。
やがて何輛ともしれない市電が整然と並んで眠りについている「青山車庫」を右に見て、さらに行くと、通りは長い下り坂になり、眼下に広がる渋谷の盛り場の灯が一望できた。
五年前に、渋谷と横浜を結ぶ東急東横電車が開通し、今では、銀座、浅草、新宿につぐ盛り場となり、その華やかさを象徴しているモダンな《キリンビール》の真紅のネオン塔が夜空にひときわ鮮やかにそそり立っていた。
と、田島中尉の目にもそれが映ったのか、不意に足を止め、物思いにふんぎりをつけたかのように夜空を見上げたかとおもうと、いきなり振り返った。一瞬ギクリとしたものの、そんな時の用心は無意識のうちにもできていた。
木坂は、風に吹かれた木の葉のようにヒラリと踵を返し、三、四歩通りすぎたばかりの、これまた目映い照明を通りへ惜しげもなく撒き散らしている楽器店に飛び込んだ。
『酒は涙か、溜息か……』と、世の荒波に翻弄されている人々に、切々と語りかけるような物悲しい歌詞、それと裏腹な、軽快なギターの調べも絶妙な古賀メロディーが流れていた。店内に所狭しと陳列された、大きな宝石箱のような蓄音機。その一台の上に鎮座して首をかしげているビクターの賢そうな陶磁の犬。
左手の陳列棚には、アコーディオン、マンドリン、ギター、バイオリン。右側の陳列棚には、金ピカの金管楽器類が、絢爛(けんらん)たるモダニズムの華が妍(けん)を競っていたが、木坂には、どれもこれも縁のない別世界のものばかりだった。
が、灯台もと暗し。目の前の小学生でも上から覗きこめるような、全面ガラス張りのショーケースの中に、これまたピカピカのハーモニカが、飾り雛のように行儀よく並んでいた。
一瞬それに目を奪われた。三人の娘たちが口を揃えて欲しがっていたからだったが、見とれているヒマはなかった。
田島中尉が手を上げて、三宅坂方面からやってきた円タクを止めていた。大手町のオフィス街とちがい、盛り場を目指してやってくる空車には事欠かなかった。木坂は、田島中尉が乗り込んだシボレーが走りだすやいなや、つづいてやって来たフォードに手を振りながら、通りへ躍り出た。