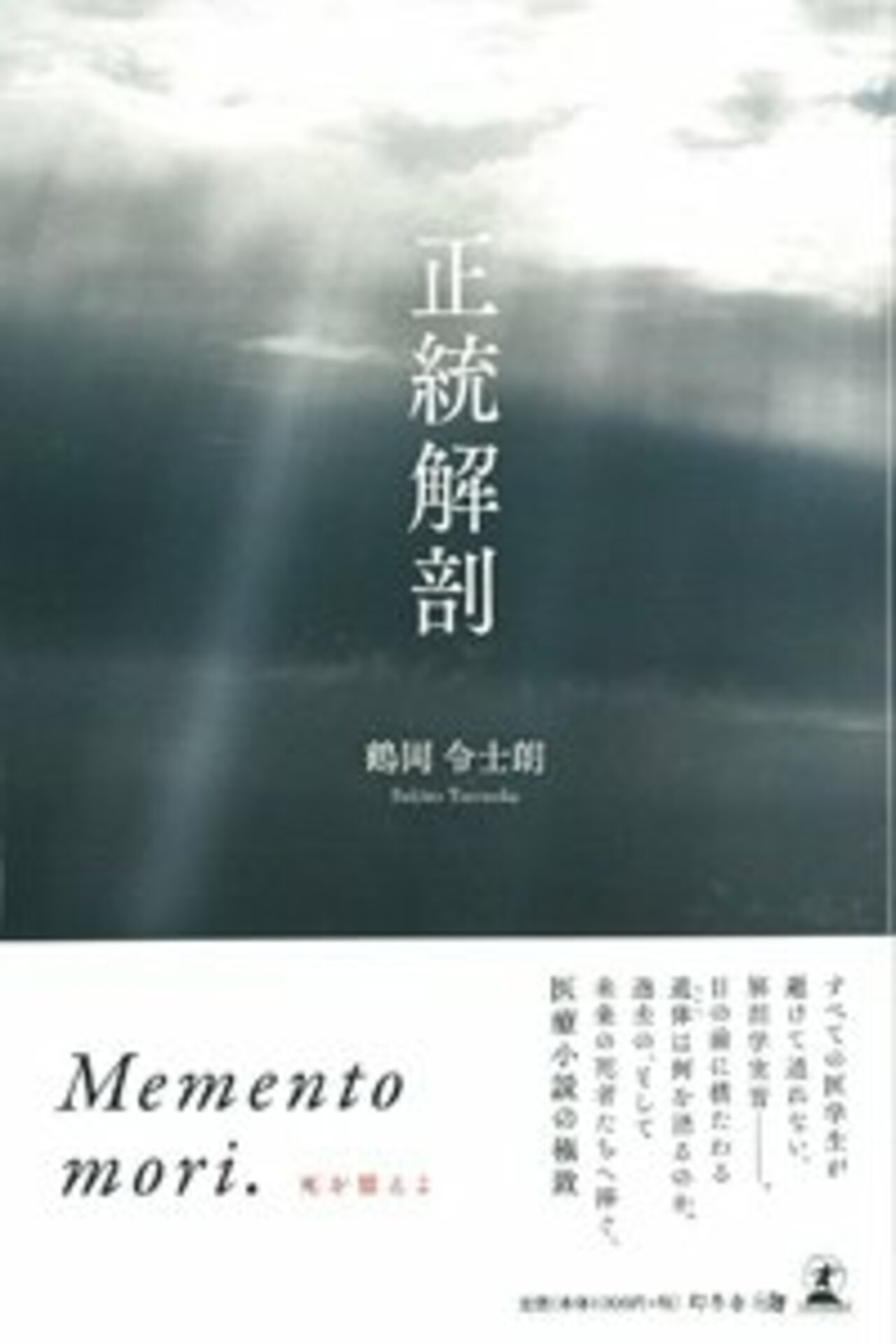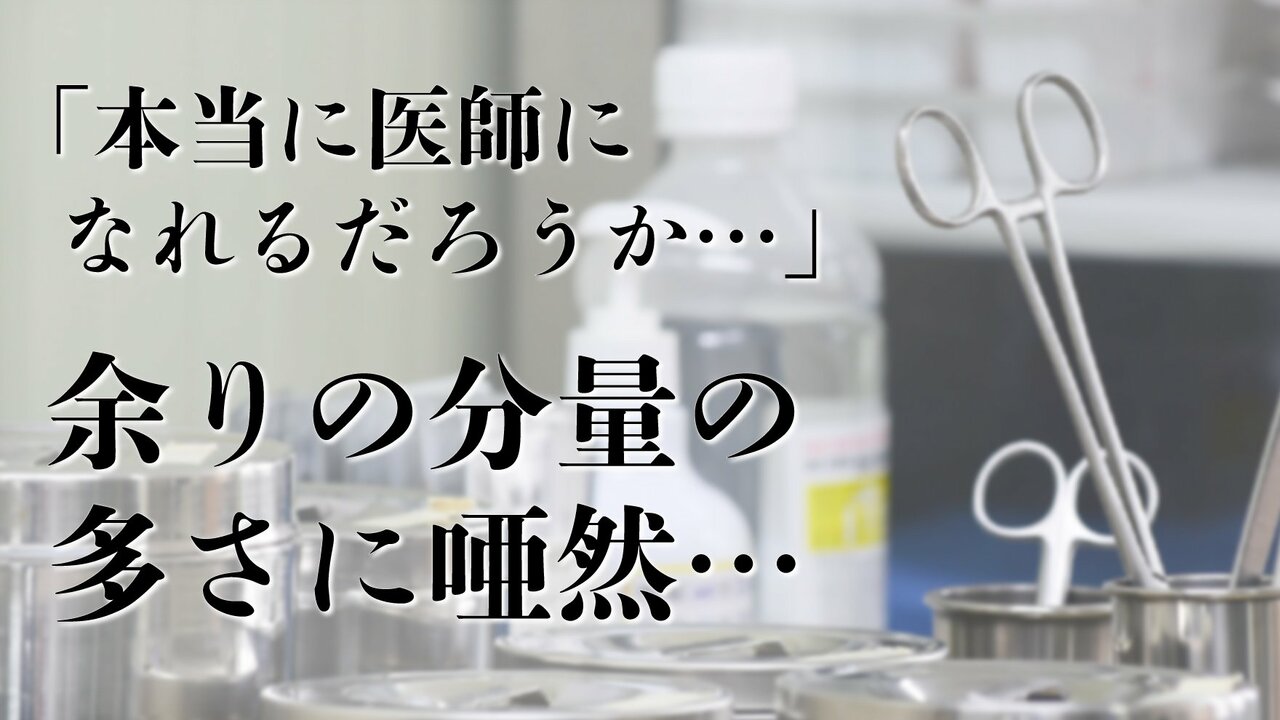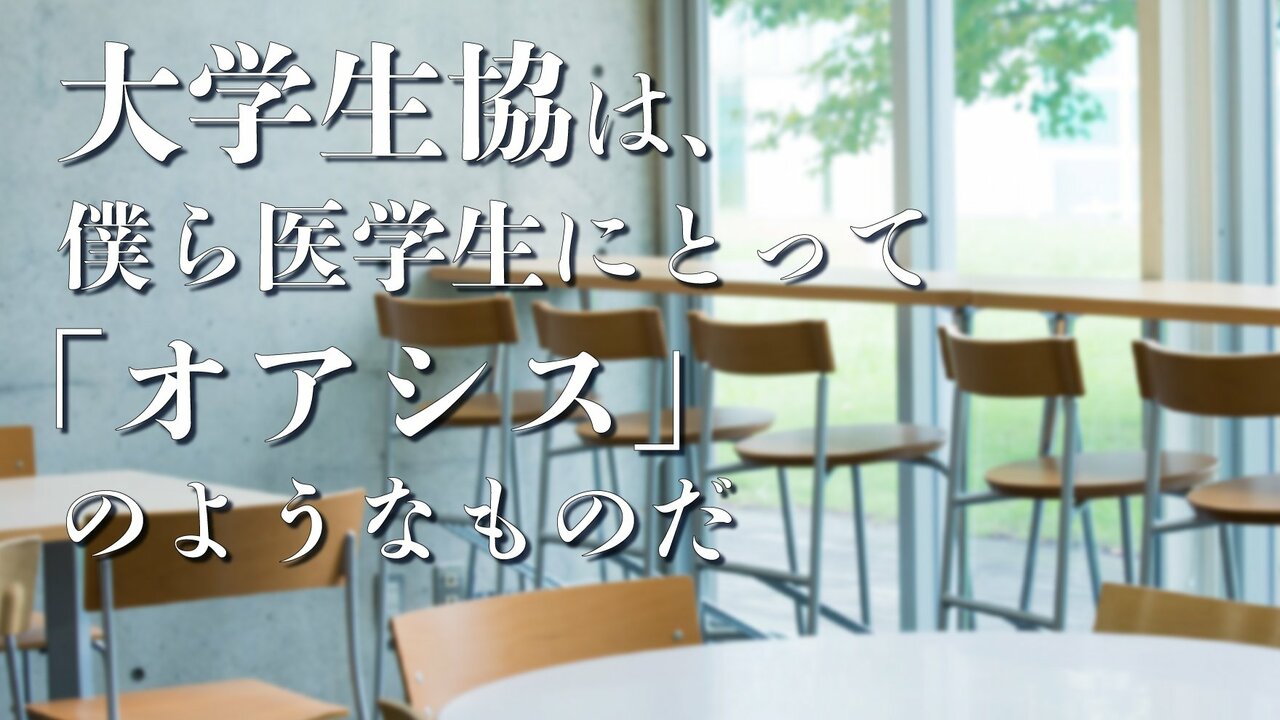生命の崇高と人体構造の神秘を描き切る傑作。
ほぼ100日、約3カ月におよぶ正統解剖学実習。死者と向き合う日々のなかで、医学生たちの人生も揺れ動いていく。目の前に横たわる遺体(ライヘ)は何を語るのか。過去の、そして未来の死者たちへ捧ぐ、医療小説をお届けします。
第3章 上肢をはずす
実習が始った時には、まだ風も冷たい日が有り、春のまろやかな日ざしだったが、講義と実習、実習に講義と繰り返すうち、季節は巡り、初夏の気配を感じるこの頃になった。先日、僕は久しぶりの休みを利用して、ショッピングモールへ夏服を買いに出かけた。
【他の記事も見る】「発達障害かもしれない職場の人」との関係でうつ病になった話
天気も良く、初夏の日差し、適度な温もりの風が心地よかったし、家族や恋人同士らしい楽しそうな人々と行きかい、その中に混じっていることが嬉しかった。ご遺体と向かい合うことが日常となっている今の時期、生きた人ごみの中にいることは、何か新鮮な気がした。
ふと、明るい服装で、楽しそうに会話する若い男女を見ているうちに、こうしている僕もいつかはいなくなってしまうのだな、と初めて実感を伴って気づいた。でも、それは自分にとって、当分考える必要のない、遠い未来だろう。
繁華街を屈託なく行き交う若い男女には、死の気配さえもない、かけらさえも。僕には、ホルマリン、いや死の匂いが染み付いていないだろうか。ふと不安になった。