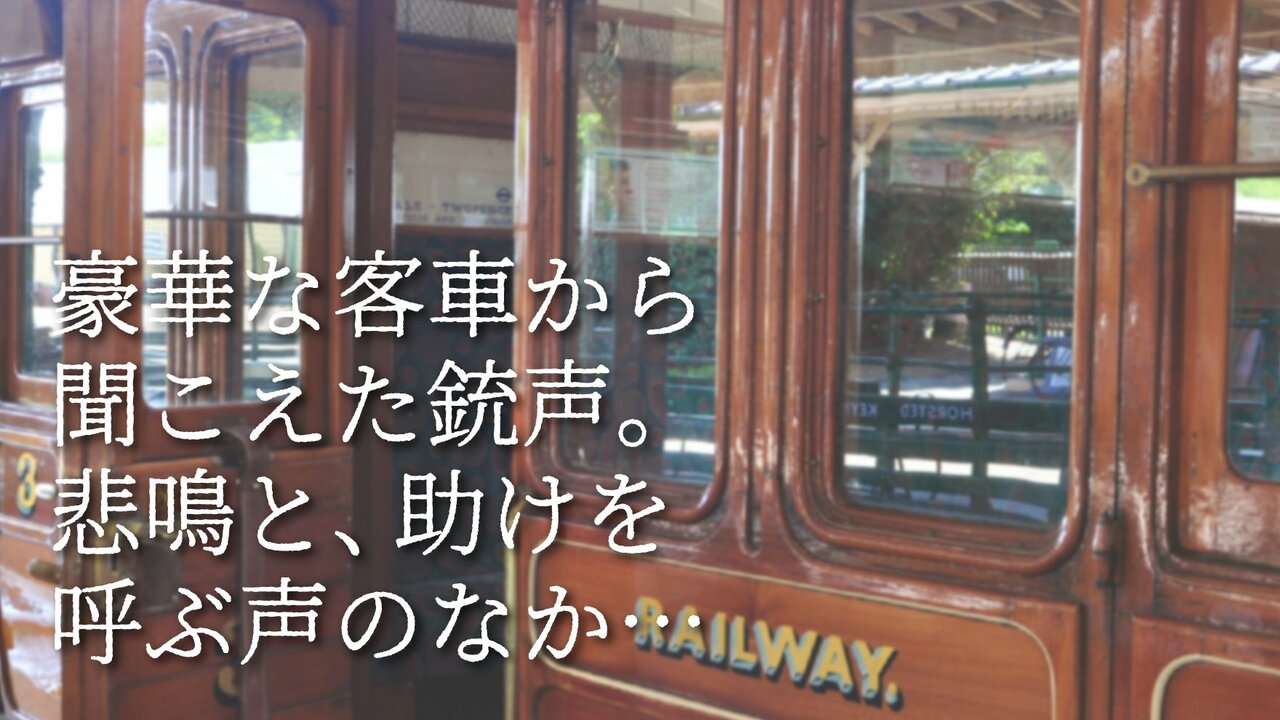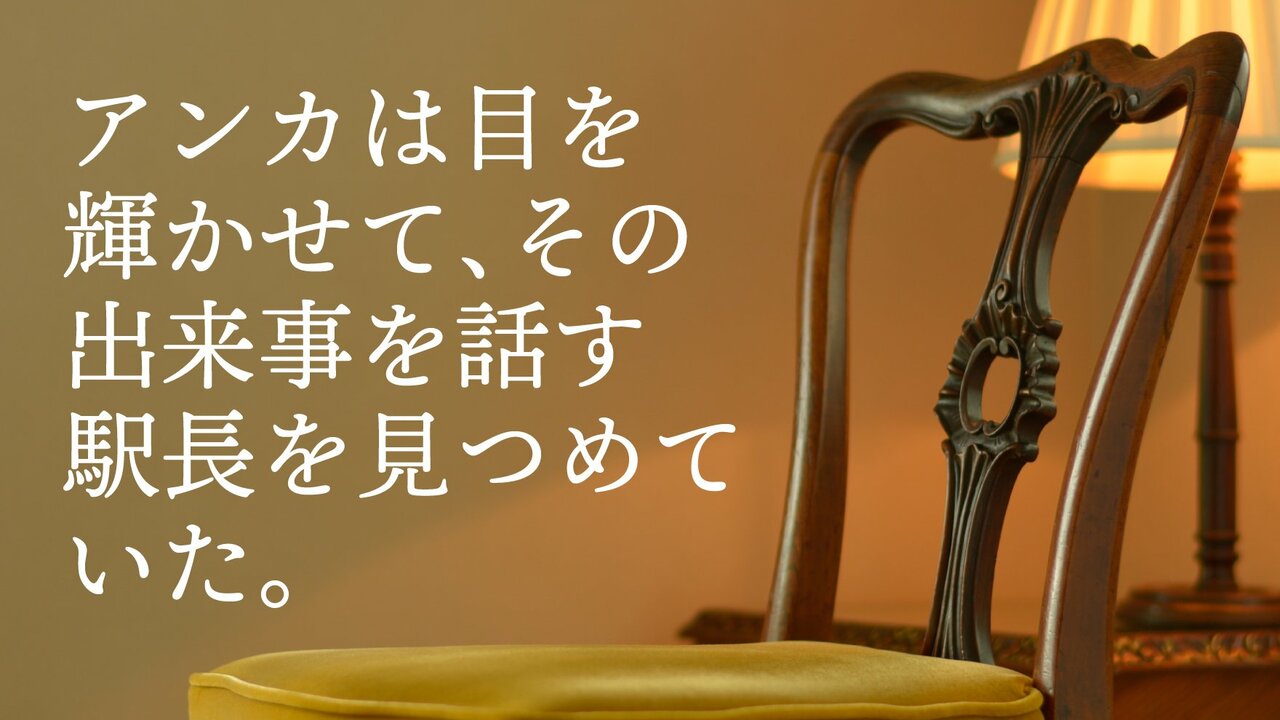彼は、ありふれたビジネススーツを上品なタキシードに着替えていた。手には、あの必携のかばんをたずさえており、そのことは、夕食の時ですら身から離さないという意志を表していた。グリマルディはアンカが広間にいないかとキョロキョロ見回して、数人の宿泊客の存在を認めた─隆々とした白髪のもみあげの頭で、パイプを片手に新聞に見入っている年輩の大柄なオーストリア人一人。次に、昔の流行の装いで古風なカップでコーヒーをすすりながら盛んにおしゃべりしている、明らかに田舎者とわかる二人の中年女性。そして、三、四歳の落ち着きがない娘を連れた夫婦。その娘はしばらく騒ぎ声をあげて走り回っていたが、そばかすのある色白で赤毛の母親は見るに見かねて子供を膝にうつ伏せに載せてはお尻を引っぱたいた。暗色の表紙の本をずっと眉をひそめて読んでいた夫が、不承不承といった目つきで促して初めて、妻は泣き叫ぶ子供を引きずり出さざるを得ないと観念した。アンカは、彼らが東洋への旅の途中の英国人家族であり、鉄道で南進する前にベオグラードで一、二日間の途中休憩を取ることにしたのだと推測した。
グリマルディはついにアンカを見つけて、陽気に手を振りあげる。彼女は微笑んで、雑誌をテーブルに片づける。そのイタリア人は、しっかりとした足取りでアンカが座っていたひじ掛け椅子に近づき、お辞儀して懇願する。「麗しきお嬢様。お願いがあるのですが。ここで懇意になっていただいているただ一人の御方として、ディナーで私と同伴していただくことを。決して拒否なさらないでください。そうなったとすれば、あなたの美しい首都での印象と歓びを滅茶苦茶に壊してしまうことになるでしょうから」
「ジョルダーノ様、そうでしたらば」と、アンカはしとやかに答え、起立を助けようと自分の前に差し出されていた手を受け入れる。「あなたが満足せずにベオグラードを離れるのを見過ごすなんて、できませんわ」