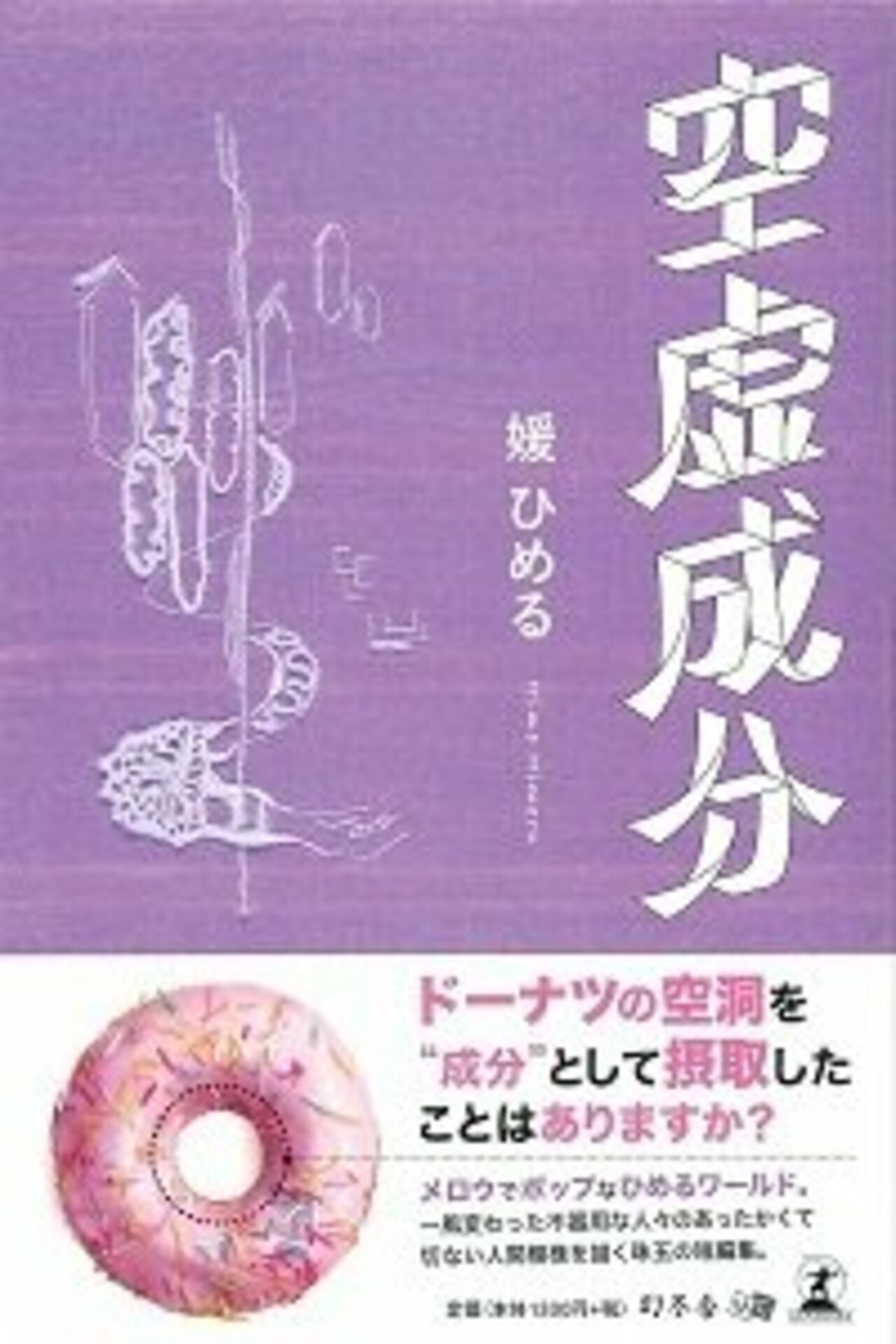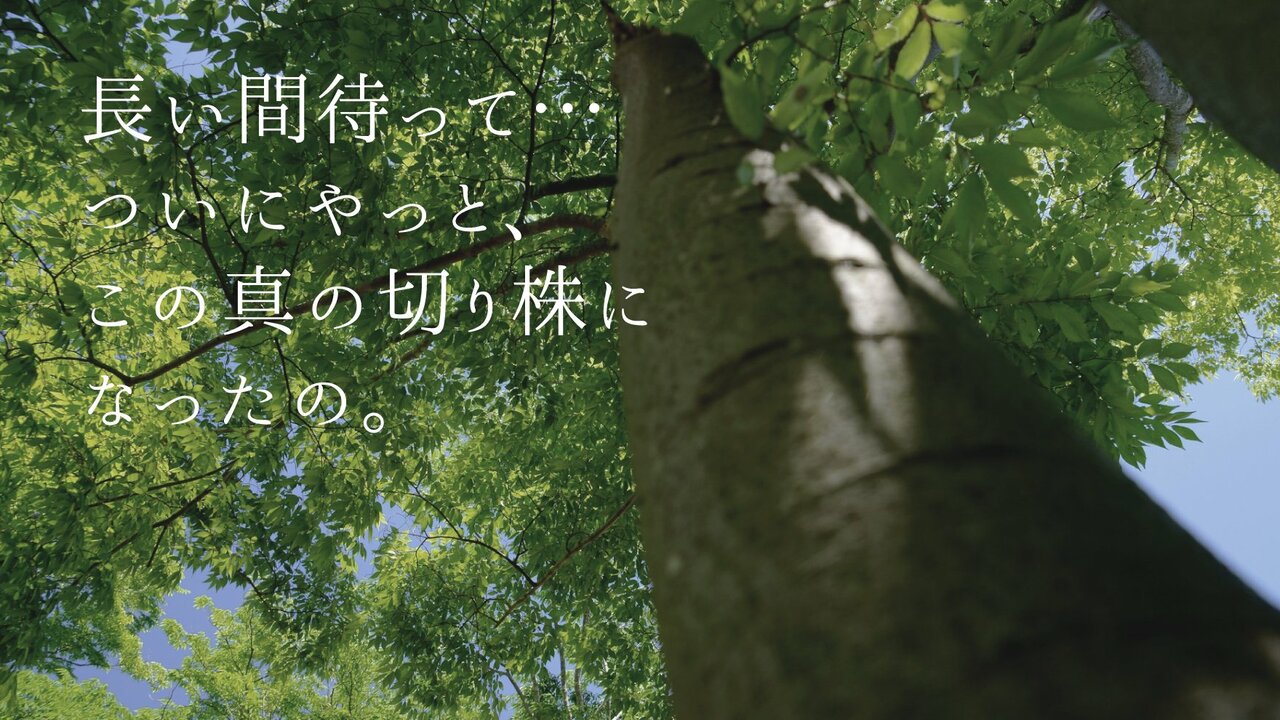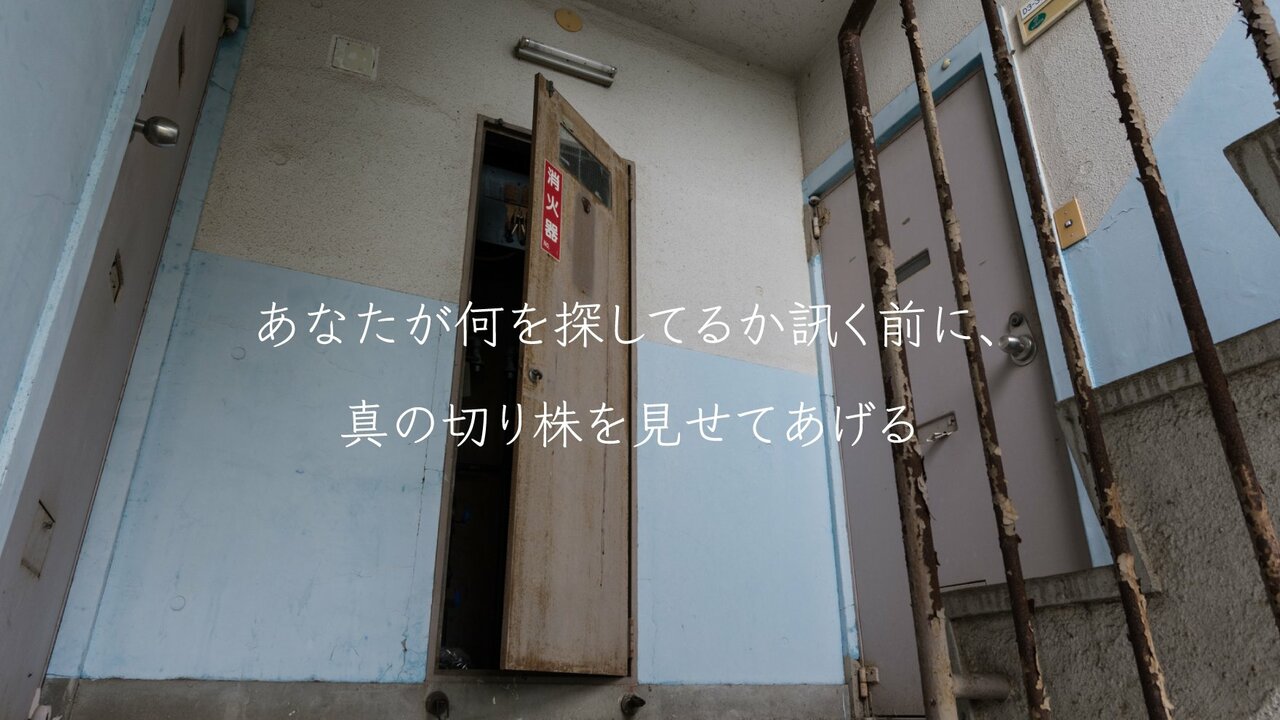くしゃみとルービックキューブ
4.
華は学校を突然やめてしまってからずっと家にいる。部屋にこもりっぱなしだ。さすがに気になって、旦那様にさりげなく言ってみると、「何考えてるんだか。困ったもんだな」と鷹揚に笑っただけだった。
その後すぐ、「ところで君」と口調を変え、出張の日程などについて話し始めて、華の話はそこでおしまいになった。
父親がよしとしているなら、部外者の自分がとやかく言うことではない。柚木は旦那様のその反応を見て、それ以降は華に関して完全ノータッチに切り替えた。
それに、柚木は華が苦手だった。ろくに言葉を交わしたこともないが、華の発している雰囲気がどうも好きになれない。いつも暗い目をして、周囲をうかがうようにしている。
柚木が食堂を出たのを見計らって、こそこそ一階に降りてくる。何を考えているのかまったく分からない。まぁ自分の娘以上に年が離れている子のことなど、最初から分かるはずもないのだが。
あるとき、屋敷の門の前を掃いていると、ふと視線を感じた。ほうきの手を止め、顔を上げる。誰もいない。通勤や通学に急ぐ人も途絶え、午前十時の通りはシンと静まり返っている。気のせいか、と柚木は再び掃除に戻った。
一日の仕事を終えて彼女が屋敷を出るのは、だいたい夜の八時だ。夕食の支度をして、台所の掃除と明日の朝食の簡単な準備を済ませてから屋敷を後にする。いつものように仕事を終え、夜道を歩き始めた彼女は再び視線を感じた。
視線というのは本当に感じるものなのだ。なんとなく、緊迫感を含んだ視線だった。
間違いない。誰かが自分を見ている。