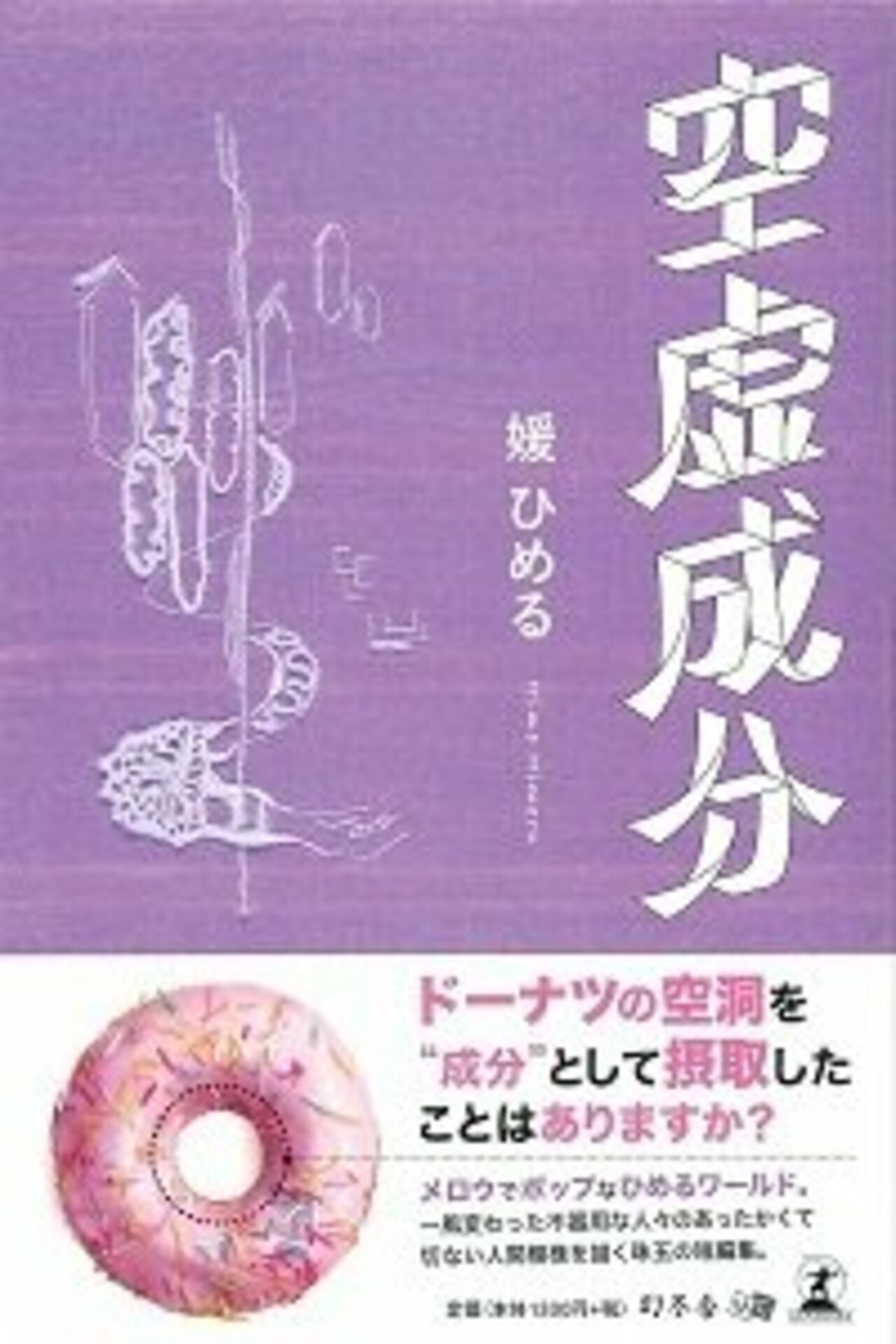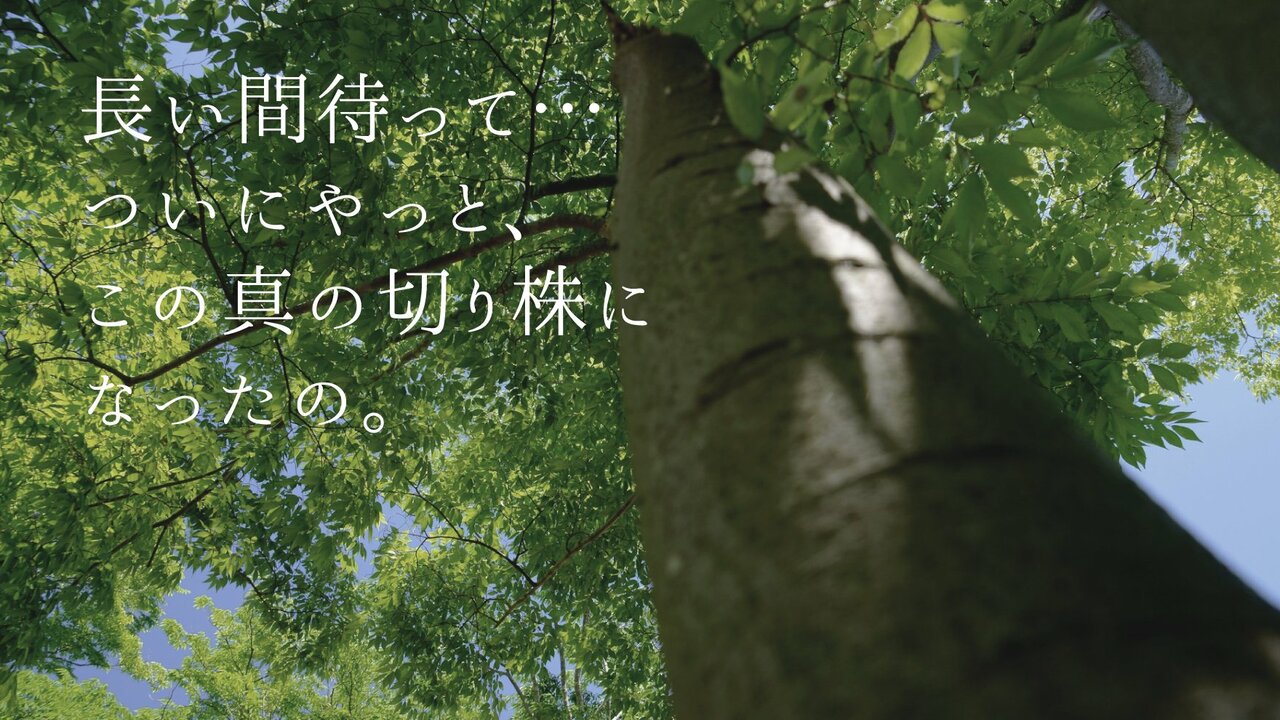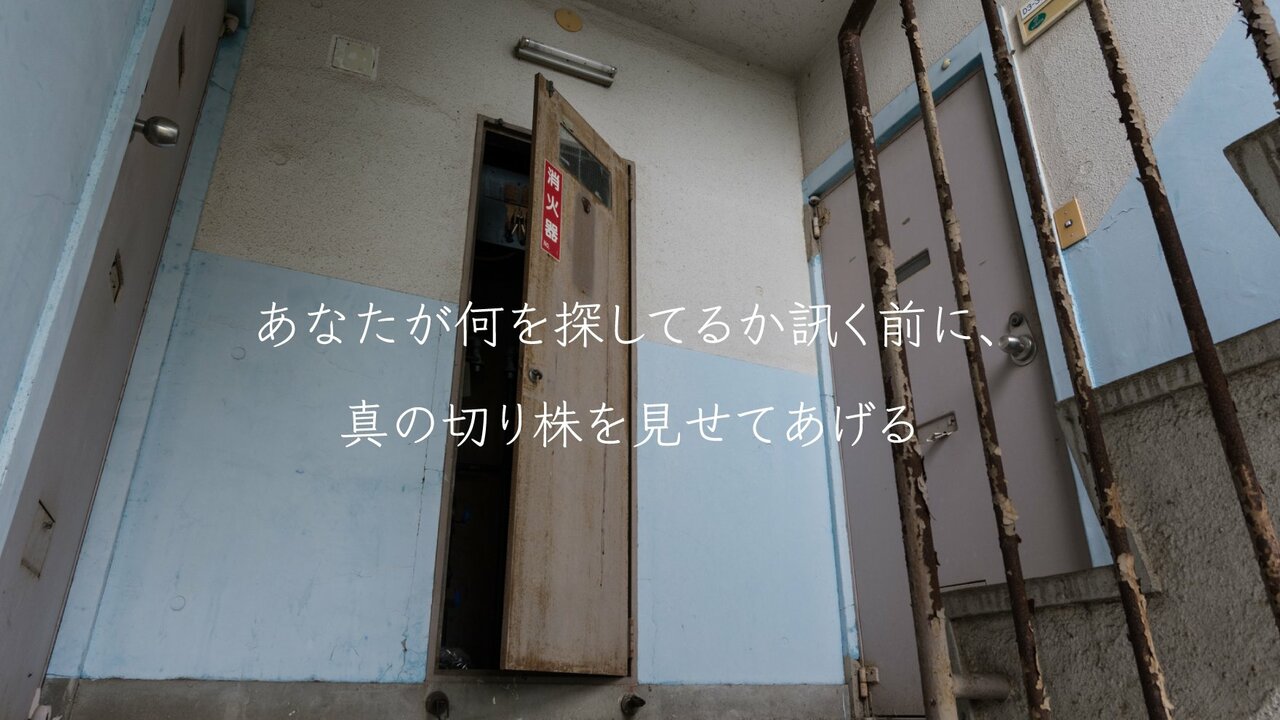だが暗い夜道の途中で立ち止まってキョロキョロするのはためらわれた。
そんなことをしたら最後、視線の主が襲いかかってくるような気がする。急に走るのも駄目だ。
柚木は背筋を緊張させたまま、駆けだしたい衝動を必死に抑えつつ、ひたすら前を向いて歩いた。
その日からというもの、彼女はたびたび視線を感じるようになった。ふと気付くと誰かに見られている気がする。旦那様の仕事の関係者だろうか、と漠然と考える。
ライバル会社の誰かか、それかもしかすると個人的に恨みを買うようなことでもしたのかもしれない。旦那様にこのことを報告したほうがいいか、柚木は迷った。考えた末、話さないことに決める。あくまで自分は一介の家政婦なのだ。余計なことに口出ししないほうがいい。何か訊かれたら、実は……と話せばいいのだ。
だが、事態は向こうから動き始めた。
食料の買いだしにいこうとスーパーに向かっている途中で、見知らぬ男性に声をかけられた。
「すみません。郷田さんの家で働いてらっしゃる柚木登志子さんでしょうか」
柚木は驚いて立ち止まった。男の全身にざっと目を走らせる。くたびれた感じの紺色の背広に、水色のチェック柄のネクタイ。年は四十後半といったところだろうか。短髪で、目が少し吊りあがっている。
「そうですが……なんでしょう?」
視線の主はこの人か、と柚木は思った。