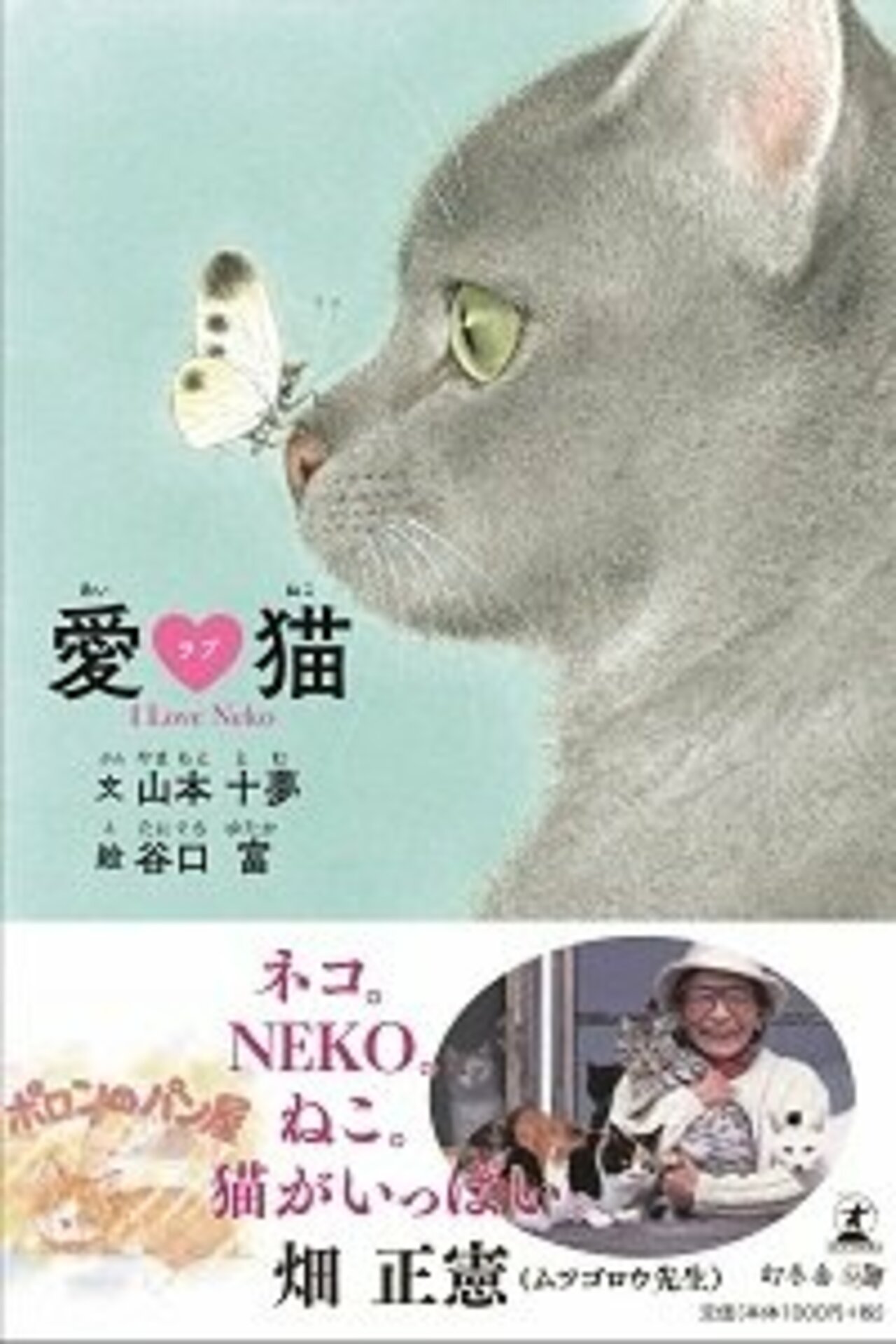パン屋のポロン
おじちゃんとおばちゃんが、いそがしくパンを運んで棚に並べていた。
「ミャーォ」
まだ、おじちゃんも、おばちゃんも、ぼくの声に気がつかない。
「ミャーオ、ミャーオ」
思いきり声を出した。
「ん? おおっ?」
「ポロンやなかと? お前生きとったか」
「ミャーオ」
「まあ、ほんなこつポロンかい? よかったぁ」
おばちゃんとおじちゃんは、かわるがわる、ぼくを抱いて泣いていた。
「あん時、必死でさがしたつばってん、見つけきらんかったぁ。家はつぶれてしもうたけん、着の身着のままで避難所に行ったと。すまんかったなぁ」
ぼくは体じゅう汚れていたけど、おばちゃんも、おじちゃんも、平気で抱きしめてくれた。ぼくは、うれしくなってゴロゴロ、ゴロゴロと声を出して、おじちゃんやおばちゃんの胸もとに肉球を交互に押しつけた。
「店の休みのたんびに(たびに)、ふたりであっちこっちポロンばさがしまわったとやけど、見つけきらんかった」
おじちゃんとおばちゃんの目から、またひとつぶ、なみだがこぼれ落ちた。
「ここは仮設住宅ばってん、ポロンも一緒に住めるたい。よかった、よかった。ほんなこつ(本当に)よかった」
これからずっと一緒住める。それだけでじゅうぶんだ。それにまた、おじちゃんとおばちゃんの、できそこないのメロンパンが食べられる。仮設住宅のお店はせまいけど、パンのにおいは一緒だ。それから数日後のことだった。お客さんが1人入ってきた。
「あんたげんパン(お宅のパン)は、ほんなこつ(本当に)おいしかねぇ」
どこかで聞いたことのある声がした。
(そうだ! いつかぼくに、おかかのおにぎりを食べさせてくれた、あのおばちゃんだ!)
「あれっ、この猫ちゃんな、あんたげんとな(お宅の)猫?」
「そう。家がうちくざけたもんだけん(家えがこわれたから)、離れ離れになっとったと。やっと再会できたとよ」
「この猫ちゃんなら、地震のあと西原村の小学校で会うて、3日くらい、ご飯ば分けてやったこつがある」