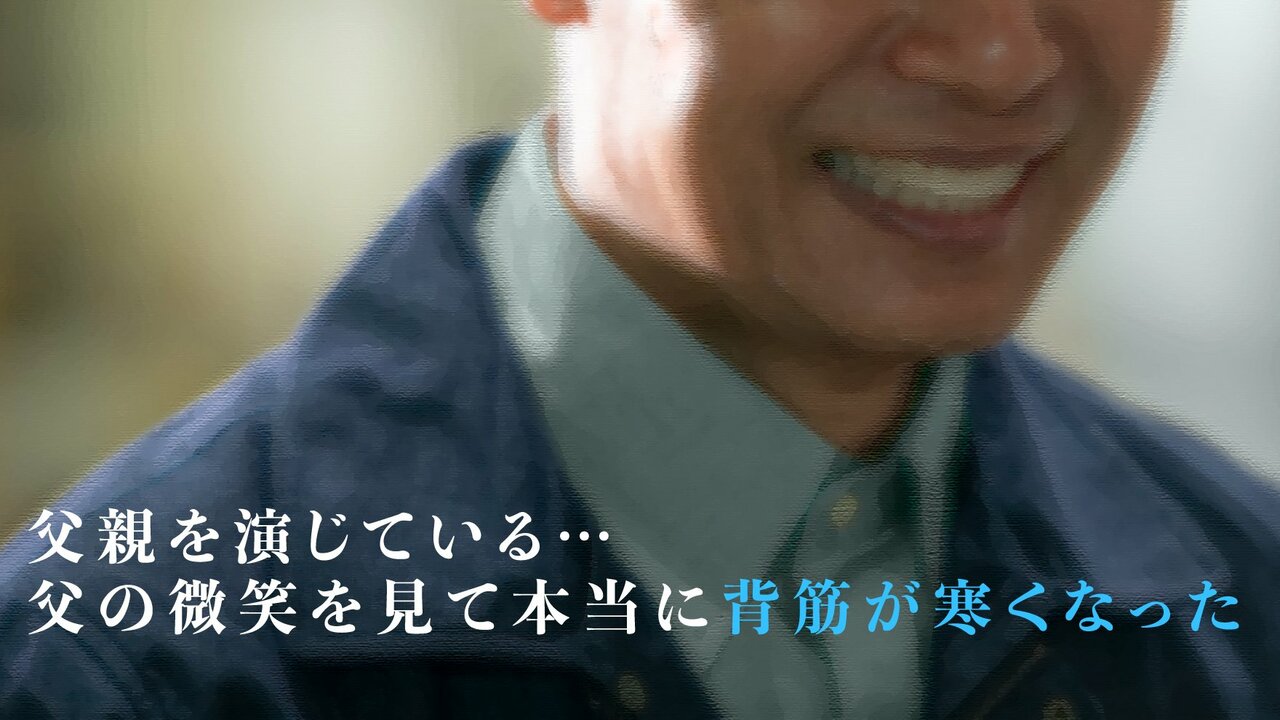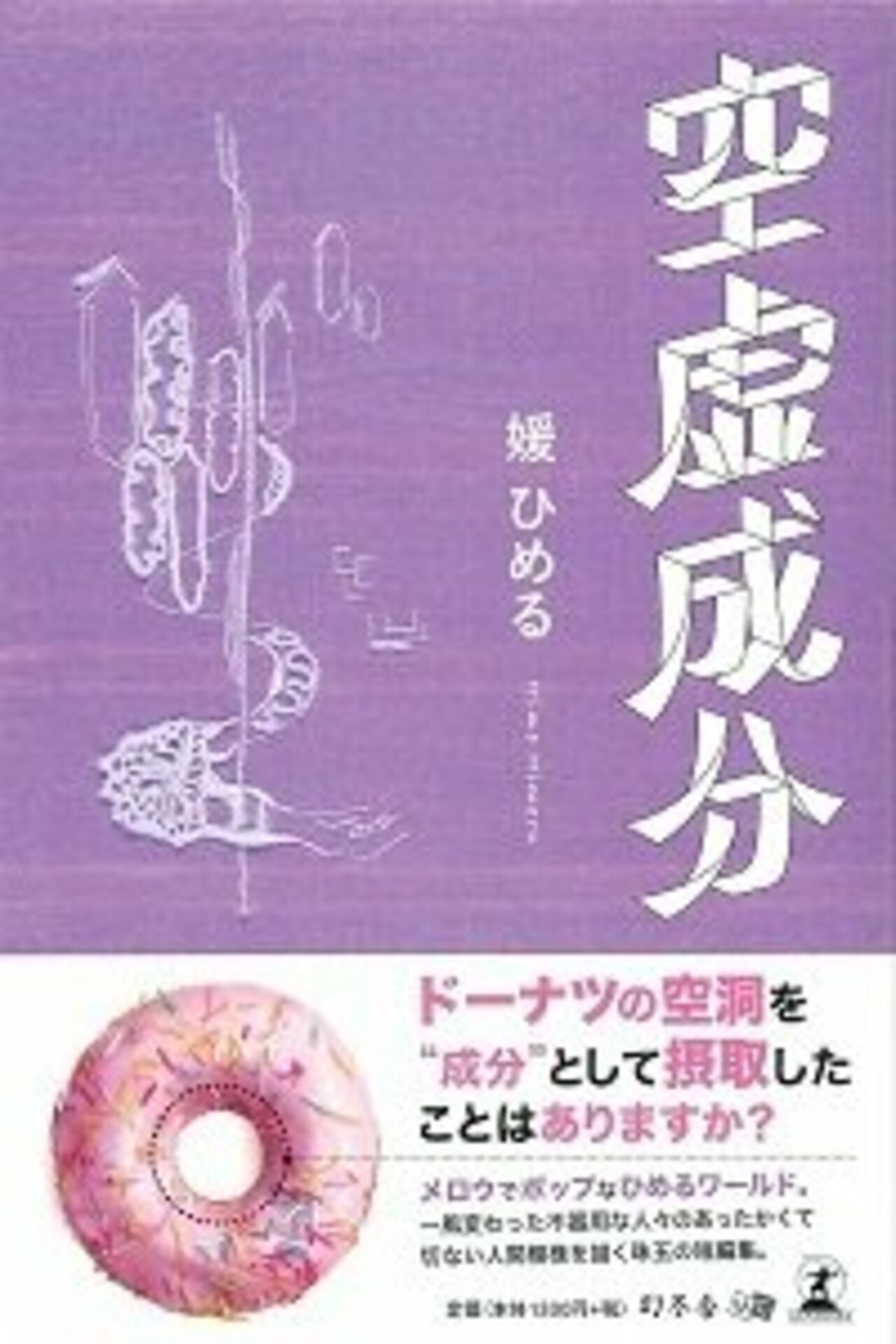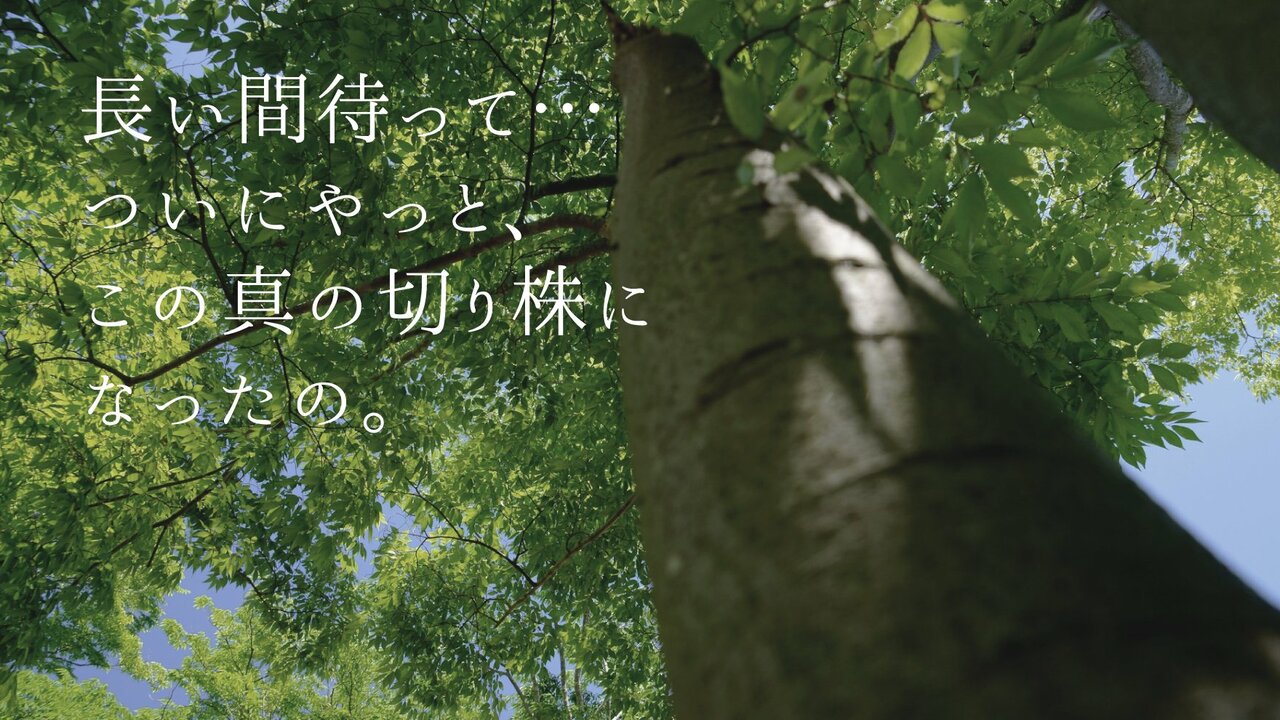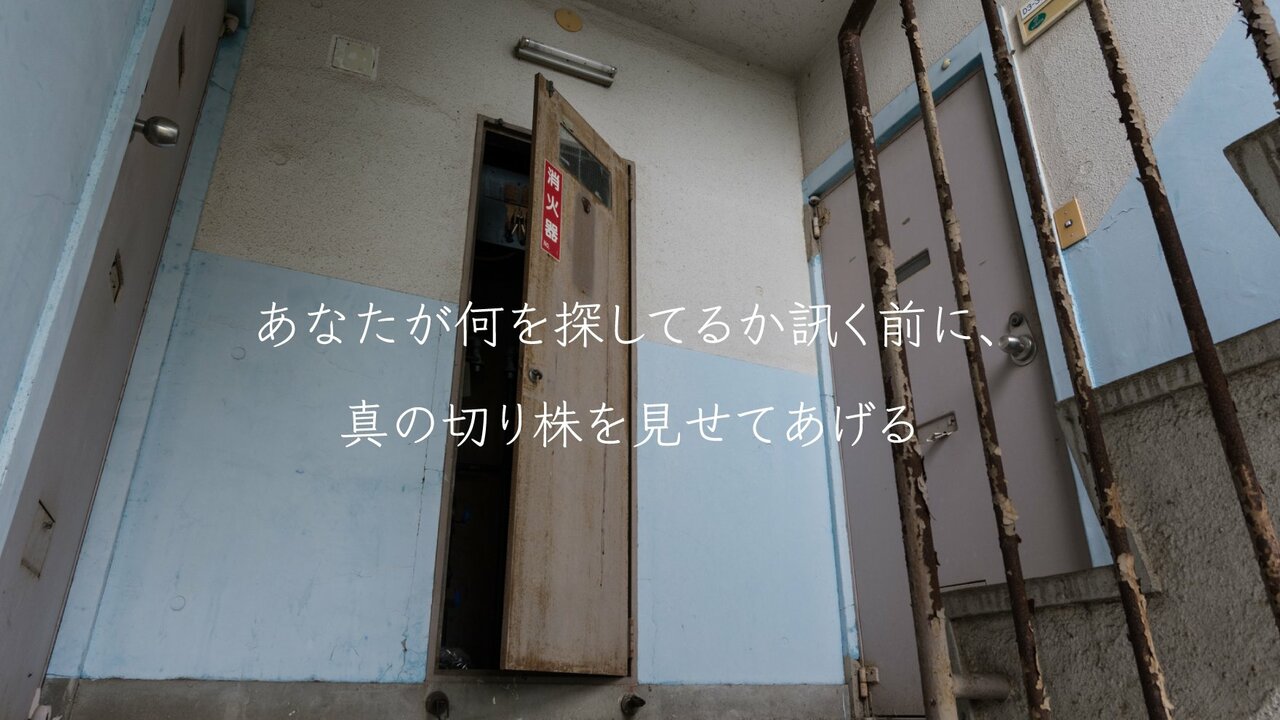くしゃみとルービックキューブ
3.
華はしばらく固まっていたが、渋々ベッドから下りた。おそるおそるドアを開ける。
部屋の光を浴びて、少し眩しそうに目を細めた父が目の前にいた。一瞬、華は虚を突かれた。頭で思い描いていた姿より、ずっと老けているように見えたのだ。
今まではそそりたつ壁のように感じていたが、背丈も横幅もごく一般的、いやむしろ一般よりも小さく頼りなげに感じた。父は目を細めたまま数秒間、華を見ていた。その顔には、特に表情らしいものは浮かんでいない。
「学校、やめたそうじゃないか」
さりげなさを装っているのが華には分かった。華は父から目をそらした。黙っていると、父がふっと笑った気がして、視線を上げる。だがそれは気のせいだった。父は笑ってなどいなかった。それはそうだ。ここは笑う場面ではない。
「本気なのか?」
華はうなずいた。きっぱりと意思を込めて。父が軽くため息をつく。
「本気なら仕方ない。やる気がないのにやっても身にならないからな。学校をやめて何をするつもりだ」
そういう質問をされることは分かっていた。だがそれに対して、華は明確な答えなど何も持っていなかった。華自身、自分が何をしたいのかまったく分からないのだ。ただ一つ確かなことは、もう学校になんの魅力も感じていないということだった。
華は、父の後ろの壁に視線をあてたまま黙っていた。再び軽いため息が聞こえたので、壁から目の前に視線を移す。