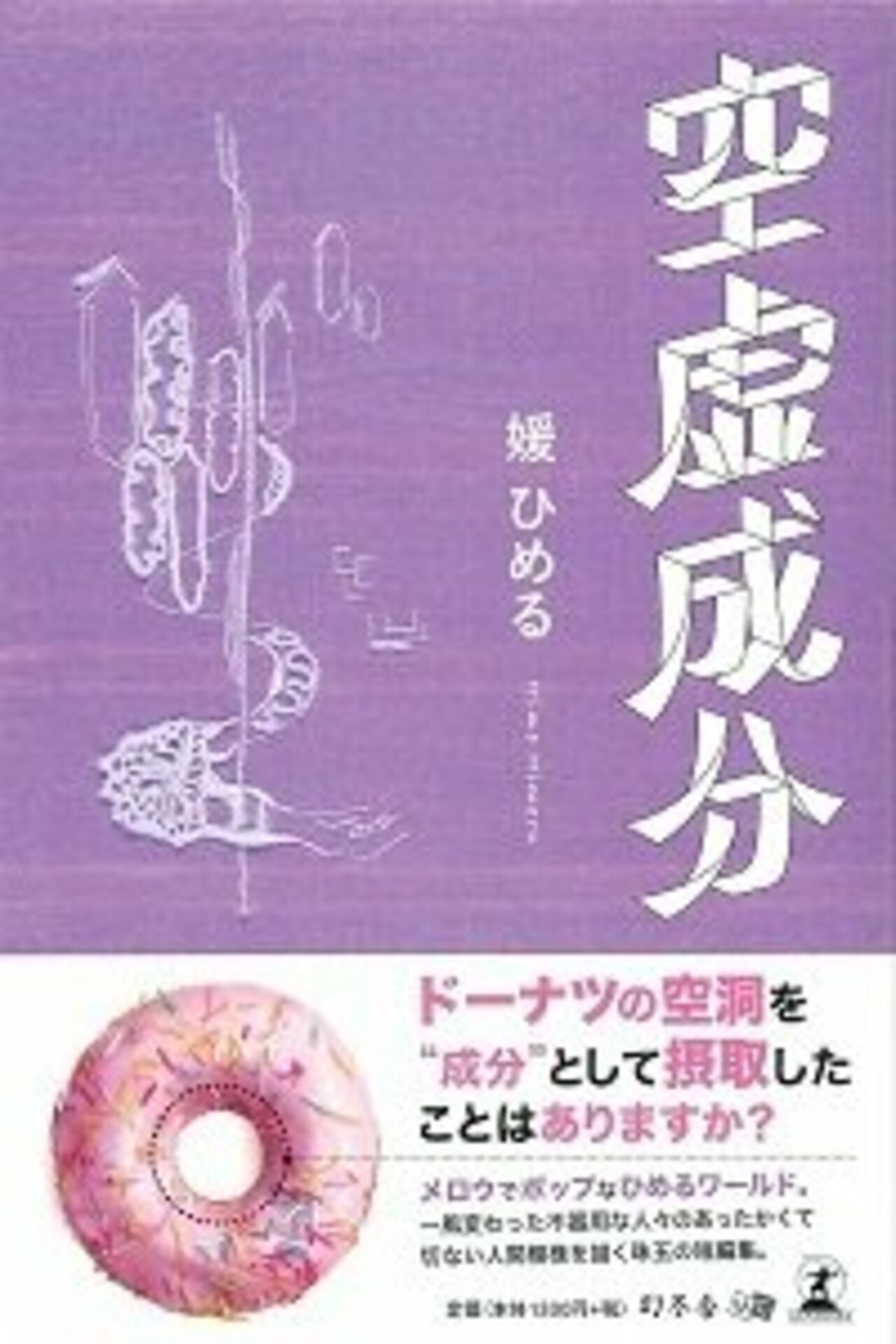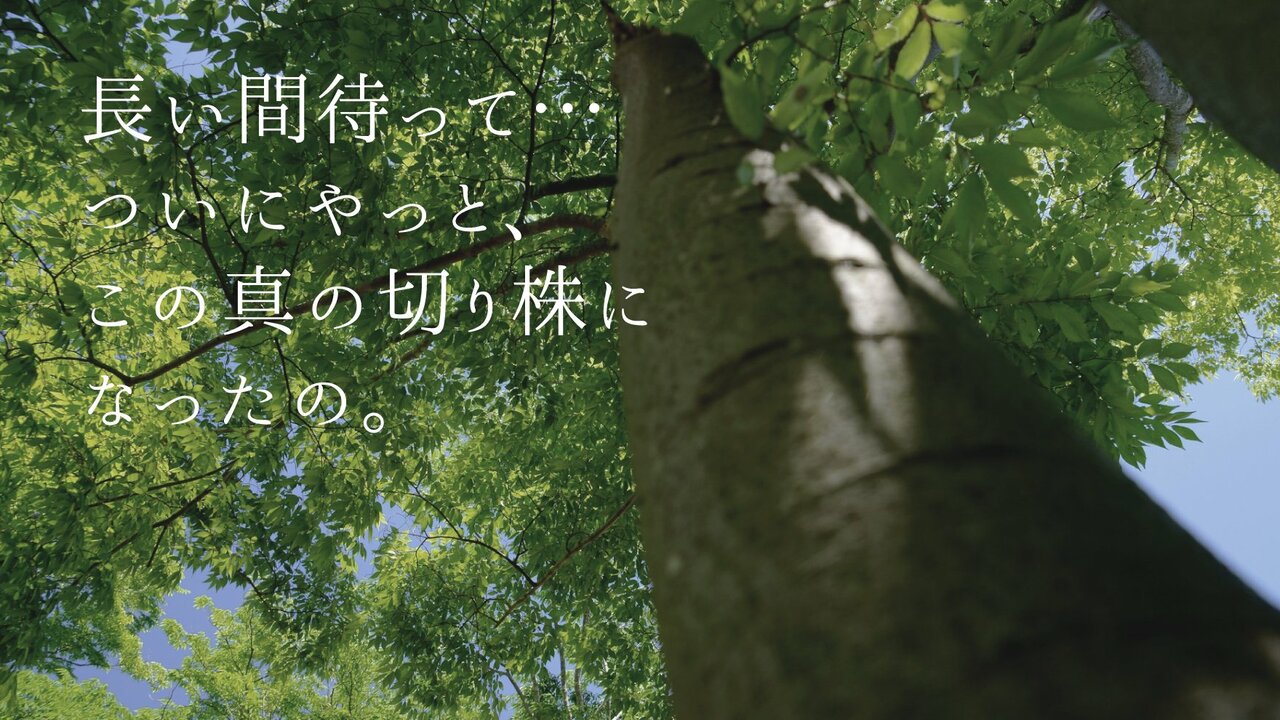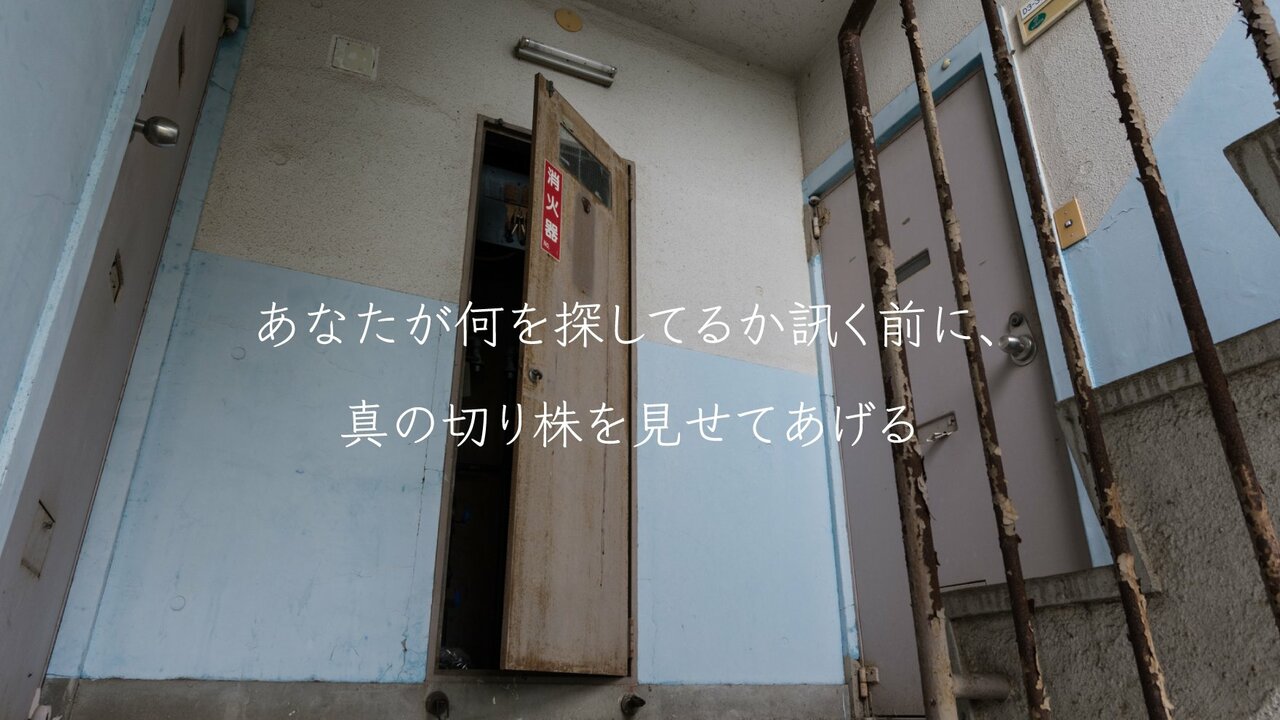父の唇に微笑が浮かんでいるのを華は見た。それは、わがままな娘の言うことを仕方なくきいてあげている寛大な父親が浮かべる微笑だった。華はゾッとした。本当に背筋が寒くなった。
──演じている。華が感じたのは、父が父親を演じている、ということだった。
「どうせまだ決まってないんだろう? やりたいことができたら言いなさい。私がいなかったら、柚木さんにでも」
とりあえず華はうなずいた。話はそれで終わりだ、とばかりに父は背を向けた。華はドアを閉めた。背筋に感じた寒気は、まだ体に貼りついている。
端から見たら、父の微笑、穏やかな言葉は、良い父親に見えることだろう。娘の意思を尊重し、見守る父。だが華の目はごまかせなかった。娘だからこそ分かった。父親だからそうしているだけであって、心の内ではまったく別のことを考えている……。
この人は私のことなどどうでもいいのだ。はっきりと華はそう感じた。前から何かにつけてそう感じていたが、目の前で父親の顔を見て確信した。まるで駄目押しのようだった。
背筋に感じた寒気は、今や薄い氷のように華の全身を覆っている。昔から分かっていたはずなのに、いざ目の前に突きつけられると、やはりショックだった。
父は私になんの関心もない。いや──と華は苦々しく思う。それどころか、私を邪魔に思っている。私なんかいなければいいと思っている。