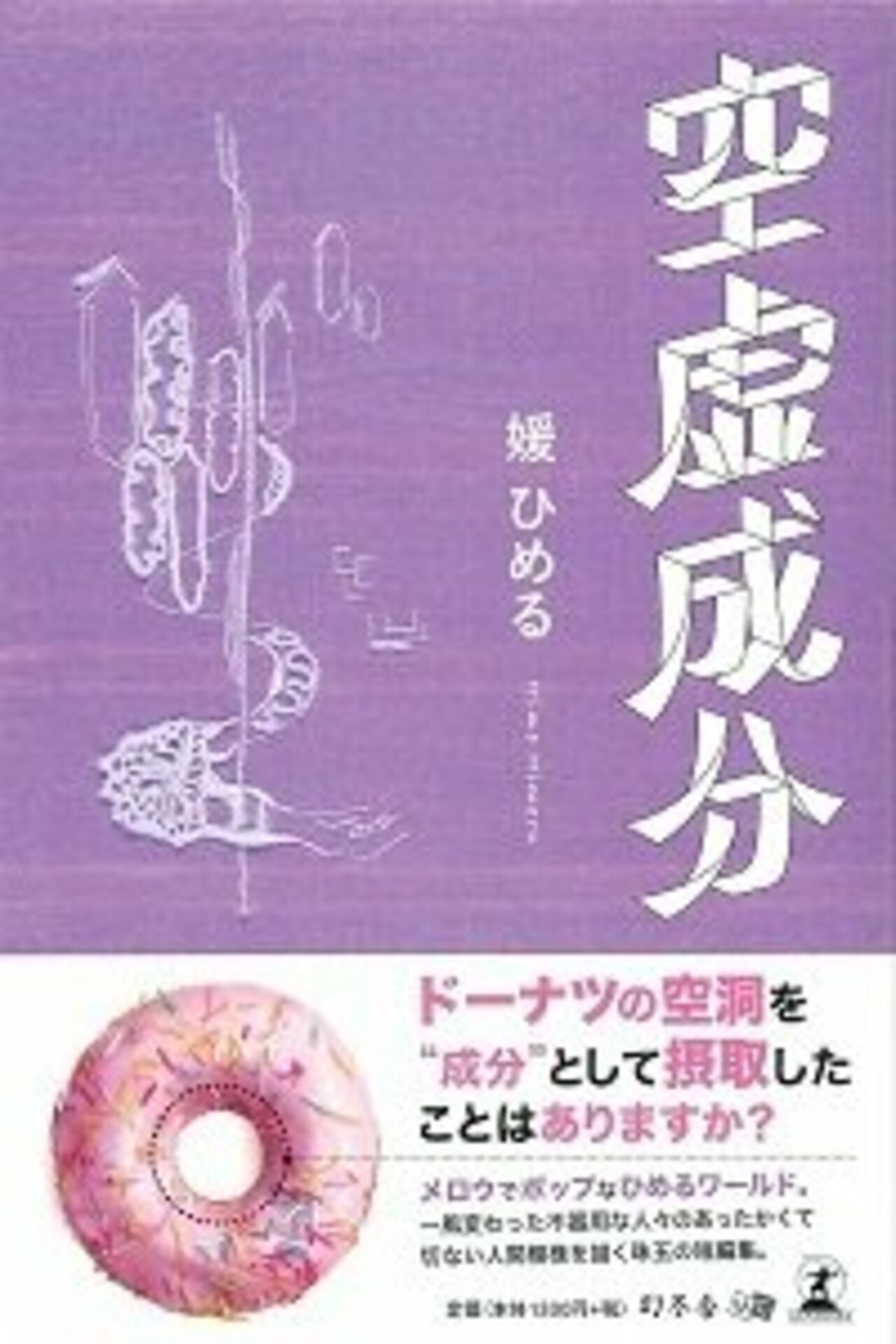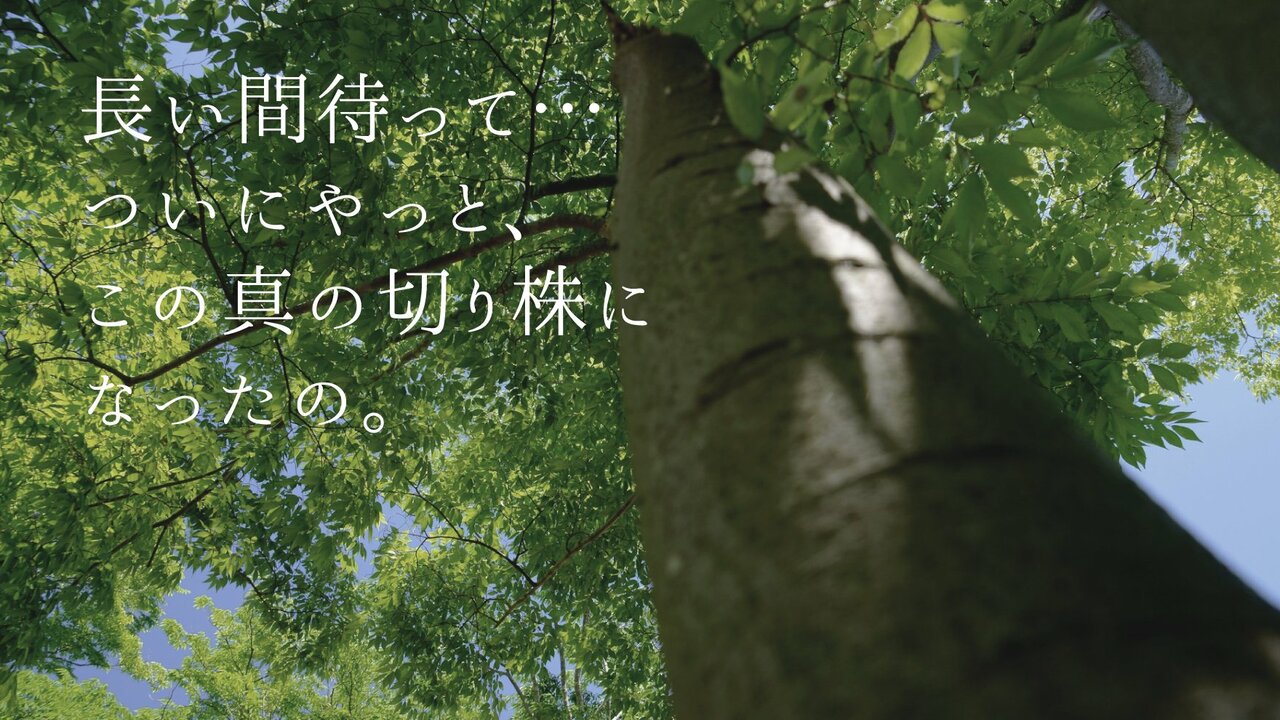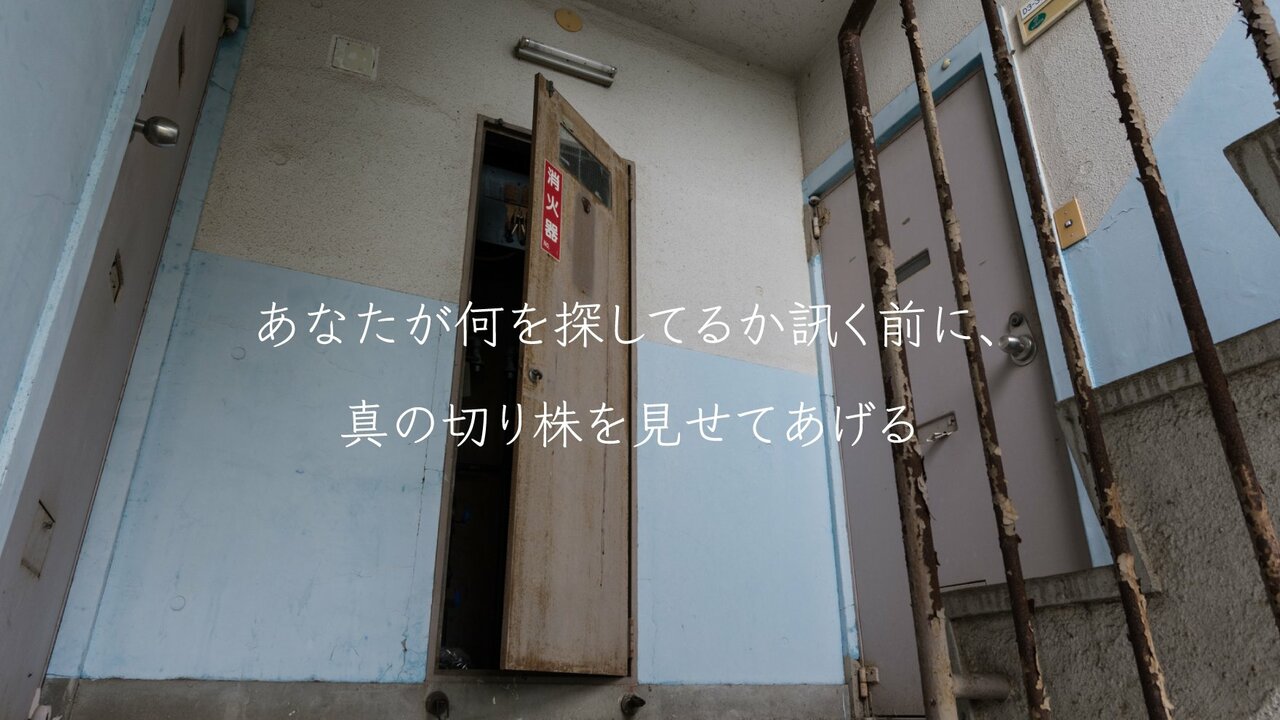ある朝目覚めた華は、学校に行く意味がどこにもなくなっていることに気付いた。授業で習うすべてのことに、すっかり興味を失っていたのだ。つい昨日まで学校に通っていた自分が信じられなかった。
何も考えず、ただ惰性で学校に行っていたのだといきなり悟った華は、その日のうちに学校の事務室に退学届けを出しにいった。誰かに相談しようとも思わなかった。
数日後、事務的な書類が家に郵送され、父親に知られるところとなった。父は毎日忙しく、家にほとんどいなかったが、書類を柚木さんから受け取ったその日の夜、華の部屋を訪れた。
ベッドに寝そべって雑誌をめくっていた華は、ドアをノックする音に驚いた。柚木さんはノックをしない。「華さん」とまず呼びかけてから、ドアの向こう側で用件を話し始める。
退学の件だ、と華は全身を緊張させた。と同時に軽い驚きを覚えた。学校をやめたことについて、父は何も言ってこないと勝手に思い込んでいたのだ。雑誌のページをめくろうとした手のまま、華はドアを見つめていた。
前回、父と面と向かって話をしたのがいつだったか思いだせない。嫌な感じの動悸がしてくる。父はなんて言うつもりだろう? だが心のどこかでは、これが正当な反応なのだ、と少しほっとしていた。
娘が学校をやめたのに何も言わない親は、普通に考えても明らかにおかしい。だが、父と面と向かうのは憂鬱だった。