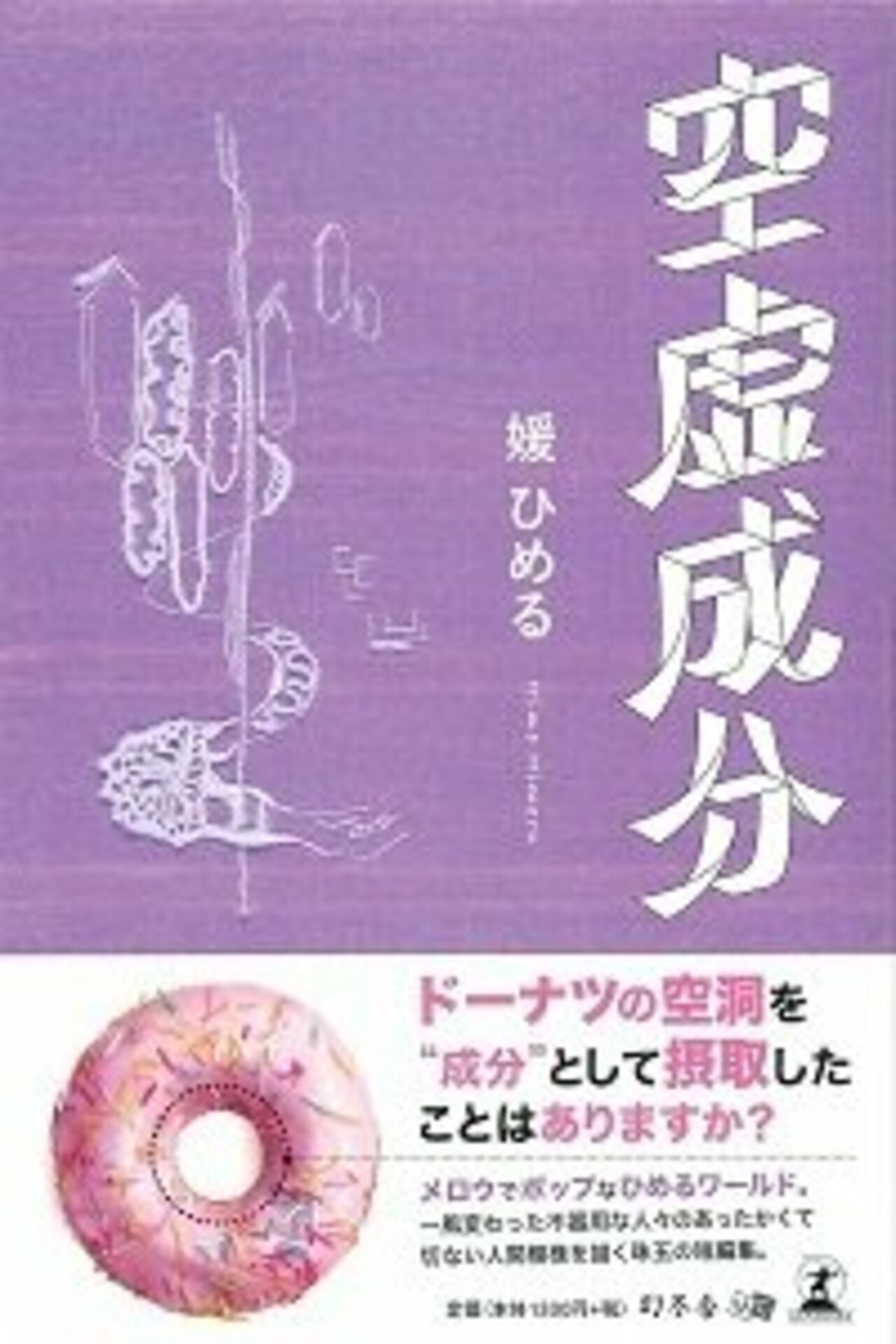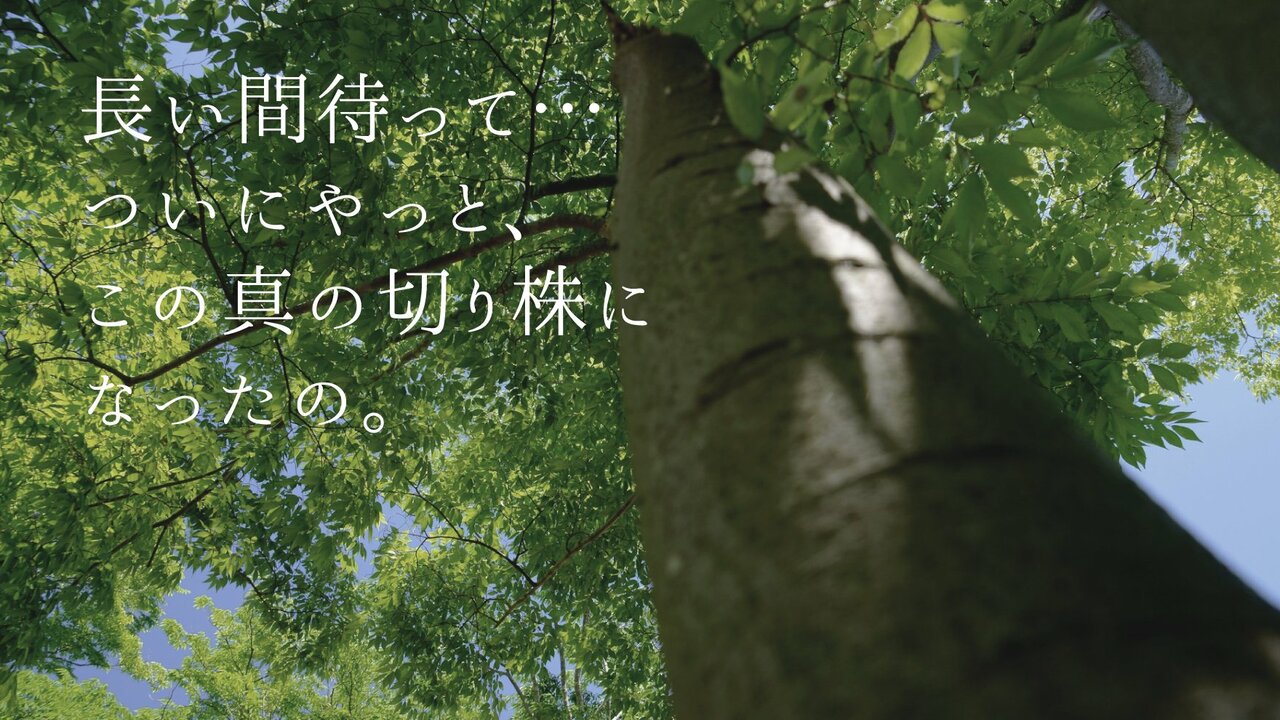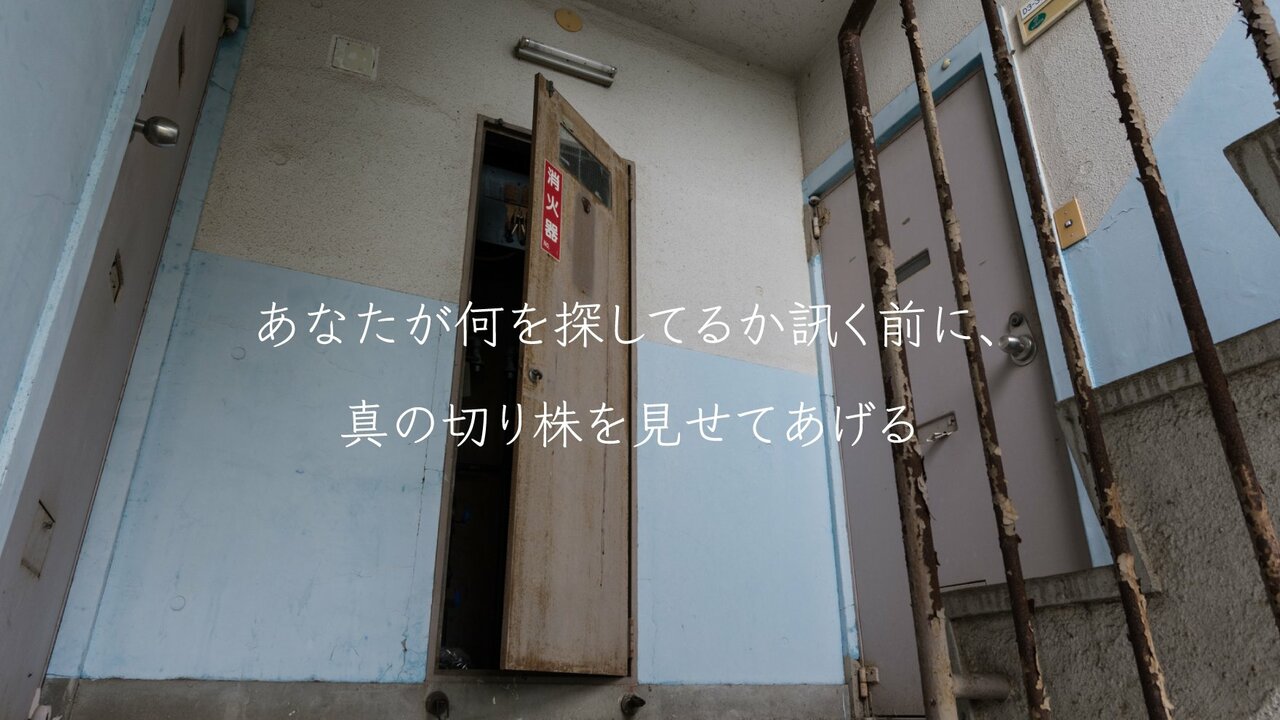くしゃみとルービックキューブ
3.
カーテンの隙間から朝日が部屋に射し込んでいる。その一筋の光は、鋭く尖った刃物のようだ。この明る過ぎる、なんだかやる気まんまんの朝日と、今日一日これから始まる膨大な時間を、忙しくしている誰かにそっくりあげてしまいたい、と華は思う。
自分は持て余すだけだから。もっと仕事や人生に燃えている人に、有効に使ってもらいたい。そもそもどうして朝など来るのだろう? 一日くらい朝が来ない日があってもよさそうなのに。なんて律儀な地球の回転。
華はベッドの中でゆっくりと体を丸めたり伸ばしたりする。そうしてイモムシみたいにもぞもぞ動いているうちに、体がシーツに染み込んでしまわないかな、とくだらないことを考える。それは毎朝の恒例の願いごとみたいなものだ。
シーツに染み込んで、完全にベッドの一部となる。できればこの世から消えてしまいたい、と華はひっそり思っている。たとえ自分がいなくなっても、当分のあいだは誰も気付かないだろう。よしんば気付いたとしても、多分なんとも思わないに違いない。
父親は自分にまったく関心がないし、家政婦の柚木さんは、ただ父に言われた通りのことをして、事務的に食事を作って置いておくだけだ。私は食べたり食べなかったりと波があるから、食事に手がつけられていなくても、柚木さんは、ああまたか、と思うくらいだろう。そして黙って食事をゴミ箱に捨てるに違いない。
柚木さんのことを、華はなんとなく、父の女版のように思っている。雰囲気や、冷たい目の光なんかが似ているのだ。そして何より二人共、華に関心がないという共通点を持っている。
福祉関係の専門学校を中退してから、華は特に何もしていない。ずっと部屋にこもっている。ひきこもり歴は今年で三年になる。三年──。貴重な青春時代を無駄にしている自覚はじゅうぶんある。世間では、恋愛に身を焦がしたり、やりたいことを見つけて邁進したりしている人もたくさんいるだろう。
そう考えると、華は体の内側が痒くなるような、ぼんやりとした焦りを感じる。だが何か手を打つわけではない。どうしたらいいのか分からないのだ。