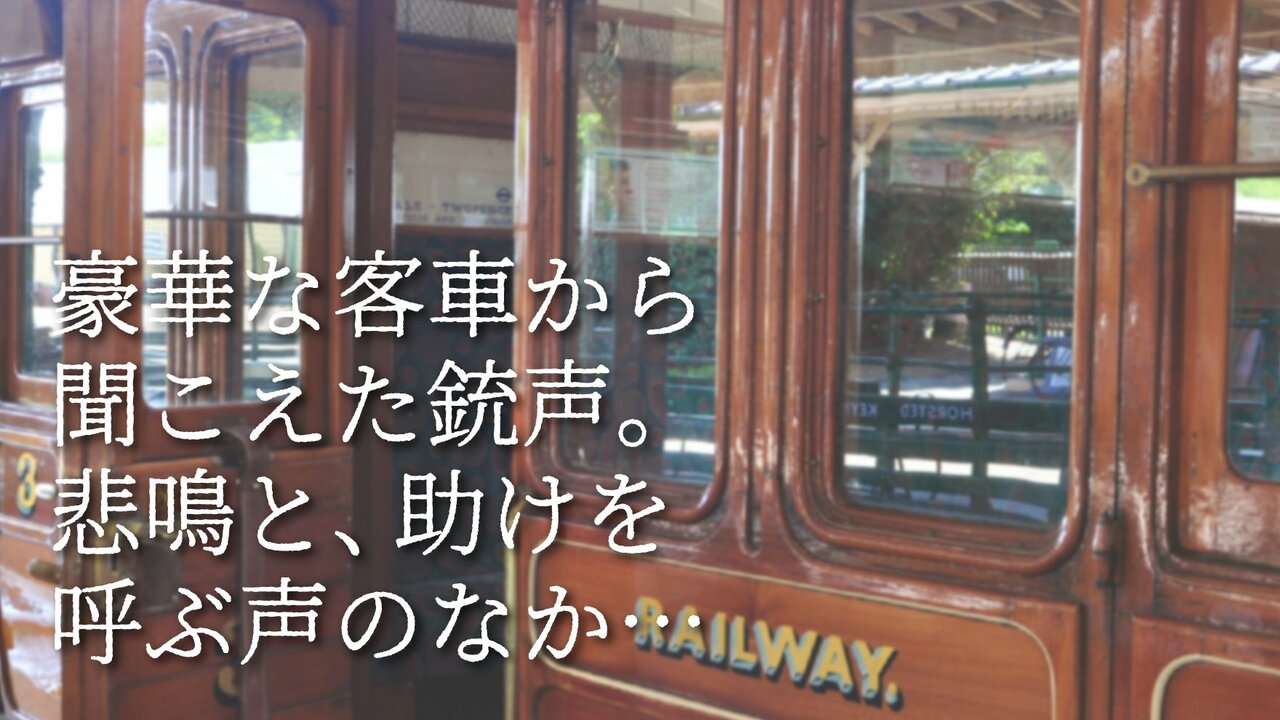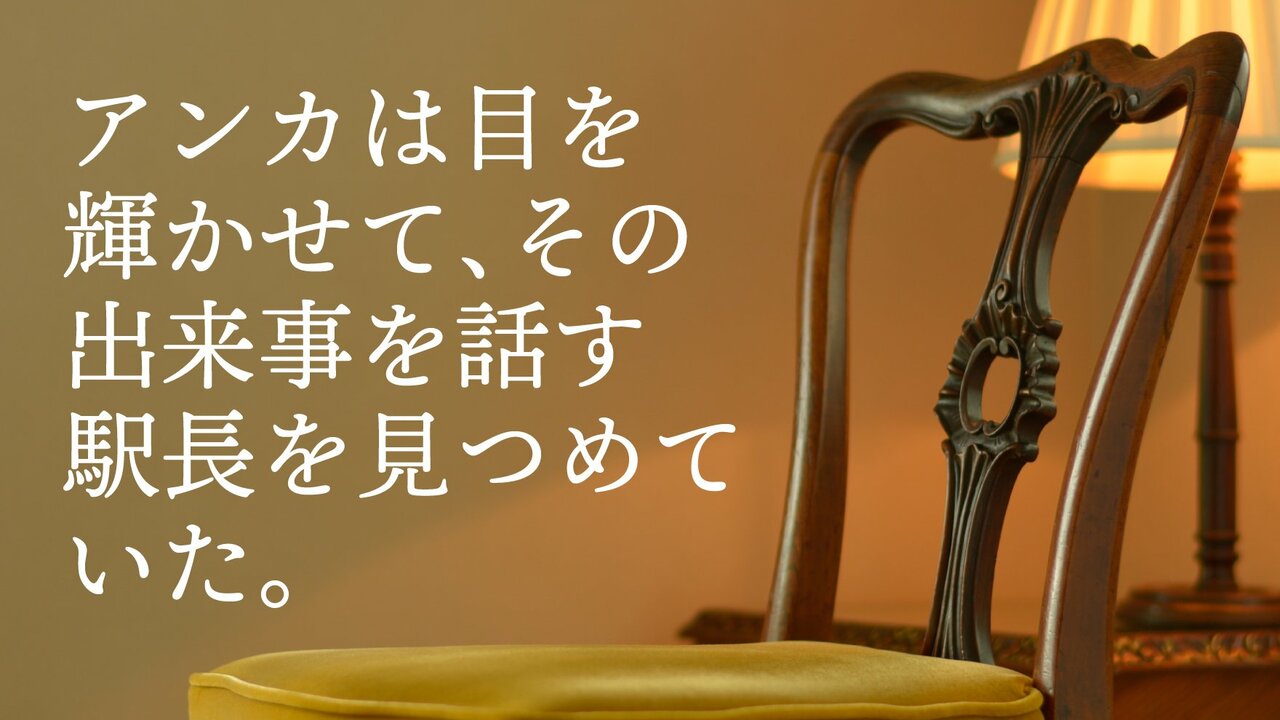プランクは自分のステータスを決して過信しなかった。彼は著名であり、尊敬され、裕福だった。彼は自分の世代の傑出した科学者たちとともに未来を創造したものの、彼はそれでも皇帝の政治上行政上の権益に依存していた。
時に一九一九年三月、世界は、テクノロジーが急速に進展していくという予感に満ち溢れた時代に踏み出していて、アインシュタイン、プランク、そしてテスラのような人たちは、明るく楽観的でありオープンな学術会議の舞台裏で暗いスパイ活動が大きな力となりつつあることに気がついていた。そのスパイ活動は、敵国に対して学術技術上のそして戦力としての覇権を確立することを切望していた。
プランクの女性助手がウィルヘルム通りにある皇帝秘密警察所属の何某と内通していることは、疑う余地はなかった。しかしプランクはこのことを受け入れ、我慢せざるを得なかった。
プランクは眼鏡を鼻に引っ掛け、黒いテーブルに戻り、両手で端っこにもたれかかった。ランプの微かな光に照らされた不思議な物体のほうを見つめ、それから大きく息を吸って、震えている手で一番近いものを持ち上げた。