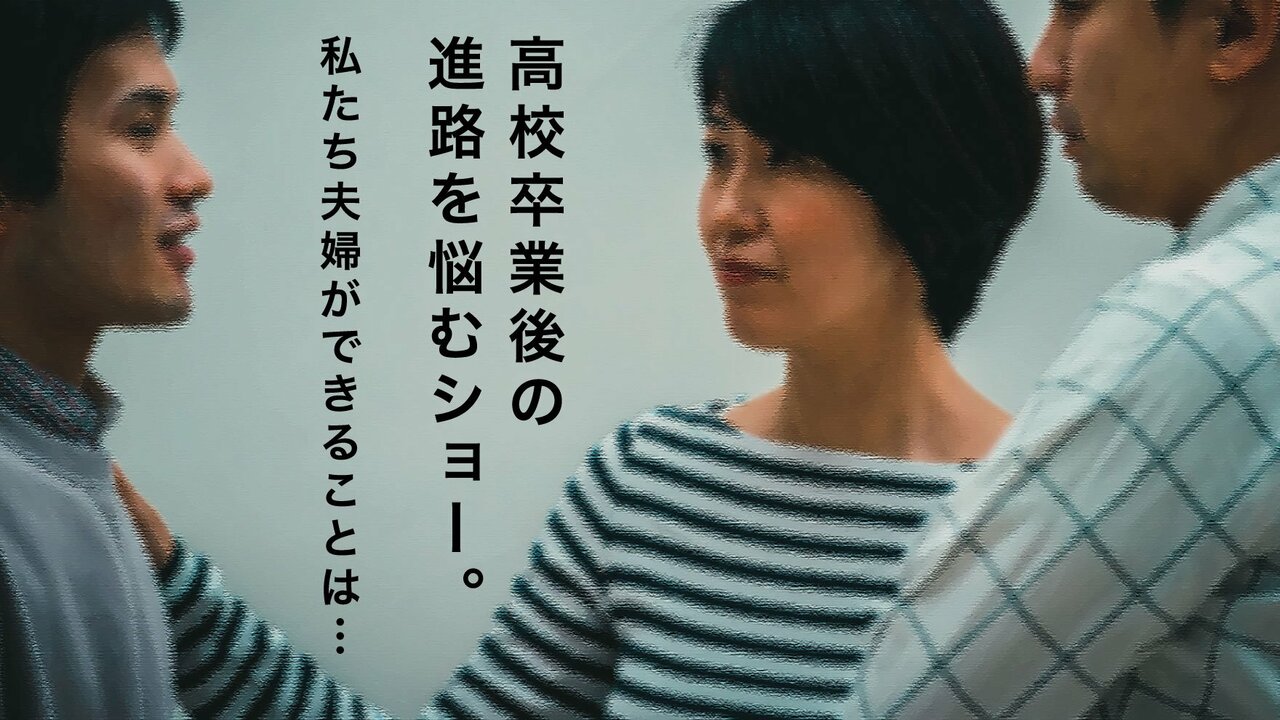第一章 ショーが居なくなった!
平成三年、ショーがまだ四歳頃の話である。私はコンピュータープログラマーであった。
毎日、毎日納期に追われ、最終電車で帰宅することは当たり前、徹夜作業になることもしばしばある。そんな生活を続けていた。
この日もいつものように残業になることを予感しながら作業を進めていた。その時、総務の女性から突然「小見山さん、家から電話ですよ」と声が掛かった。
当時は携帯電話は蔭さえ見ない時代であったので、緊急時は当然会社に連絡が入ることになる。妻からの電話だ。
大抵、家から電話があるときは良いことはない。嫌な予感を感じながら受話器を取る。
「もしもし」
受話器の向こうから、切羽詰まったような妻の細く弱々しい声が聞こえてくる。
「もしもし、あたしです。ショーが居なくなりました」
私は妻の言っていることが聞き取れず、
「え、どうしたのだ。もっと大きな声で、ゆっくり落ち着いて話してくれ」
妻は息を飲み込むと、落ち着いて話しだした。