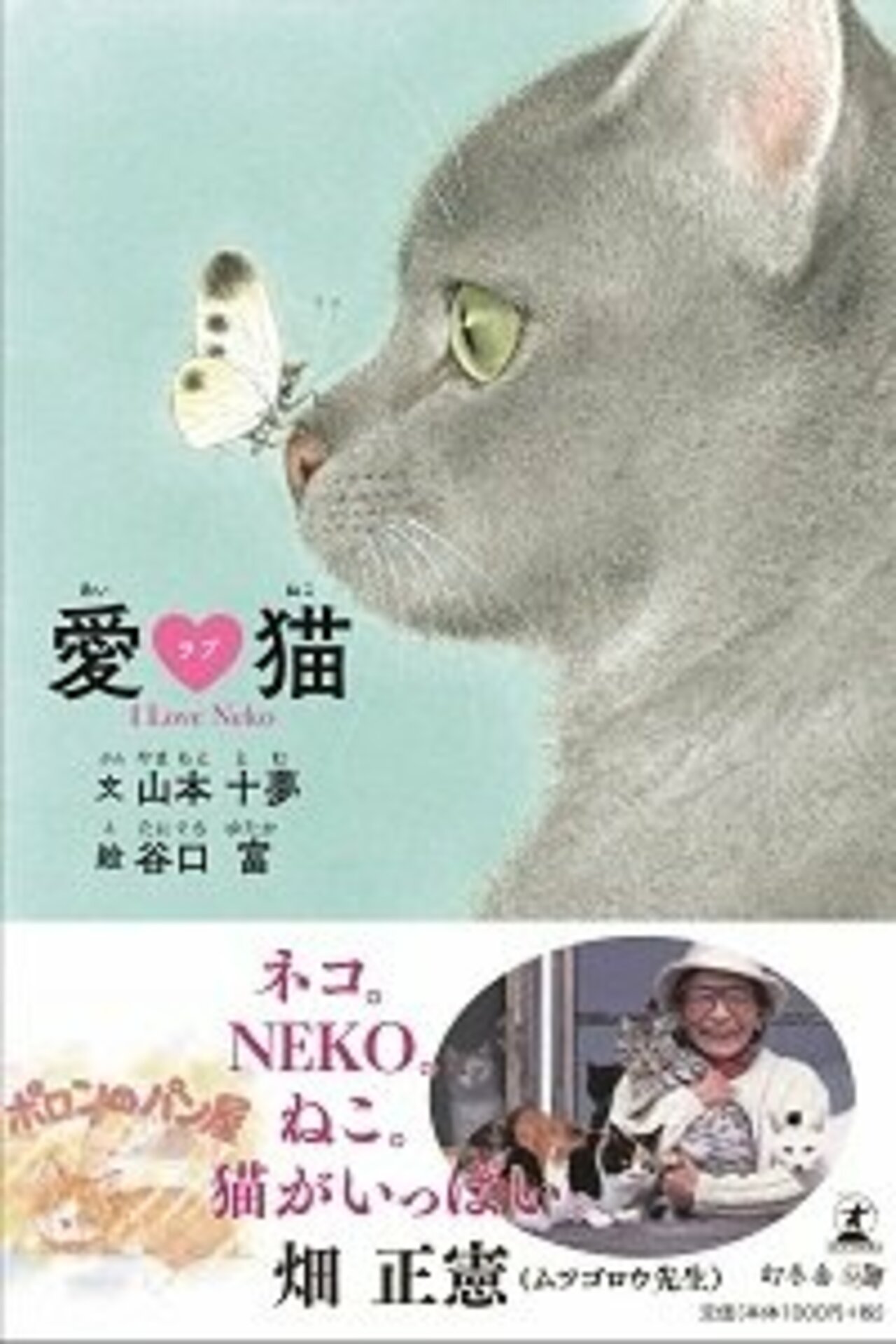パン屋のポロン
ゆれがなくなると、おじちゃんとおばちゃんは、遠くから「ポロン、ポロン」とさがしている。ぼくも、せいいっぱい「ミャーオ、ミャーオ」と応えたけれど、声が届かなかったらしい。
しばらくすると、おじちゃんの声も、おばちゃんの声も聞こえなくなった。まわりは、メロンパンのにおいでなくて、壁土のいやなにおいに変わっていた。
「どうしよう。どうやって、ここから出たらいいのかなぁ」
柱やら棚やら、いろんな物でふさがれていた。こんな大変な時に、おばちゃんが前に言っていたことを思い出したんだ。
「ポロンは暗うして、せまーかとこが、ほんに好きたい」
でも今はちがう。こんなに暗くて、せまいところなんて大きらいだ。ぼくは死にたくない!
どのくらいの時間がすぎたのかわからないけど、いくつかの小さな光が射してきた。ぼくは体を細くして、光に向かって、ゆっくりのぼっていった。
ついに外に出られた。青空がまぶしい。見まわすと、まわりの家がみんな、ぺったんこにつぶれて遠くが見えた。
「おじちゃんとおばちゃん、いったい、どこに行ったんだろう?」

ひとりぼっちのさびしさが、グッとこみあげてきた。これからどうしよう。倒れている柱で、とりあえず爪とぎをして心を落ち着かせた。
それから、おじちゃんとおばちゃんをさがしまわった。いろんな人が泣いたり、立ちすくんだり、無事を喜んで、おたがいに抱きあったり。